
発売日: 2006年3月27日
ジャンル: ポップ・ロック、アダルト・コンテンポラリー、モダンAOR
『Staying Power』は、The Holliesが2006年にリリースした通算22作目のスタジオ・アルバムであり、1960年代から活動を続ける彼らの“現役宣言”とも言える作品である。
タイトルの“Staying Power”(=持続する力)はまさに自己言及的であり、デビューから40年以上を経てもなお音楽シーンに存在感を示すことへの誇りが込められている。
本作では、アラン・クラークに代わってピーター・ハウデンがリード・ヴォーカルを務めており、世代交代後のHolliesがどのように自らの伝統を引き継ぎ、現代的なサウンドへアップデートしたかが大きな焦点となっている。
制作はモダンなAOR/ポップスのプロダクションを意識して行われ、シンセサイザーやループ・ビートを積極的に導入。
それでもなお、The Holliesの代名詞である美しいコーラス・ワークは健在であり、時代に応じて変化しながらも“声による調和”を守り抜いていることが伝わってくる。
全曲レビュー
1曲目:Hope You Find It
壮大なストリングスと洗練されたリズム・アレンジで幕を開ける、モダンHolliesの象徴的なナンバー。
“あなたが探しているものを見つけられますように”というフレーズに、長いキャリアを経た彼らの人間的な温かさが滲む。
ピーター・ハウデンの声はやや低音寄りで、アラン・クラークの繊細さとは異なる深みを持つ。
2曲目:So Damn Beautiful
メロウで滑らかなAORサウンドを基調としたラブソング。
アコースティック・ギターと電子パッドが絶妙に融合し、都会的な夜のムードを演出する。
コーラスの重なり方に、The Holliesの伝統と現代性の共存が見える。
3曲目:Prove Me Wrong
よりリズミックでR&B寄りのグルーヴを持つナンバー。
“僕が間違っていると言ってくれ”という挑発的な歌詞が印象的で、ベテランながらも挑戦的な姿勢を感じさせる。
サウンド面ではドラム・ループとシンセベースが際立ち、The Holliesが21世紀の制作環境に適応していることがよくわかる。
4曲目:Break Me
スローテンポのバラードで、現代的なエレクトロ・アレンジを採用。
ハーモニーの柔らかさとデジタルの冷たさが交錯し、心の葛藤を表現している。
ピーター・ハウデンのヴォーカル表現が光り、アルバムの感情的なハイライトのひとつとなっている。
5曲目:Shine on Me
希望をテーマにしたアップテンポのポップ・ロック。
タイトルの“Shine on Me”は、まるでバンド自身へのエールのように響く。
壮大なコーラスと明るいメロディが印象的で、ライブでも映える楽曲である。
6曲目:Suspended Animation
電子的なリズムとギターのカッティングが融合したモダン・ロック調の曲。
“時が止まったような感覚”というテーマを、クールで洗練されたサウンドで表現。
90年代後半以降のポップ・ロックにも通じる質感を持ち、彼らの柔軟な適応力が垣間見える。
7曲目:Touch Me
艶やかなシンセとボーカルの掛け合いが印象的な、現代的バラード。
“触れてほしい”という繊細な願いを、抑制されたアレンジで表現している。
ハーモニーが曲の情感を引き立て、70年代のThe Holliesにも通じるロマンティシズムを感じさせる。
8曲目:Emotions
ピアノを中心にした叙情的なナンバーで、アルバムの中でも特に静謐な空気を持つ。
タイトル通り“感情”をテーマにしており、心の内を淡々と語るような歌唱が印象的。
ストリングスとコーラスのバランスが絶妙で、現代的でありながらクラシカルな美しさを放っている。
9曲目:Weakness
グルーヴ感のあるベースラインが印象的な中期テンポのポップス。
歌詞のテーマは“人の弱さと愛の回復力”であり、年輪を重ねたバンドだからこそ響く内容。
サビでのコーラスの厚みが非常に心地よく、往年のThe Holliesファンにも訴えかける。
10曲目:Let Love Pass
“愛をそのまま通り過ぎさせよう”という、成熟した諦観を感じさせるラスト・トラック。
しっとりとしたメロディと静かな終幕が、アルバムを穏やかに締めくくる。
この終わり方には、バンドとしての円熟と平和な受容の感覚が漂う。
総評(約1300字)
『Staying Power』は、The Holliesが21世紀に入ってもなお進化を続ける姿を鮮明に刻んだ作品である。
彼らがこの時代においても“過去の遺産に頼らず、新しい音を生み出そう”としたことは驚くべきことだ。
タイトルが示す通り、このアルバムはまさに“継続する力”そのものなのだ。
まず注目すべきはサウンド・プロダクションの現代性である。
打ち込みビートやデジタル処理されたギター・トーン、シンセの多層構造など、2000年代のAORやポップスに通じるアプローチが随所に見られる。
しかし、それらの要素がThe Holliesの特徴であるヴォーカル・ハーモニーと自然に溶け合っており、“伝統と革新”が見事に融合している。
特に「Hope You Find It」や「So Damn Beautiful」では、その調和が顕著である。
ピーター・ハウデンのヴォーカルは、アラン・クラークの感傷的なトーンとは異なり、よりソウルフルで力強い。
彼の加入により、Holliesの音楽は“懐古的”ではなく“現役のポップス”として機能するようになった。
この変化は、かつてのファンにとって驚きであると同時に、バンドがいかに柔軟で誠実であるかを示す証拠でもある。
また、歌詞面でも成熟が際立つ。
“Hope”“Love”“Emotion”といった普遍的なテーマを扱いながらも、そこには年齢を重ねた者の静かな達観が漂う。
たとえば「Let Love Pass」では、若き日の情熱ではなく“受け入れる愛”が描かれており、その落ち着いた感情表現がアルバムの深みを支えている。
サウンド的にはColdplayやKeaneなど2000年代UKポップのエッセンスとも響き合い、時代との接点を感じさせる。
つまり『Staying Power』は、The Holliesが“クラシック・ロック”としてではなく“現在進行形のアーティスト”として存在するための作品だったのだ。
本作の最大の魅力は、“変わらないこと”と“変わり続けること”の両立にある。
60年代から続くハーモニーの美学を守りながら、テクノロジーを恐れず受け入れたその姿勢こそが、まさにタイトルの「Staying Power」そのものである。
この作品を通してThe Holliesは、自らの音楽的遺産を未来へと引き継ぐ“静かな革新者”としての立場を確立したのだ。
おすすめアルバム(関連・比較)
- Romany / The Hollies (1972)
初のヴォーカル交代期における意欲的作品。変化を恐れない精神が共通する。 - What Goes Around… / The Hollies (1983)
過去のメンバー復帰を経て再出発した“再生”のアルバム。 - Electric Light Orchestra / Zoom (2001)
同世代英国バンドによるモダン・ポップ化の好例。 - Paul McCartney / Chaos and Creation in the Backyard (2005)
成熟したメロディメイカーが2000年代に放った静かな挑戦作。 - Simply Red / Stay (2007)
ソウルとポップの融合をモダンに展開した同時代的AOR作品。



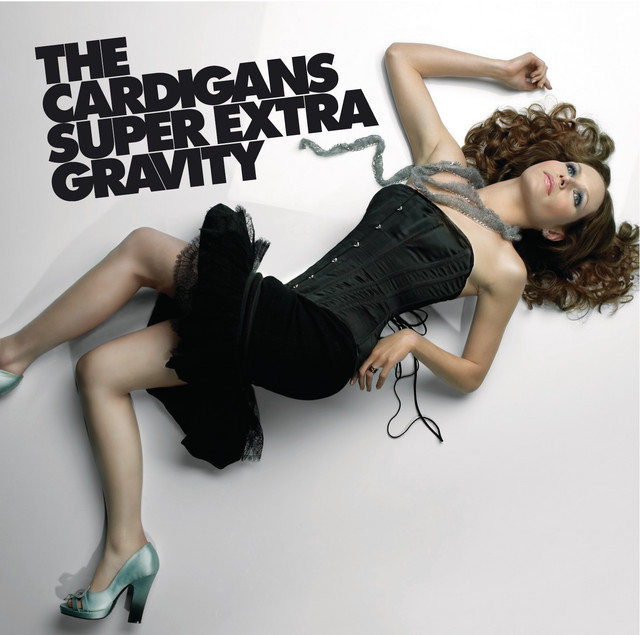
コメント