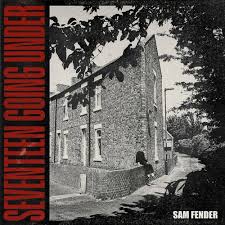
1. 歌詞の概要
「Seventeen Going Under(セブンティーン・ゴーイング・アンダー)」は、イギリス・ニューカッスル出身のシンガーソングライター、**Sam Fender(サム・フェンダー)**によって2021年にリリースされた同名アルバムのタイトル・トラックであり、彼のキャリアを決定づけた代表曲である。
この楽曲は、タイトルのとおり「17歳になるということ」がテーマだが、そこに描かれるのは青春の輝きではなく、社会の不条理に初めて直面し、“大人になること”の痛みを自覚していく過程である。父親不在の家庭、経済的困難、精神的負担、社会保障制度の冷たさ——そうした現実が、若き主人公の目の前に突如として現れる。
サウンドは疾走感のあるギターとエモーショナルなメロディが特徴的で、Bruce Springsteenの系譜を思わせる“語りと叙情”の融合が光る。だがその内側には、イギリスの労働者階級に根ざした怒りと哀しみ、そしてそれを越えていこうとする希望が確かに息づいている。
2. 歌詞のバックグラウンド
サム・フェンダーは、自身の出自を隠さず語ってきたアーティストであり、彼の楽曲の多くには北イングランドの地方都市で育った少年の視点が強く反映されている。「Seventeen Going Under」もその延長線上にあり、まさに自身の17歳時の体験を赤裸々に綴った作品だ。
彼の母親は医療従事者だったが、健康上の問題で働けなくなり、社会保障の制度に頼ることとなった。だがその過程で彼女は制度からの冷遇や精神的なプレッシャーを受ける。フェンダーは、自分の感情の起伏や怒りを当時どう処理してよいかもわからず、無力感と葛藤していたと語っている。
この曲はその時期の“心のログ”のようなものであり、サム・フェンダーにとっては青春というよりも、生存の証言であり、同時に多くの若者の“失われたティーンエイジ”への共感を呼び起こす現代のアンセムとなっている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
I was far too scared to hit him
彼を殴るには、僕はあまりにも怖がりだったBut I would hit him in a heartbeat now
でも今なら、迷わずに殴るだろうThat’s the thing with anger
怒りってそういうもんなんだIt begs to stick around
しつこく付きまとって離れないIt festers in the dark
暗闇の中で膿んでいくIt’s funny how the past keeps coming back
過去ってやつが、どうしても戻ってくるのが不思議だ
歌詞引用元:Genius Lyrics – Seventeen Going Under
4. 歌詞の考察
「Seventeen Going Under」は、単なるノスタルジーや自己憐憫ではなく、成長の痛みと怒りの源泉を冷静に掘り下げたルポルタージュのような詩である。特に注目すべきは、怒りが単に爆発するのではなく、「今なら殴れる」と過去と現在の自我を対比しながら怒りが内面化され、変質していく過程を描いている点だ。
「It festers in the dark(それは暗闇の中で膿む)」というラインは、怒りが放置されたまま心の底に溜まり続ける危険性を象徴しており、ここには少年から大人への“通過儀礼”のようなテーマが込められている。
さらに、過去の経験が未来を決定づけるのではなく、「怒りを知ることで自己を知る」プロセスとして描かれていることも、この曲の深さを物語っている。それは、フェンダーの音楽における最大の魅力——社会的リアリズムと個人的カタルシスの交差に他ならない。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- The River by Bruce Springsteen
労働者階級の若者が直面する現実と、逃れられない運命を情感豊かに描いたバラッド。 - Happier Than Ever by Billie Eilish
内面の怒りと過去への決別を、静けさと轟音の対比で表現する現代のカタルシス。 - Someone Great by LCD Soundsystem
個人の喪失とそれに伴う社会的な空洞を、淡々と語ることで逆説的に浮き彫りにした名曲。 - Spit of You by Sam Fender
父親との関係を描きながら、個人と家族の歴史に寄り添うフェンダー自身のもう一つの代表作。
6. “怒りを知ることは、自分を知ることだった”
「Seventeen Going Under」は、怒りを描いた歌でありながら、それを叫びではなく告白と観察として届けるという点で、他の多くの“若さの歌”とは決定的に異なる。ここには「僕はこうだった、だからこうなった、でもそれでいいんだ」という自己理解の物語がある。
サム・フェンダーは、自身の苦しみをパーソナルなまま語るのではなく、それを他者の声にもなりうる普遍性へと昇華させた。その姿勢が、この曲を“時代のアンセム”にしているのだ。
この曲を聴いた若者は、自分の怒りや不安が否定されるものではなく、立ち止まって見つめ直す価値のある感情だということに気づくだろう。そしてそれは、「大人になる」ということが単なる責任や諦めではなく、自己の歴史と和解しながら前に進む力を持つことであると、そっと教えてくれる。
「Seventeen Going Under」は、そんな痛みと救済のはざまに立ち続ける、現代の青年のための詩である。


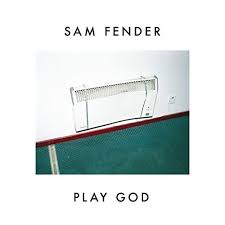

コメント