
発売日: 1981年10月16日
ジャンル: ニューウェイヴ、ポストパンク、アフロビート・ポップ
概要
『See Jungle! See Jungle! Go Join Your Gang Yeah, City All Over! Go Ape Crazy!』は、Bow Wow Wowが1981年に発表したデビュー・アルバムであり、ポストパンクとワールドミュージックが過激に交差した異端の名作として知られている。
その長大かつ挑発的なタイトルは、当時のアナーキーな若者文化や、商業化される都市社会への皮肉とユーモアを兼ね備えており、バンドの美学を象徴するものである。
Malcolm McLaren(元Sex Pistolsのマネージャー)のプロデュースのもと、元Adam and the Antsのメンバーを核に編成された本バンドは、アフリカンビート、サーフロック、パーカッションを中心に据えたサウンドで、ニューウェイヴの枠を大胆に拡張。
フロントウーマン、アナベラ・ルウィンの奔放かつ妖艶なボーカルと相まって、奇抜ながらも確かな個性を確立している。
本作は、MTV時代初期の映像革命とも呼応しながら、エスニック、性、反抗、ファッションをすべて飲み込んだポップアートとしての側面を持つ。
UKチャートでも中程度の成功を収め、以降の“ワールドポップ”の先駆けとして、カルト的支持を集めるようになった。
全曲レビュー
1. Jungle Boy
アルバムの幕開けを飾るこの曲は、プリミティヴなドラムとジャングルビートが絡むダンサブルなナンバー。
“ジャングル=都市”という比喩のもと、若者の本能と混沌が歌われる。
アナベラのヴォーカルは野生的で奔放、まさに「都会の原始人」としてのキャラクターを体現する。
2. Chihuahua
高速のパーカッションと叫ぶようなヴォーカルが交錯する、ポップと狂騒の中間にある楽曲。
「チワワ」という軽快な語感に反し、リリックには性的なダブルミーニングが含まれており、McLaren的な戦略が垣間見える。
中毒性の高いリフとリズムに支えられた、代表的キラーチューン。
3. Mickey Put It Down
無機質なギターカッティングと、軍隊的なドラムが印象的。
「ミッキー、やめてよ!」というコーラスが繰り返される中で、性別や力関係を巡るポリティクスが暗示されている。
キャッチーでありながら不穏さを孕む。
4. (I’m A) TV Savage
メディアに消費される人間像を風刺する、鋭利なメッセージソング。
「テレビの野蛮人」というセルフイメージは、MTV時代の若者の反映でもある。
ノイジーなギターと叫ぶヴォーカルが、パンクとアートポップの橋渡し的存在として機能している。
5. El Boss Dicho!
スペイン語のタイトルを冠したこの曲は、リズムの切り返しが小気味よいダンスナンバー。
ナンセンスでトリッキーな歌詞とメロディが、Bow Wow Wowらしいカラフルな混沌を生む。
6. Go Wild in the Country
シングルカットもされた代表曲のひとつ。
「都会を離れ、田舎で野生を取り戻せ」というメッセージが、過剰な文明批判とユーモアのバランスで描かれている。
サビの開放感とキャッチーさは、バンドのポップセンスを証明している。
7. I’m Not a Know It All
反抗的なテーマが全面に出たパンク寄りのナンバー。
「なんでも知ってるわけじゃない」と開き直る態度が、80年代初期の若者像と重なる。
演奏はミニマルだが、怒りと勢いに満ちている。
8. King Kong
ゆったりとしたビートとエキゾチックなギターが印象的な曲。
巨大な猿=King Kongというメタファーを通じて、性や支配、野性と理性の交差が描かれる。
ボーカルは甘く官能的で、アルバム中でも異彩を放つ。
9. Orang-Outang
アフロビートとパンクの奇妙な融合。
動物の名前を冠したタイトルが続く中で、ヒトと動物の境界線を揺るがす哲学的視点も垣間見える。
強靭なパーカッションが全編を支配している。
10. Hello, Hello Daddy (I’ll Sacrifice You)
衝撃的なタイトル通り、家父長制度や権威への反発が剥き出しになった楽曲。
性的にも挑発的な歌詞が並び、倫理とポップのギリギリを攻める。
演奏はノイジーかつミニマルで、冷笑的。
11. See Jungle! (Jungle Boy Part Two)
1曲目の続編的内容で、アルバムを物語的に循環させる役割を担う。
前曲のテーマがさらに拡張され、都市の暴力性と生存本能が再び交差する。
原始性と現代性がねじれた形で共存している。
総評
『See Jungle! See Jungle! Go Join Your Gang Yeah, City All Over! Go Ape Crazy!』は、単なるニューウェイヴ・ポップにとどまらず、ビート、ファッション、セクシャリティ、そしてサブカルチャーを横断する異端の名盤である。
その挑発的なサウンドとヴィジュアル、そしてジャンルを横断するリズム構造は、のちのワールドビートやポストポップに先駆ける要素を多分に含んでおり、当時の商業的ポップとは一線を画す存在感を放っていた。
アナベラ・ルウィンの妖精的かつ獰猛なボーカルは、ロリータ性と権力性のせめぎあいをそのまま体現しており、バンドが孕んでいた危うさとエネルギーを象徴している。
Malcolm McLarenの手腕によるプロデュースとアート戦略が功を奏し、このアルバムはただの音楽作品ではなく、文化的事件として記憶されるに値する。
ポストパンクの実験精神とダンスビートの身体性を統合しながら、文明批判と野性への回帰という矛盾を内包した『See Jungle!』は、今なお“おとなしいポップ”では得られない快楽と混乱を私たちに与えてくれる。
おすすめアルバム(5枚)
-
Adam and the Ants / Kings of the Wild Frontier (1980)
メンバーが共通し、アフリカンリズムとポストパンクが融合した先行作。 -
The Slits / Cut (1979)
フェミニズムとレゲエ/パンクの交差点にある、革新的ポストパンク。 -
Tom Tom Club / Tom Tom Club (1981)
ファンキーでエキゾチックなポップの先駆者的作品。 -
Lizzy Mercier Descloux / Press Color (1979)
パリとニューヨークをつなぐ、前衛ニューウェイヴとワールドビートの奇跡。 -
ESG / ESG (1981)
リズム主体のポストパンク〜ダンスミュージックを切り拓いたカルト名盤。


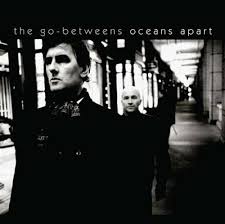

コメント