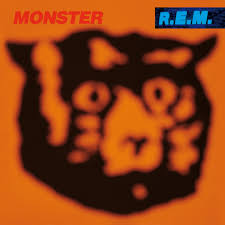
発売日: 1994年9月27日
ジャンル: オルタナティヴロック、グラムロック、ノイズポップ、ガレージロック
概要
『Monster』は、R.E.M.が1994年にリリースした9作目のスタジオ・アルバムであり、“静けさ”を極めた前2作から一転、ノイジーでエレクトリックな“バンド回帰”を果たした異色作である。
『Out of Time』(1991)と『Automatic for the People』(1992)で世界的な成功を収めたR.E.M.は、
そこではアコースティックな音像と内省的なテーマが中心だった。
だが本作ではそれらを意図的に反転させ、**ラウドでグラマラス、そしてフィクショナルな“音の仮面劇”**を展開している。
この変化には、長らく控えていた大規模ワールドツアー再開の前哨戦という意味もあり、
R.E.M.はあえて“ノイズとロール”の世界へと足を踏み入れた。
サウンド面ではディストーションギターが支配的で、マイケル・スタイプのボーカルにはヴォコーダーやエフェクト処理も多く用いられ、
歌詞も現実の自分ではなく**“他者の視点や虚構のキャラクター”**として語られる。
これは“自己”を脱構築するスタイプの美学と、グランジ/オルタナ以降の90年代的価値観を体現している。
全米チャート1位を獲得し、商業的にも成功。だが、その強烈な音像と虚構性ゆえに、当時から賛否両論を巻き起こした、R.E.M.史上もっとも分裂的で挑戦的なアルバムである。
全曲レビュー
1. What’s the Frequency, Kenneth?
CNNを襲撃した犯人の謎めいた言葉を引用した、90年代メディア時代への皮肉。
鋭いディストーションギターと語りのようなボーカルが、情報過多の世界での認識の混乱を表現する。
R.E.M.の“グランジ的変身”を象徴する幕開け。
2. Crush with Eyeliner
クールでグラマラスなギターリフと、スタイプのウィスパーボイス。
性的曖昧さやナルシシズムが漂い、デヴィッド・ボウイ以降の“演じるロックスター像”へのオマージュにも聞こえる。
ソニック・ユースのサーストン・ムーアがゲスト参加。
3. King of Comedy
ファズベースと打ち込みが特徴の、機械的で歪んだファンクロック。
「君たちが望むものを、僕は全部あげるよ」という一節に、ポップスターの虚像とパフォーマンスの暴力性が滲む。
4. I Don’t Sleep, I Dream
ミッドテンポのナイトソング。
“眠らずに夢を見る”というフレーズが、性的幻想と不眠症的現代人の心象風景を重ねる。
スタイプの低音ヴォーカルが官能的。
5. Star 69
電話番号“69”のダブルミーニングを使った、パンク色の強いアップテンポ。
追跡、盗聴、忘れられない言葉──都市の妄想と執着を短く鋭く描く。
6. Strange Currencies
本作中もっともエモーショナルなバラード。
不器用な愛と、拒絶されてもなお伝えたい想いが込められている。
『Automatic〜』の哀愁を引き継ぎながらも、歪んだギターに感情を包んだ異色のラブソング。
7. Tongue
ファルセットとオルガンを用いたスロウでセクシュアルなナンバー。
ボーカルはあえて女性的に演じられ、“性の視点の入れ替え”というテーマが静かに浮かび上がる。
8. Bang and Blame
ファンクとグランジの中間のようなリフで展開される楽曲。
「責任を押し付けて、音を立てて消えていった」というリリックは、関係の崩壊と責任転嫁の心理を突き刺す。
9. I Took Your Name
攻撃的なギターと「お前の名前を盗んだ」という執着的なリフレイン。
アイデンティティの混乱、欲望の象徴性を扱ったディストピア的ナンバー。
10. Let Me In
カート・コバーンに捧げられた追悼曲。
ギターはピーター・バックではなく、マイク・ミルズが担当。
ノイズの壁の中から聞こえてくるスタイプの声は、悲しみと鎮魂、そして無力さを淡々と語っている。
11. Circus Envy
アグレッシブでカオティックなロックチューン。
サーカス、嫉妬、狂気──制御不能な感情の暴走がテーマで、R.E.M.の“最も危険な音”のひとつ。
12. You
ベースが主導するミニマルなクロージング。
“君”に語りかけるようで、実は“語り手の分身”なのかもしれない。
アルバム全体の“虚構と真実の入れ子構造”を締めくくる謎めいたエンディング。
総評
『Monster』は、**R.E.M.が自らの“静かなる神話”を壊し、ノイズとフィクションの中へ飛び込んだ“変身のアルバム”**である。
それはグランジの流行に乗ったというより、むしろ90年代の文化的空気(性的流動性、メディアの飽和、個の拡散)を鋭く先取りした実験的ポップとして機能していた。
スタイプが“自分ではない誰か”になりきることで語られる歌詞は、
ロックスターとは何か、語るとはどういうことか、を逆説的に照らし出している。
また、過剰なツアー、メンバーの病気、音楽業界との軋轢といった背景も重なり、このアルバムは“快楽の影”に覆われた、祝祭と崩壊の記録でもある。
R.E.M.の中でも最も誤解され、最も再評価されつつある本作は、
いま聴くとむしろ、ポストモダンの不安と自由を引き受けた、最も1990年代的な傑作である。
おすすめアルバム(5枚)
- David Bowie / Scary Monsters (And Super Creeps)
ロックスターの自己解体とグラム性の再構築という意味で共鳴する作品。 - Nirvana / In Utero
内省とノイズ、メディアとの距離感を模索した、カート・コバーンの遺言。 - Radiohead / The Bends
感情と轟音の境界で揺れ動くオルタナティヴロックの代表作。 - Pixies / Bossanova
サーフロックとノイズの混交、演技と本音の曖昧さが近似している。 - Placebo / Without You I’m Nothing
性的アイデンティティとフィクション性が混じり合った90年代後期の後継的存在。
ビジュアルとアートワーク
アルバムジャケットには、オレンジがかったざらついた画質の熊の顔が大写しにされており、威圧と滑稽、現実と幻影が交錯する不穏な視線を放っている。
フォントも粗く、ノイズ加工が施されたようなロゴは、まさに“モンスター=匿名的で異質な存在”の象徴。
このビジュアルは音と歌詞の方向性と密接にリンクしており、
**“R.E.M.という名の怪物が、誰かになりすまして語る物語”**というコンセプトを補完している。
『Monster』は、ロックバンドとしてのR.E.M.がもう一度“音を出すことの快感とリスク”を引き受けた、変身のグラムロック・ドキュメントなのである。


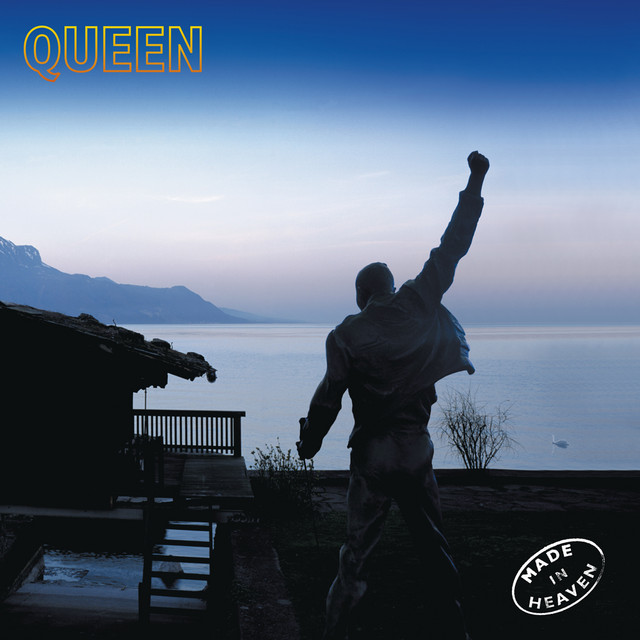
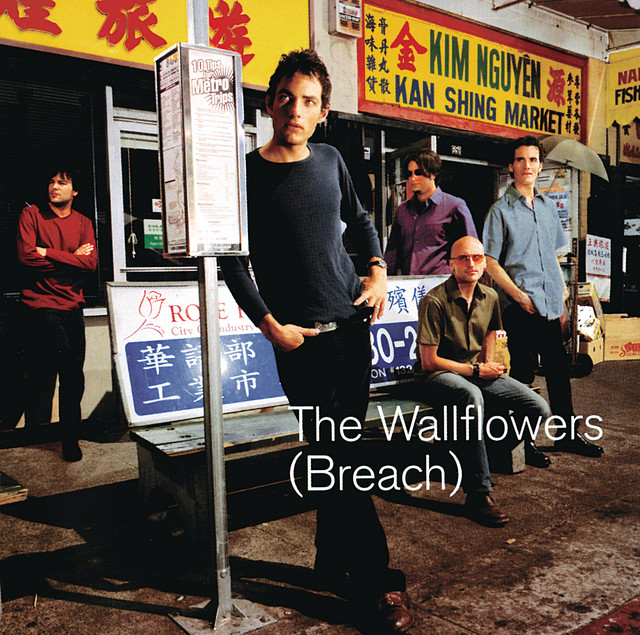
コメント