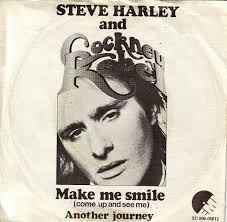
1. 歌詞の概要
「Make Me Smile (Come Up and See Me)」は、イギリスのグラムロック/アートロック・バンド、スティーヴ・ハーレイ&コックニー・レベル(Steve Harley & Cockney Rebel)が1975年に発表した代表曲であり、全英シングルチャートで堂々の1位を獲得した、バンド最大のヒット曲である。
その軽快で耳に残るアコースティックギターのイントロと、どこか茶目っ気のあるメロディ、そして艶のあるハーレイの歌声が特徴的だが、歌詞には意外にも強烈な“怒り”と“裏切りへの皮肉”が込められている。
一見すると「Come up and see me, make me smile(こっちにおいでよ、僕を笑わせてよ)」という甘い誘い文句に聞こえるが、実際にはそれは痛烈なアイロニーであり、バンドを離れた元メンバーたちに対する“勝者の嘲笑”でもある。つまりこれは、恨み言ではなく、皮肉というスタイルでリベンジを果たした、非常にパーソナルな楽曲なのだ。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Make Me Smile」は、スティーヴ・ハーレイが自身のバンドから脱退したオリジナルメンバーたちに向けて書いた、事実上の“別れの歌”である。コックニー・レベルはもともと彼のプロジェクト的バンドとして始まり、グラムやアートロックを融合したユニークなスタイルで知られていたが、商業的な成功を前にして内部分裂が起き、他のメンバーがハーレイの意向に反旗を翻す形で離脱した。
この曲が録音されたのは、1975年のアルバム『The Best Years of Our Lives』のセッション中。ハーレイは元メンバーに対する苛立ちと失望を、あえて明るくキャッチーなポップ・チューンの中に包み込み、その“笑顔”の裏に真のメッセージを仕込んだ。
レコーディングには当時の名うてのミュージシャンが多数参加しており、プロデュースを担当したのはアラン・パーソンズ。軽快ながらもどこかシアトリカルなアレンジは、ハーレイの演劇的センスを見事に引き出している。
3. 歌詞の抜粋と和訳
You’ve done it all, you’ve broken every code
やれることは全部やったろ、どんなルールも破ってきたよなAnd pulled the rebel to the floor
反逆者を地に倒してさYou spoilt the game, no matter what you say
君が何を言おうと、ゲームを壊したのは君だFor only metal, what a bore
その目的が金だったとはな、つまらないやつだCome up and see me, make me smile
会いに来いよ、笑わせてみろよOr do what you want, running wild
好きにするがいいさ、勝手に暴れてな
(引用元:[Lyrics.com – Make Me Smile (Come Up and See Me)](https://www.lyrics.com/lyric/2824769/Steve+Harley/Make+Me+Smile+(Come+Up+and+See+Me)))
皮肉の効いた語り口と、“笑顔”の中に宿る怒りの熱――その両面性がこの曲の最大の魅力である。
4. 歌詞の考察
この楽曲がユニークなのは、怒りや失望といったネガティブな感情を、激しいロックではなく、軽やかなアコースティックとポップなメロディに包み込んで表現している点にある。それにより、聴き手は一度は“明るく親しみやすい曲”だと錯覚するが、歌詞に耳を傾けることで、その背後にある複雑な感情を徐々に知ることになる。
“Make me smile”というラインも、表面的にはユーモラスだが、実際には「僕のことを笑わせるつもりか?」「本気でそう思ってるのか?」という、怒りを抑えた冷笑とも取れる。まるで舞台の上で仮面をつけたピエロのように、ハーレイは“笑い”を演じながら、その奥にある復讐の炎を燃やしているのだ。
「金(metal)だけが目的だったのか」「ゲームを壊したのは君だ」――こうしたラインは、音楽における理想と現実、創造と欲望の衝突を鋭く描き出している。裏切りを経験したからこそ書けた曲であり、彼が“言い返す”ための、しかし優雅で洗練された手段でもあった。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Ballroom Blitz by Sweet
グラム・ロック的な派手さとユーモアが共通。騒がしい中にも演劇的な構成が魅力。 - Coz I Luv You by Slade
グラム期の親しみやすいメロディと独特の口語表現が「Make Me Smile」と共鳴。 - Virginia Plain by Roxy Music
アートロックとポップの境界を軽やかに越える、70年代イギリスの知的ポップ。 - Life on Mars? by David Bowie
音楽業界の裏と表、夢と現実を切なく歌い上げた代表曲。ハーレイの皮肉と対照的な美学。
6. 裏切りと芸術、ポップと皮肉の交差点
「Make Me Smile (Come Up and See Me)」は、ポップでキャッチーな“ヒット曲”でありながら、実際には極めて私的で、アーティストの内面を鋭くえぐった一曲である。その成功は、単に音楽的センスの勝利というよりも、感情の処理の仕方として「怒りをエレガンスに変換した」ことにあった。
この曲によって、スティーヴ・ハーレイは音楽的にも精神的にも“勝者”となった。自らが裏切られた出来事を、怒鳴り散らすのではなく、ウィットと音楽で包み込み、しかもそれがチャート1位を記録するという皮肉なカタルシス。そう、彼にとってこの曲は報復であり、復活であり、そして“最後の笑い”なのだ。
その後もこの曲は映画やCMで繰り返し使用され、イギリス国内では“ポップ・クラシック”として定着した。だが、ただの懐メロとして消費されるには惜しい。そこには、アーティストとしての矜持と、皮肉な勝利の微笑みが今もなお刻まれている。これは、ポップの仮面を被った、一つの“文学的な復讐劇”なのである。


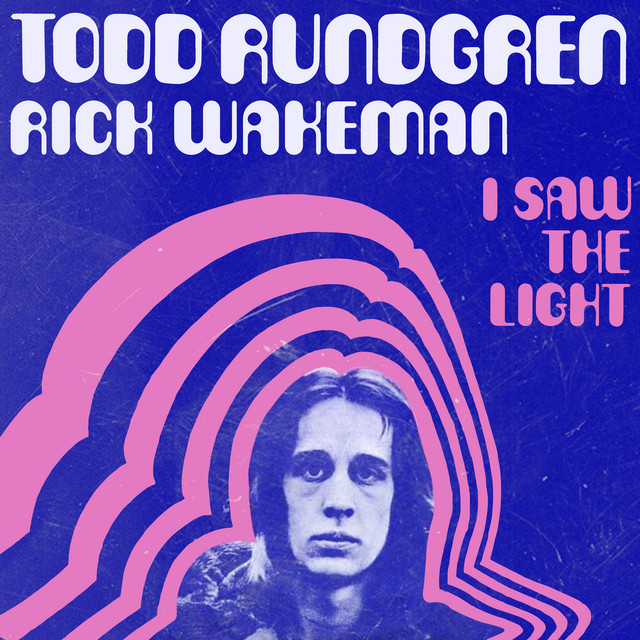
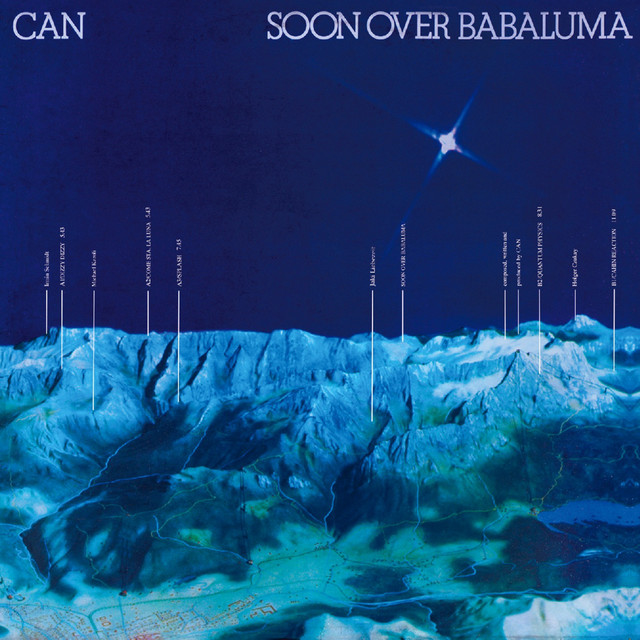
コメント