
発売日: 2013年10月8日
ジャンル: サイケデリック・フォーク、カントリー・ロック、ローファイ・ポップ
アメリカーナと詩的暴力の交錯——of Montrealが原点へ還り、言葉で切り刻んだ旅の記録
『Lousy with Sylvianbriar』は、of Montrealが2013年に発表した12作目のスタジオ・アルバムであり、エレクトロ期以降の奔放なファンク/グラム路線から一転、60〜70年代のアメリカーナやサイケ・フォークに回帰した異色作である。
ロサンゼルスからサンフランシスコ、アメリカ西部を巡る旅の中で、ケヴィン・バーンズが書きためた詩と日記。それをもとに、“完全アナログ録音・ワンテイク収録”という荒々しい制作手法でまとめあげたのが本作である。
Bob Dylan、Neil Young、The Byrds、Grateful Deadといったレジェンドたちの影を感じさせながらも、その詞世界はまぎれもなく現代的で、愛、別離、ナルシシズム、暴力性、精神疾患、創造の孤独といったテーマがむき出しのままに歌われる。
グラムやファンクで耽美に包んできた自意識を、ここでは“言葉”と“生音”で剥き出しにするような痛烈な一撃が込められているのだ。
全曲レビュー
1. Fugitive Air
開幕を飾る、ザラついたガレージ風フォーク・ロック。怒りと自己嫌悪が激しく交錯し、耳を突き刺すような迫力を持つ。
2. Obsidian Currents
呪術的なコード進行と曖昧なメロディ。愛と破壊を巡る冷たい視線が印象的で、まるで詩の断片が浮遊しているかのようだ。
3. Belle Glade Missionaries
アメリカ南部の宗教的風景を背景に、暴力と洗脳を描いた社会批評的楽曲。Bob Dylan的な政治的レトリックも香る。
4. Sirens of Your Toxic Spirit
アコースティックなサウンドで綴られる内省的バラード。自己破壊的な恋愛に囚われた心の揺れを淡々と描いている。
5. Colossus
語りのような前半から、爆発的に展開する後半へ。アルバム中もっともドラマチックな構成を持つナンバー。
6. Triumph of Disintegration
躁うつ的な感情の流れが、タイトルそのままに崩壊と歓喜の間を振り子のように行き来する。Neil Youngを思わせるギター・トーン。
7. Amphibian Days
繊細で憂いを帯びた楽曲。自己否定と幻想逃避が絡み合う、夢うつつの中での回想。
8. She Ain’t Speakin’ Now
失語症のように沈黙する恋人との距離を描いたフォーク・ロック。切なさと怒りの間で揺れるボーカルが痛ましい。
9. Hegira Émigré
アルバム中もっともサイケデリックな楽曲。ボードレールの詩のように、旅と退廃、逃避願望が詰まった詩的構成。
10. Raindrop in My Skull
不穏な言葉のリズムが繰り返される、呪文のようなミニマル・フォーク。ケヴィンの詩人としての側面が浮き彫りになる一曲。
11. Imbecile Rages
最後を飾るのは、言葉による暴力と愛の屈折した表現。叫びにも似たボーカルが、アルバムを痛烈に締めくくる。
総評
『Lousy with Sylvianbriar』は、of Montrealが過剰な装飾を脱ぎ捨て、アメリカーナと詩によって再構築された“素の表現”の到達点である。
録音方法を含め、作品全体に流れるのは「即興性」と「不完全さ」の美学。完璧に磨かれたポップではなく、傷やノイズを伴ったまま感情を音に刻むという決意がここにはある。
歌詞は時に攻撃的で、時に繊細に崩れ、まるで詩集とロードノベルが融合したような構造を持っている。その分、リスナーに解釈を委ねる余白も多く、読み込むほどに深く沈み込んでいく。
これは「偽りの司祭」以後のバーンズが、いったん仮面を外し、“アメリカの風景と人間の弱さ”を真正面から見つめ直したアルバムなのだ。派手さはないが、彼のキャリアでもっとも誠実で、もっとも鋭い作品のひとつである。
おすすめアルバム
-
Harvest / Neil Young
アコースティックと内省が結びついたアメリカーナの金字塔。音の手触りが共通する。 -
Bringing It All Back Home / Bob Dylan
詩的レトリックと社会批評が融合した、60年代のポップ革命的作品。 -
Tanglewood Numbers / Silver Jews
ローファイ・ロックと詩的世界観の融合。崩れた美しさが印象的。 -
I See a Darkness / Bonnie “Prince” Billy
静かに突き刺すような痛みを持つオルタナ・フォークの傑作。 -
A Crow Looked at Me / Mount Eerie
死や喪失を“装飾ゼロ”で語る極限の個人表現。バーンズの誠実な詩性と響き合う。


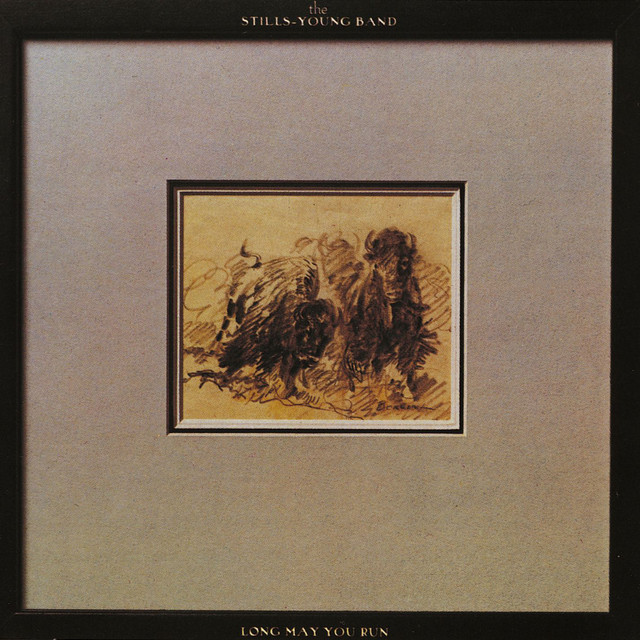
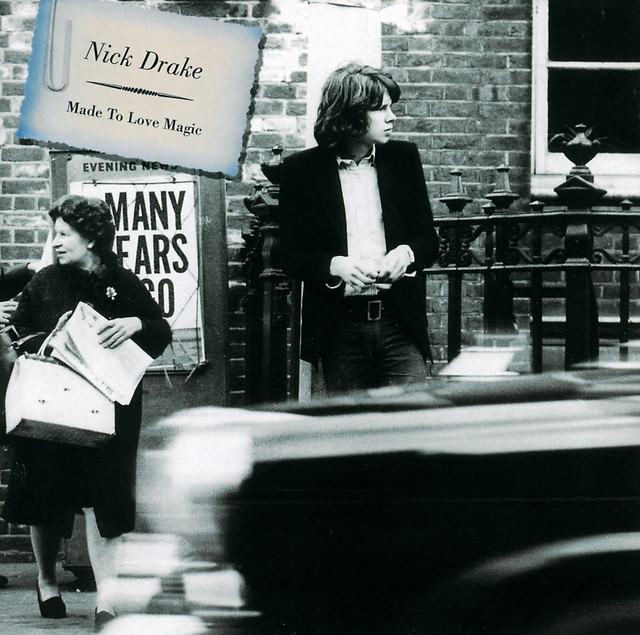
コメント