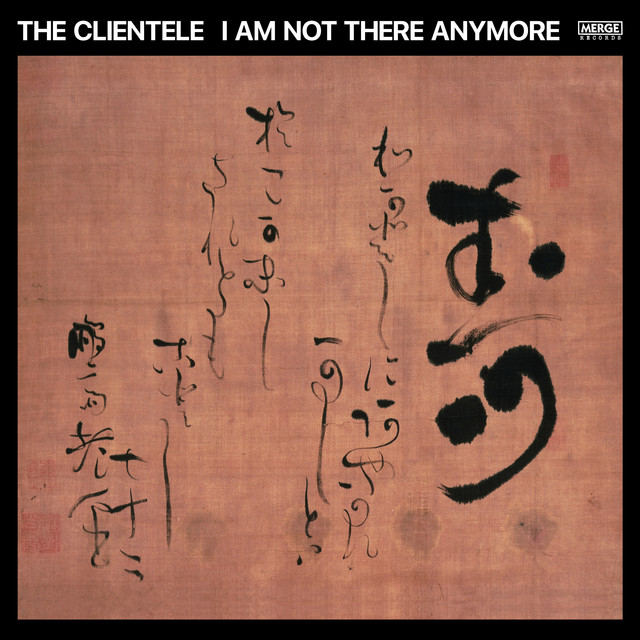
発売日: 2023年7月28日
ジャンル: ドリームポップ、室内楽ポップ、ポストクラシカル、サイケデリック・フォーク、ネオアコースティック
『I Am Not There Anymore』は、The Clienteleが2023年に発表した約6年ぶりとなる7作目のスタジオ・アルバムであり、彼らのキャリアにおける最も実験的で野心的な作品である。
タイトルが示すとおり、本作には「記憶の喪失」「場所と時間の乖離」「自己の消失」といった主題が貫かれており、これまで以上に詩的かつ構造的なアプローチによって、夢と現実、過去と現在が断片的に編み込まれている。
Alasdair MacLean率いるThe Clienteleは、長年にわたって“静かな風景と記憶”をテーマに音楽を紡いできたが、
本作ではその内向性と美学がついに「構造化された迷宮」へと進化を遂げた。
ストリングスや木管、ピアノ、フィールドレコーディングはもちろん、複数の朗読やミニマリズム的インタールードも大胆に導入。
クラシック、フォーク、アンビエント、サイケ、エレクトロニカが違和感なく融合し、バンドの核はそのままに、まるで音楽による記憶のコラージュのような世界が展開される。
本作はまた、約64分に及ぶ大作であり、通して聴くことで得られる“時間の揺らぎ”と“空間の歪み”の体験は、従来のアルバム単位の聴取を超えるリスニング体験となる。
「私はもうそこにいない」という言葉の通り、このアルバムそのものが「存在しない場所」への旅の記録なのだ。
全曲レビュー(主要曲中心)
1. Fables of the Silverlink
11分を超えるオープニング曲にして、まるで映画の序章のような構成美。
時間、記憶、喪失を語るMacLeanのリリックが、メロディとポエトリー、環境音のコラージュに乗せられ、物語を始動させる。
“The Silverlink”という消えた鉄道が、物理的にも象徴的にも中心となる。
2. Garden Eye Mantra
中盤のインタールードでありながら、アルバムの音楽的・象徴的テーマを凝縮したような楽曲。
サントゥール、語り、エレクトロニカ的断片が融合し、“形を持たない記憶”のような不定形な美しさが漂う。
3. Lady Grey
メランコリックで美しいバロック・ポップの佳曲。
『Strange Geometry』や『Bonfires on the Heath』を想起させるような親しみあるメロディと、時間と記憶の詩学を組み合わせたリリックが秀逸。
4. Dying in May
季節と死、別れを静かに描いたセンチメンタルな楽曲。
室内楽のようなアレンジと、囁くようなボーカルが、まるで時間が止まったかのような静けさを生む。
5. Blue Over Blue
比較的ポップで明快な旋律を持つ曲であり、アルバムの中でも耳馴染みの良いナンバー。
“青の向こうの青”という表現が、空間と感情のグラデーションを示す。
6. Claire’s Not Real
存在しない“クレア”という人物を巡る幻想的なナンバー。
現実と虚構のあわいにある記憶装置としての人物描写が、語りのような節回しで提示される。
7. My Childhood
詩の朗読とアンビエントサウンドが交差する、記憶の再現実化。
個人的な幼少期の情景が断片的に語られつつ、それが普遍的な感情へと変換されていく。
8. I Dreamed of You, Maria
アルバム終盤に現れる、穏やかで情緒的なラブソング。
夢と現実の境界を曖昧にするような構成と、深いエコー処理が特徴。
9. I Am Not There Anymore
タイトル曲としては最終曲ではないが、アルバムのコンセプトを象徴する瞑想的なトラック。
その言葉通り、過去の場所/人間関係/自己に別れを告げるような、柔らかくもしんとした達観がある。
10. The Village Is Always on Fire
最終曲。
“村がいつも燃えている”という象徴的なタイトルは、過去の記憶が常に揺らめき続けていることを暗示する。
終わりにして始まりのような、静かで壮麗なクロージング。
総評
『I Am Not There Anymore』は、The Clienteleが長年にわたり積み上げてきた「時間と記憶の音楽」を、ついにアルバム全体の構造そのものにまで浸透させた作品である。
これは単なる楽曲の集合体ではなく、ひとつの小説、あるいは長編詩に近い。
それは、線形の時間軸ではなく、回想、ループ、断片、遡行といった構造を持ち、音楽そのものが“過去を探索する旅”になっている。
ポップスとしてはきわめて野心的でありながら、感情の震えはむしろ以前よりも強く、
リリックには「亡き人との再会」「見えないものに名前を与える」「過ぎ去った自分をもう一度抱きしめる」といった主題が、
決して押しつけがましくなく、音の余白の中にそっと滲んでいる。
まさに、“私はもうそこにはいない”というタイトルは、The Clienteleというバンドが、
かつての自分たちさえ超えて、“記憶の音楽家”として次の地平へと到達したことを静かに告げているのだ。
おすすめアルバム
- Virginia Astley / From Gardens Where We Feel Secure
環境音とピアノによる記憶と自然の交差点。『I Am Not There Anymore』と共振。 - David Sylvian / Secrets of the Beehive
内省的な語りと緻密なアレンジ。詩的密度と音の親密さが共通。 - Steve Reich / Different Trains
時間と記憶をテーマにしたポストミニマル音楽。構造的試みとして共鳴。 - Mark Hollis / Mark Hollis
静謐と抽象、音の呼吸で語るような音楽。The Clienteleの現在形に近い精神性。 - Broadcast / Berberian Sound Studio (OST)
記憶と映像、語りとノイズの断片が混ざり合う幻想的作品。
ビジュアルとアートワーク
『I Am Not There Anymore』のジャケットは、抽象的でぼんやりとした肖像画のようなデザイン。
それはまさに、アルバムのテーマである「存在の不在」「過去の自分の影」と響き合い、
鑑賞者に対して“あなたもそこにいたのかもしれない”という錯覚を与えるように設計されている。
アートワークと音楽、リリックが完全に一体化した本作は、
The Clienteleが長年にわたって構築してきた“音楽による文学”の集大成であり、
同時に、これからの音楽が目指すべき「ジャンルの外側で語る力」を体現した傑作である。



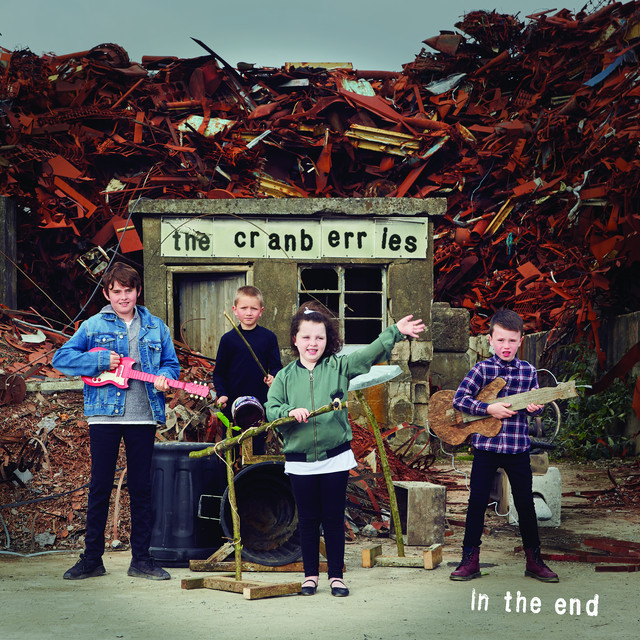
コメント