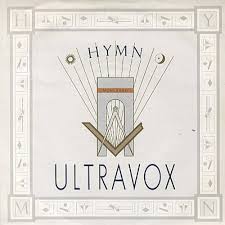
1. 歌詞の概要
Ultravoxの「Hymn(賛歌)」は、1982年にリリースされたアルバム『Quartet』からの第2弾シングルであり、その名の通り“現代の賛美歌”とも言える重厚かつ荘厳なトラックである。「Hymn」というタイトルが示すように、この楽曲は単なるポップソングにとどまらず、権力・信仰・自己欺瞞・堕落と救済といった大きなテーマを内包しており、Ultravoxの中でも最も哲学的な作品のひとつとされている。
歌詞の核には、「神に代わって力を得ようとする人間の欲望」と「その結果としての堕落」が描かれている。特に、「All that we can do is learn to pray(私たちにできることは、祈ることを学ぶことだけ)」というリフレインは、無力感の中でも最後に残される“祈り”という行為を象徴しており、人間の弱さと希望を同時に表現している。
宗教的な言葉や比喩が多く用いられているものの、それは必ずしもキリスト教信仰を讃えるものではなく、むしろ現代社会における権力構造や資本主義、道徳の退廃を鋭く風刺する視点が根底にある。荘厳なシンセサウンドと力強いコーラスがそのメッセージを一層際立たせており、聴く者に“何を信じ、何を見失ったのか”を静かに問いかける。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Hymn」はUltravoxが名プロデューサー、ジョージ・マーティン(The Beatlesのプロデューサー)と初めてタッグを組んだアルバム『Quartet』に収録された楽曲であり、その音作りにはクラシック音楽的な重厚さとシンセ・ポップの洗練が高い次元で融合している。リリース当時のUKチャートではシングルとして最高11位を記録し、Ultravoxの音楽的野心が最も広い層に届いた楽曲のひとつとなった。
ミッジ・ユーロ(Midge Ure)はこの曲について、「80年代の消費社会や資本主義の過剰さ、権力に対する皮肉がテーマだった」と語っており、特に“信仰”という言葉が本来持つ神聖さが、金や成功、地位といった俗的なものに置き換えられてしまっているという問題意識が根底にある。
楽曲の構成は典型的なポップ・ソングの枠を超え、宗教音楽を思わせるようなコーラス、力強くも内省的なボーカル、荘厳なコード進行とストリングス風のシンセサイザーで構成されている。そのすべてが「現代における“祈り”のかたちとは何か」を音で問いかけるような設計になっており、Ultravoxが単なるヒットメイカーにとどまらない“芸術性”を有していることを証明する作品となった。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、「Hymn」の印象的なフレーズを抜粋し、日本語訳とともに紹介する。
Give us this day
今日という日を我らに与えたまえ
All that you showed me
あなたが私に見せてくれたすべてを
The power and the glory
力と栄光を
‘Til my kingdom comes
私の王国が来るその日までAll I’ve wanted
私が望んできたすべては
Is the freedom to live
自由に生きることだけだった
Give me peace of mind
心の平安を与えてほしいAll that we can do is learn to pray
私たちにできるのは、祈ることを学ぶことだけ
出典:Genius – Ultravox “Hymn”
4. 歌詞の考察
「Hymn」の歌詞は、“祈り”という言葉を中心に展開されながらも、実際にはそれが個人的な信仰や心の救済に結びつくとは限らないという皮肉を内包している。特に、「力と栄光を(The power and the glory)」という一節は、キリスト教の祈祷文の一部を想起させるが、それを“自分の王国”の到来まで維持しようとする語り手の態度には、明らかな傲慢さや欲望が見え隠れしている。
つまり、この曲は宗教的モチーフを借りながら、現代における“新しい信仰”——金、成功、権力——の危うさを描いた作品である。語り手は自由と平安を望みながらも、そのために“手段を選ばず”、結果として真の自由や救済から遠ざかってしまう。そうした矛盾こそが、Ultravoxがこの曲を「Hymn(賛歌)」と名付けた皮肉的な意図なのだ。
また、「All that we can do is learn to pray」という繰り返しは、無力さの象徴であると同時に、祈りこそが人間に残された最後の自由であるという希望の光も宿している。すべてを手にしても、結局人は“心の平安”を求める存在である——この曲はその普遍的な真実に、ニュー・ウェイヴという冷たい音像を通じて迫っている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- New Gold Dream (81–82–83–84) by Simple Minds
信仰、未来、栄光をテーマにした壮麗なニュー・ウェイヴ・アンセム。 - The Lebanon by The Human League
宗教と政治、戦争の皮肉をポップに描いたシリアスなシンセ・ポップ。 - Enjoy the Silence by Depeche Mode
沈黙と祈りの対比、内面世界を追求する哲学的シンセ・バラード。 - Moments in Love by The Art of Noise
語らない祈りのような、インストゥルメンタルのエレクトロニック叙情詩。 -
Being Boiled by The Human League(初期)
機械文明と宗教の交差点をシンプルかつ鋭く描いたニュー・ウェイヴ初期の傑作。
6. シンセサイザーで鳴らされる現代の“賛歌”
Ultravoxの「Hymn」は、単なる宗教的イメージを装ったポップソングではない。それは、1980年代という消費と権力の象徴的な時代において、“何を信じるか”という普遍的な問いを投げかけた**現代の寓話(モダン・パラブル)**である。
人々は自由を求め、成功を手に入れ、平安を願う。しかしそのプロセスにおいて、本当に大切なものを見失っていないか? Ultravoxはその問いを、荘厳で壮麗なサウンドの中に埋め込み、聴く者の心に訴えかける。
その美しくも皮肉な構造は、まさに「祈り」という行為の本質を照らし出している。すなわち、人は何を前にひざまずくのか、何のために手を合わせるのか。そしてそれは、現代においてこそ改めて問われるべきテーマなのだ。
「Hymn」は、信仰と欲望、救済と虚構のあいだを揺れ動く我々の姿を映す鏡であり、Ultravoxというバンドが音楽を通して世界に問い続けた“存在の意味”そのものである。シンセサイザーで鳴らされるこの“賛歌”は、機械の冷たさを超えて、どこまでも人間的な響きを放ち続けている。




コメント