
発売日: 1976年10月
ジャンル: クラウトロック、レゲエ、ファンク、エクスペリメンタル・ロック
概要
『Flow Motion』は、ドイツの実験的ロックバンドCanが1976年にリリースした8作目のスタジオ・アルバムであり、クラウトロックという文脈から一歩踏み出し、**レゲエやエスニック・ファンクといった多様なジャンルを大胆に取り入れた“越境的作品”**として位置づけられる。
前作『Landed』ではポップ性と実験性のバランスを模索していたCanだが、本作では**より明快に“ダンス”や“身体性”**へと傾倒。
その象徴となるのが、英国でシングル・ヒットとなった「I Want More」であり、バンドとしては異例のTV出演も果たし、商業的な注目を集めた。
とはいえ、Canがレゲエをそのまま模倣するわけではない。
彼らの手にかかると、リズムは解体され、音響的に加工され、独自の空間感覚を持って再構築される。
“レゲエ風”であって、決して本来のレゲエではない——そこにこそCanの“翻訳的な実験精神”が息づいている。
また、本作はヤキ・リーベツァイトのドラムがより柔軟に“溶けていく”ような動きを見せ、ミニマル・グルーヴの真骨頂とも言えるサウンドを形成している。
録音は例によってケルンのInner Spaceスタジオで行われ、メンバー全員がプロデュースに関与した。
全曲レビュー
1. I Want More
シンセ・ポップ風のメロディとレゲエビートが融合した、Can史上最もキャッチーな楽曲。
ホルガー・シューカイとイルミン・シュミットの声がユニゾンし、「And I want more and more and more…」という繰り返しが中毒的な印象を残す。
音響的には非常に洗練されており、商業的成功を意識しながらも、実験性を損なっていない。
2. Cascade Waltz
3拍子のワルツに民族音楽風のギターが乗るという奇妙な構成。
Canにしては珍しく“楽しげ”なトーンを持つが、その裏には不安定なリズム構造と音色の断絶があり、聴けば聴くほど“ズレ”が気になってくる。
表層の軽快さと奥行きのある奇妙さが共存している。
3. Laugh Till You Cry, Live Till You Die
カリブ音楽を思わせるパーカッションに乗せて、サイケデリックなシンセと即興的なボーカルが交差。
無国籍的でありながら、身体が自然と動いてしまうような“トランスの種子”を内包している。
ダンス・ミュージックとしても成立しながら、Can特有の歪みが要所に挟まれている。
4. …And More
1曲目のリプライズであり、Canにしては珍しい“ポップの構造美”が感じられる。
同一のモチーフが変奏されることで、“I Want More”の反復性をさらに強調し、アルバム全体に円環的な感触を与える。
5. Babylonian Pearl
スロウテンポで幻想的なギターとオルガンが交錯する、美しいサイケ・バラード。
言葉の意味が曖昧なまま、音の余白に身を委ねるような聴き心地。
Canにおける“静寂の力”が静かに炸裂する一曲。
6. Smoke (E.F.S. No. 59)
“Ethnological Forgery Series”と題された即興的民族音楽模倣シリーズの一つ。
タイトル通り、もやのかかったような演奏で、音のエッジがすべて丸められている。
この“虚構の民族音楽”というアプローチは、後のワールド・ミュージックやエレクトロ・アコースティックにも影響を与えている。
7. Flow Motion
アルバムのラストを飾る10分超の大作。
Reggae、アンビエント、ミニマルの要素が流れるように融合しており、まさに“音の流動体=Flow Motion”。
ダビーなエフェクト処理と即興演奏が溶け合い、意識の深層にまで沈んでいくような没入体験を与える。
終わりが始まりでもあるような、不思議な余韻を残す名曲。
総評
『Flow Motion』は、Canが“ポップの語彙”と“実験の精神”を高度に融合させた、ジャンル横断的かつ空間志向的な作品である。
このアルバムにおいて、彼らは従来のクラウトロック文脈を離れ、より“リスナーの身体”に寄り添う音作りへとシフトしている。
しかしそれは、決して“迎合”ではなく、“翻訳”である。
レゲエのように聴こえても、それはCanにとっての“レゲエの再構築”であり、既存のスタイルをCan語に書き換える試みである。
また、バンドとしては初めてチャート・ヒットを経験しながらも、楽曲構造、編集手法、録音技術のすべてにおいて独自性を失っておらず、“音の中で踊ること”と“音そのものを観察すること”が共存した稀有なアルバムとなっている。
この作品によってCanは、ダンス・カルチャーと実験音楽の架け橋となり、その後のエレクトロニカ、ポストパンク、テクノなどの潮流に潜在的な影響を与えることになるのだ。
おすすめアルバム(5枚)
- Can – Saw Delight (1977)
本作の流れを受け継ぎ、さらにアフリカ音楽やジャズの要素を導入した次作。 - Brian Eno & David Byrne – My Life in the Bush of Ghosts (1981)
フィールド録音とグルーヴの融合。Canの民族音楽的アプローチと親和性が高い。 - Talking Heads – Speaking in Tongues (1983)
ファンクとポップ、アフロビートの融合という意味で、『Flow Motion』の影響を感じる作品。 - Massive Attack – Blue Lines (1991)
ダブ、ソウル、エレクトロニカを融合。Canのリズム実験に通じる音の設計が光る。 - Burnt Friedman & Jaki Liebezeit – Secret Rhythms (2002)
Canのドラマー、ヤキ・リーベツァイトによる後年のプロジェクト。ミニマルと民族音楽の現在進行形。
制作の裏側(Behind the Scenes)
『Flow Motion』制作時、Canは音楽的にも物理的にも“開かれた空間”を意識していた。
録音は例によってInner Spaceスタジオで行われたが、この頃にはスタジオ設備も進化し、**ミックス段階での空間処理(リバーブ、ディレイ、パンニング)**に重点が置かれるようになった。
とりわけ「Flow Motion」では、ライブでのジャム・セッションを複数テイク録音し、その中から“流れのある断片”を編集で繋げるという、まさにタイトル通りの手法が取られていた。
また、「I Want More」のプロモーションにおいては、CanがBBCの音楽番組『Top of the Pops』に出演するという異例の出来事も話題となった。
そこでは、彼らが“アングラ”であることを一切隠さず、むしろそれを“面白がられる”状況に変えてしまったことも、1970年代の実験音楽シーンにおける転換点である。
つまり、『Flow Motion』は、“地下から地上への流入”を音で表現した記録であり、Canというバンドがいかにして異物としてポップカルチャーに侵入したかを示す鮮烈なドキュメントなのだ。



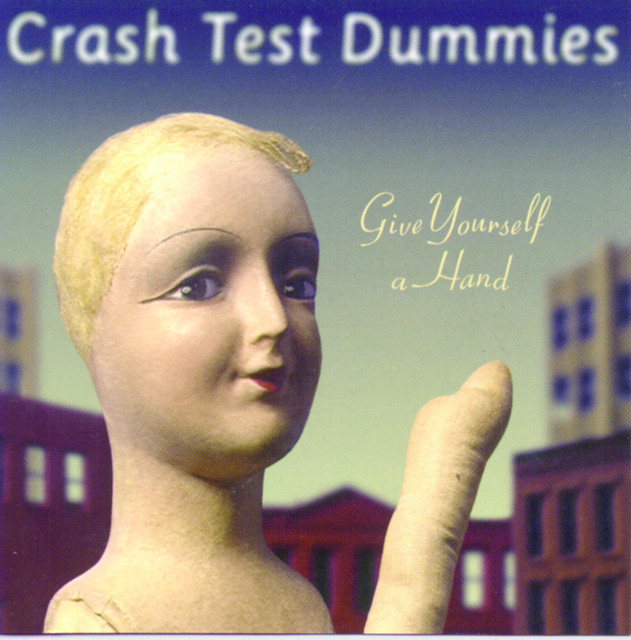
コメント