
発売日: 1996年
ジャンル: オルタナティブ・ロック、ドリームポップ、ブリットポップ、アートロック
概要
『Everything’s Mad』は、Modern Englishが1996年に発表した6作目のスタジオ・アルバムであり、
再々結成後に生まれた“混沌と再出発”をテーマにした、静かなる異端作である。
『Pillow Lips』(1990年)を最後に再び活動を停止していたModern Englishだったが、
90年代中盤に入り、リチャード・ブラウン(G)を中心とした新ラインナップで制作されたのが本作。
タイトルの “Everything’s Mad(すべてが狂っている)” が示す通り、
過去の美しいドリームポップ路線とは異なり、よりシニカルで、脱構築的で、そして音楽的にも方向性の多様化が顕著なアルバムである。
サウンドは、90年代的なブリットポップ、ローファイ、オルタナティブ・ロックの影響を受けており、
一方でHugh Jones(『After the Snow』の名プロデューサー)のプロダクションによって、
初期Modern Englishの残響的美学がかすかに息づいている点が魅力的。
一貫性に欠けるという批判もあるが、それはむしろ、再構築を試みるバンドの“迷いの痕跡”を忠実に映した誠実な作品として捉えるべきだろう。
全曲レビュー
1. Everything’s Mad
表題曲にしてアルバムのテーマを象徴するオープニング・トラック。
歪んだギターと不安定なリズムが、90年代オルタナ的混乱感と無力感をそのまま音像化している。
“狂ってるのは世界か、それとも僕か”という問いが繰り返され、ポップというよりポストグランジに近い質感。
初期Modern Englishの美しさからは遠いが、その不穏さが逆に新鮮。
2. Here Comes the Failure
前作『Pillow Lips』にも同名曲があったが、本作ではより皮肉めいたテンションとダウナーなリズムで再構成。
歌詞に漂うのは敗北と受容、あるいは愛と人生における疲労感であり、
あえてエッジを丸めたギターと低く沈むベースが、重力のあるサウンドを生んでいる。
3. I Don’t Know Anything
イントロから鳴るルーズなギターと気だるいヴォーカルは、BlurやRadiohead初期にも通じるブリットポップ文脈。
“何も知らない”という反語的なメッセージは、情報過多の90年代における脱知性主義と内的崩壊の象徴とも読める。
言葉よりも“音の引き算”で語る曲。
4. It’s OK
アルバム中でもっともストレートなポップナンバー。
タイトル通り“まあ、大丈夫”という投げやりとも救済ともとれる言葉がリフレインされるが、
その裏にあるのは明らかに疲労、諦観、または希望の残骸。
サビの明るさと、歌詞の静かな寂しさの対比が切ない。
5. New Beginning
ギターリフが希望を予感させる構成で、再生やリスタートを暗示する明るめの楽曲。
だがその“新しさ”は不確かで、歌詞には繰り返す不安や失敗の予感が絶えず現れる。
その二面性こそが、本作全体の感情の中心といえる。
6. Dance
意外にもグルーヴィでビート重視のトラック。
そのタイトルにもかかわらず、**喜びではなく空虚さからの逃避としての“踊り”**がテーマに思える。
ギターとベースの絡みはクセになるが、どこか「心ここにあらず」の演奏が妙にリアル。
7. The Order
アルバム終盤に位置するこの曲は、再びシリアスな空気へと回帰する。
タイトルの“秩序”とは何か? 社会か、自己か、関係性か。
その問いをサウンドと歌詞で輪郭のないままに提示し、聴き手に余白を残す構成となっている。
曲の終わりもフェードアウト的に宙づりで、答えは出さないという姿勢が印象的。
8. Dreamtime
本作で唯一、初期Modern Englishのドリーミーな質感を想起させる楽曲。
ディレイがかったギターと柔らかなシンセパッドが、『After the Snow』を遠くから眺めるような郷愁を感じさせる。
“夢の時間”は過去か未来か、それとも現実逃避か──
短くも美しい、アルバムの中の小さな光。
総評
『Everything’s Mad』は、Modern Englishが**90年代の混沌のなかで、自らのアイデンティティと音楽的ルーツを見つめ直した“問いかけのアルバム”**である。
それは決して明快ではないし、統一感にも欠ける。
だがそこにこそ、ポストポップ時代のアーティストのリアルな苦悩と、生き延びようとする試行錯誤の痕跡が刻まれている。
“すべてが狂っている”──その言葉は叫びではなく、
静かな共鳴としてリスナーの耳に届く。
おすすめアルバム(5枚)
-
Blur – Modern Life Is Rubbish (1993)
ブリットポップと退屈な現代生活の詩的融合。シニカルさが共鳴。 -
The Boo Radleys – Giant Steps (1993)
ジャンルの混合と音楽的多様性という意味での兄弟作。 -
Radiohead – Pablo Honey (1993)
まだ迷いを抱えていた初期Radioheadと『Everything’s Mad』の空気感は近い。 -
Suede – Dog Man Star (1994)
耽美的でありながらも不穏な情緒を漂わせる、90年代UKロックの極北。 -
The House of Love – Babe Rainbow (1992)
繊細なギター・ポップと心象風景の描写。Modern Englishの陰影と交差。


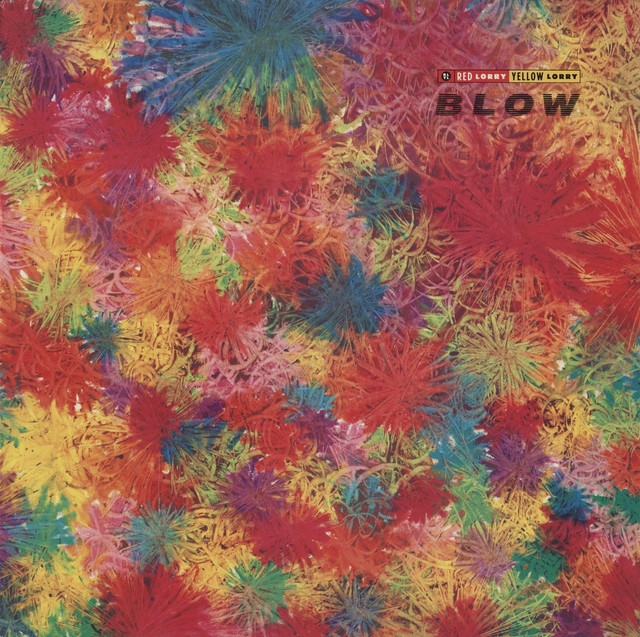

コメント