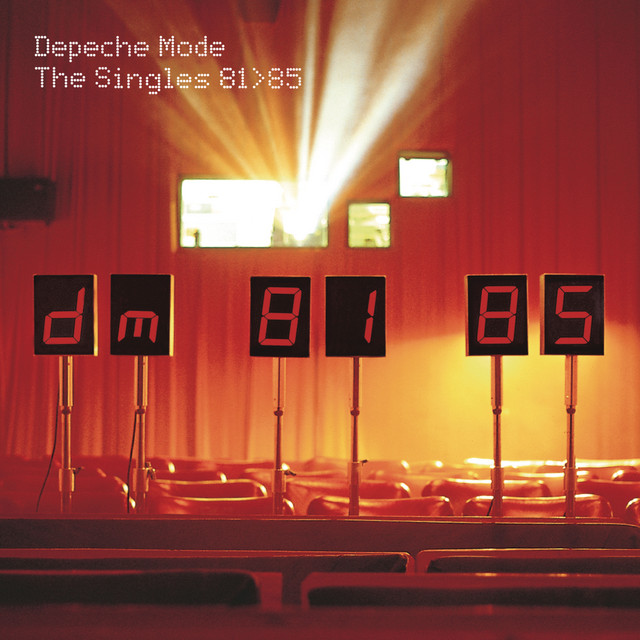
1. 歌詞の概要
「Everything Counts」は、Depeche Modeが1983年に発表したアルバム『Construction Time Again』からのシングルであり、バンドの音楽的進化を決定づけた作品のひとつである。歌詞のテーマは商業主義と資本主義社会への批判であり、当時まだ20代前半だったDepeche Modeが、ポップ・ソングの形式を借りながら鋭い社会的メッセージを提示したことは大きな衝撃だった。
「Everything counts in large amounts(すべてが大量に数えられる)」というリフレインは、経済活動や企業の貪欲さを皮肉ると同時に、人間の欲望の尽きなさをシンプルに言い当てる。単なるラブソングや青春の歌ではなく、社会批評的な視点を持つことによって、Depeche Modeはシンセポップの枠を超えて新しい領域に踏み込んだのである。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Everything Counts」がリリースされた1983年、Depeche Modeは新しい音楽的・思想的方向性を模索していた。ヴィンス・クラーク脱退後、マーティン・ゴアが主要ソングライターとしてバンドを牽引し、『A Broken Frame』(1982)ではまだ手探りの段階だったが、この『Construction Time Again』で大きく飛躍を遂げた。
特に重要なのは、アラン・ワイルダーの存在である。彼は1982年に正式加入し、クラシックの素養と実験的な感覚を持ち込み、サンプリングや工業的なサウンドを導入した。鉄を打つ音や機械の衝撃音などが曲に織り込まれ、まさに産業社会のメタファーとして機能している。これによって「Everything Counts」は、ただのシンセポップではなく、インダストリアル的な質感を持つ先進的な楽曲へと昇華された。
歌詞のテーマも、当時のイギリス社会の空気を強く反映している。サッチャー政権下のイギリスは市場原理主義と産業構造の変化に揺れており、失業率の上昇や社会格差の拡大が問題となっていた。そうした背景の中で「Everything Counts」は、権力者や企業が利益を追求する姿を冷ややかに描写し、それをキャッチーなポップ・ソングに仕立て上げたのである。
この曲はシングルとしてリリースされ、UKチャート6位を記録。ライヴでも定番曲となり、以後のDepeche Modeが社会批評や人間存在のテーマを扱う上での基盤を築いた作品となった。
3. 歌詞の抜粋と和訳
(歌詞引用元:Depeche Mode – Everything Counts Lyrics | Genius)
The handshake seals the contract
握手は契約を成立させる
From the contract, there’s no turning back
契約からはもう逃れられない
The turning point of a career
キャリアの転機となる瞬間
In Korea, being insincere
韓国での不誠実な取引
The grabbing hands grab all they can
欲深い手は掴めるだけ掴み取る
All for themselves, after all
結局はすべて自分たちのため
It’s a competitive world
それが競争社会というもの
Everything counts in large amounts
すべてが大量に数えられる
これらの歌詞は、冷徹なビジネスの世界や資本主義の本質を短いフレーズで鋭く描き出している。「grabbing hands(掴み取る手)」という比喩は、欲望に突き動かされる人間や企業の姿を直感的に表現している。
4. 歌詞の考察
「Everything Counts」は、初期Depeche Modeに見られた恋愛中心のポップ・ソングからの脱却を象徴している。その核心にあるのは、資本主義社会の倫理観に対する疑念だ。握手が「契約」を意味し、その契約が「後戻りできないもの」とされる描写には、ビジネスの世界に潜む冷酷さが刻まれている。
特に印象的なのは「Everything counts in large amounts」というフレーズである。これは、数字が支配する社会において、人間の価値までもが数量化され、利益の大きさだけが評価される現実を皮肉っている。数字に換算できないもの——人間の感情や倫理——は切り捨てられ、結果として「grabbing hands」が世界を覆っていくのだ。
同時に、この曲は単純な社会批判にとどまらず、ポップ・ミュージックの機能そのものを再定義した。キャッチーで踊れるメロディの中に、鋭い風刺を忍ばせることで、リスナーは無意識に社会問題を反芻することになる。まさに「楽しさ」と「批判精神」の二重性がDepeche Modeの魅力であり、後に『Violator』や『Songs of Faith and Devotion』といった作品で深化していくそのスタイルの原点がここにある。
さらに、サウンドの面でも考察できる。工場の騒音のようなサンプリングが使われることで、歌詞のテーマと音が直接結びついている。これは音楽が「社会の写し鏡」となり得ることを示す好例であり、当時のシンセポップの中でも群を抜いて先鋭的であった。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- People Are People by Depeche Mode
「Everything Counts」と同じく社会批評的なテーマを扱い、人種差別や偏見を批判する代表曲。 - Master and Servant by Depeche Mode
支配と従属の構造を風刺的に描いた曲。シンセの鋭さと歌詞の挑発性が共鳴する。 - Love Action (I Believe in Love) by The Human League
シンセポップに社会性を織り交ぜた作品で、同時代的な文脈で聴くと興味深い。 - She’s in Parties by Bauhaus
ポストパンクの文脈で、資本主義と表層的な文化を批評的に扱った楽曲。 - True Faith by New Order
快楽的なメロディの裏に自己批評的な言葉が潜むという点で共通している。
6. 社会的メッセージとDepeche Modeの進化
「Everything Counts」は、Depeche Modeが単なるシンセポップ・バンドから「時代を映す批評的アーティスト」へと変貌する契機となった。キャッチーなメロディと鋭い社会風刺が共存することで、バンドの音楽は娯楽以上の意味を持つようになったのである。
この曲のライヴにおける重要性も特筆すべきだ。以降のツアーでは観客の大合唱を誘う定番曲となり、バンドとファンの間の「儀式」のような瞬間を生み出した。とりわけ「Everything counts in large amounts」というリフレインが群衆によって繰り返される光景は、楽曲自体のテーマ——個人の欲望が集まって巨大な力になる——を逆説的に体現していた。
結果として、この曲は単なる1980年代シンセポップの一里塚にとどまらず、現代に至るまで社会批評的なポップ・ソングの典型として語り継がれているのである。


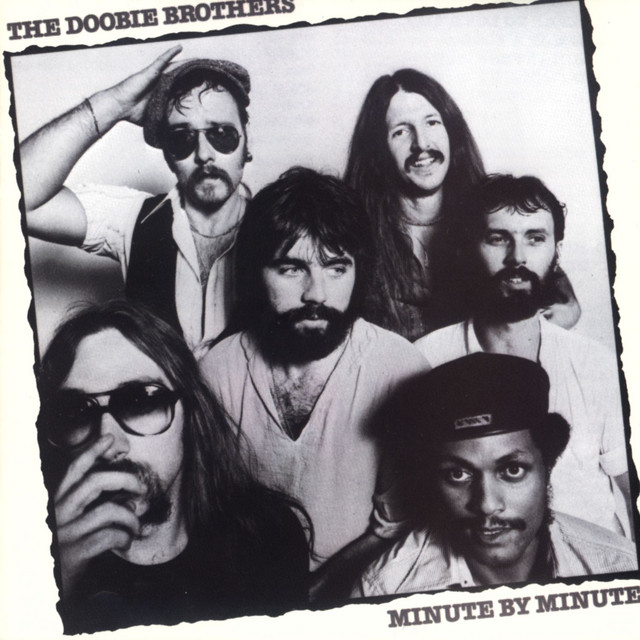
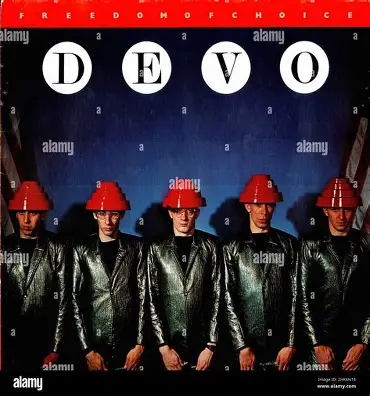
コメント