
イギリス・ブリストル発のグループ、Portisheadが1994年にリリースしたアルバム『Dummy』は、トリップホップというジャンルを世界的に認知させる一翼を担った作品として知られています。ヒップホップ由来のブレイクビーツ、ジャズ的なコード感、そしてシネマティックなサウンドスケープを持ち込みながらも、どこか「冷たさ」を孕んだ幻想的なムードが特徴的です。しかし、その「冷たさ」こそが、深い「感情」や静謐さを逆説的に浮き彫りにしているという視点もあります。今回は、90年代イギリスの音楽文化を研究してきたSophieと、エレクトロニカやシンセポップを専門とし、日本でDJ・音楽プロデューサーとして活動するNaomiの二人を招き、Portisheadの『Dummy』がもたらしたインパクト、そして「冷たさ」と「感情」の交差点について深掘りしていきたいと思います。
対談メンバー紹介
- Naomi(ナオミ)
- 42歳。スペイン・バルセロナ生まれ。音楽大学で電子音楽を専攻後、日本に移住。テクノ、アンビエント、シンセポップなどのイベントを主催しつつ、多様な音楽制作に携わる。民族音楽とエレクトロニカの融合にも興味を持ち、週末はフィールドレコーディングに出かけるなど、前衛的なアプローチにも精通。
- Sophie(ソフィー)
- 40歳。マンチェスター生まれ。90年代のブリットポップ隆盛期を肌で感じながら育ち、大学では音楽文化論を専攻。BBCラジオをはじめ、多くの音楽誌で評論を行う。ブリットポップやポップカルチャーの社会的影響、アートロックの歴史などにも詳しく、英国音楽シーンにおけるファッションと音楽の関係を研究している。
対談スタート
──ポーティスヘッドの『Dummy』は、トリップホップの金字塔のひとつと言われる作品ですが、お二人はこのアルバムに初めて触れたときの印象を覚えていますか?
Naomi:
「私が初めて『Dummy』を聴いたのは、スペインにまだ住んでいた頃でした。クラブミュージックを勉強していたんですが、いわゆるドラムンベースのようにアップテンポでもなく、ハウスとも違う。むしろジャズ的なメロウ感があるのに、裏に潜むビートはヒップホップ由来のブレイクビーツ。そこに、あのBeth Gibbonsの冷徹とも言えるボーカルが乗ってくる。その時、これまでにない“静寂のような空気感”を抱えつつ、強いグルーヴも感じられて、衝撃でした。」
Sophie:
「私の場合、当時イギリスの音楽シーンはブリットポップ全盛期で、オアシスやブラー、スウェードとか、ギターをかき鳴らすタイプの“英国らしさ”が注目されていた。そんな中で、ブリストルのトリップホップというのは、どこか“冷めた”雰囲気があると見られていました。最初に『Dummy』を聴いたときの印象は、ある種の孤独感が強調されたサウンドと、ダークでミステリアスな世界観。大衆的な明るさの真逆を突きつつ、なぜかとても魅力的でしたね。」
──ギター中心のブリットポップが猛威を振るっていた中で、Portisheadの『Dummy』は異質な存在でしたよね。その異質性が「トリップホップ」という言葉そのもののイメージを定着させたと思います。
Sophie:
「そうですね。当時、TrickyやMassive Attackと並んで“ブリストル・サウンド”と呼ばれ始めた頃でした。ギターサウンドではなく、サンプリングやエレクトロニックな手法を主軸にして、そこにジャズやソウルの要素を入れていた。ロンドン的なクラブシーンとも違うし、北のマンチェスターが発信していた“Madchester”ともまた違う。まさに“ブリストル特有の陰鬱さ”と“クールさ”が混ざった新たなサウンドとして認識されていました。」
Naomi:
「私が興味深いと思うのは、当時のヨーロッパの音楽マーケットにおいて、こういうダークでクールなサウンドが一種の“オシャレ”として受け入れられた点です。普通、ダークな音楽ってニッチなイメージがあったりするじゃないですか? でも『Dummy』はファッション誌とかライフスタイル誌なんかでも度々紹介されていて。その“スタイリッシュな世界観”が同時に“感情を抑圧した冷たい雰囲気”にもなっていたことが、すごくアイロニカルで面白いですよね。」
「冷たさ」と「感情」の両立
──今回のテーマにもあるように、“冷たさ”と“感情”が『Dummy』という作品の大きな特徴だと思います。具体的にはどんなところに感じられますか?
Naomi:
「私がいちばん象徴的だと感じるのは、やっぱりBeth Gibbonsのボーカルです。声質そのものは繊細で内省的ですよね。決して力強くシャウトするわけではない。でも、その背後にある痛みとか、どうしようもない切なさみたいなものがじわじわと伝わってくる。その一方で、楽器の使い方やトラックの構成はクールなサンプリングが中心で、“人間臭さ”は抑えられている。そこが“冷たさ”と“感情”の同居を象徴していると思います。」
Sophie:
「Bethのボーカルは、まるで独白のようですよね。メロディがあっても、独り言の延長線みたいに聴こえる。その“痛切なトーン”こそPortisheadのエッセンスなんだと思います。楽器の配置はかなりミニマルで、時折鳴るターンテーブルのスクラッチや、ローファイなビートが“静かな闇”を強調している。そこでリスナーは、ボーカルの奥にある感情の渦を想像するんです。」
Naomi:
「あと、“冷たさ”を感じるポイントとして、当時の録音技術やプロダクション手法が意図的にヴィンテージ感を出しているところも大きいと思います。彼らは古い録音機材やサンプリングを使って、モノクロ映画のサウンドトラックみたいな雰囲気を醸し出していました。結果として、リアルすぎる生々しさというよりは、ちょっとモノクロ写真を眺めているようなノスタルジックな冷たさが強調されているんじゃないでしょうか。」
“トリップホップ”というレッテル
──そもそも、Portisheadの音楽を「トリップホップ」と呼ぶことについて、賛否が分かれるところでもありますよね。どうお考えですか?
Sophie:
「マーケティングの面で“トリップホップ”という言葉が非常にわかりやすかったんでしょうね。ブリストルのアーティストたちが作り出したゆったりとしたビート、暗くメランコリックな雰囲気、どこか幻惑的な感覚……それらをひとつに括るのに都合が良かった。ただ、アーティスト本人たちはあまりその呼び方を好まなかったりもします。ジャンルってあとから付いてくるものが多いですし、それが固定化されると作り手の自由度が減るという面もあるから。」
Naomi:
「実際、Portishead自身は自分たちを“トリップホップ”だとはあまり意識していなかったんじゃないかなと思います。ヒップホップからの影響は認めつつも、“私たちの音楽はもっと映画的で、ある種のサントラ的要素が強い”という考えがあったはず。でも、結果的に『Dummy』によってトリップホップという言葉がクローズアップされ、ジャンルの枠組みが定着していったのも事実でしょうね。」
ブリットポップや他ジャンルとの比較
──当時のイギリスといえば、ブリットポップ真っ盛りの時代でした。Sophieさんとしては、ブリットポップとは全く違う世界観の音楽が同じ国内で生まれたことをどう捉えていますか?
Sophie:
「私はブリットポップの名のもとにギターをかき鳴らすバンドが主流になっていた一方で、“じゃあ他のアーティストたちは本当にギターサウンド一辺倒だったのか?”という疑問を持っていました。実際には、同時期にエレクトロやハウスなどのクラブシーンも盛り上がっていたし、ブリストルのように独特の実験性を持った土地もあった。ブリットポップ以外のイギリス音楽シーンを掘り下げていくと、こうしたトリップホップが誕生したのも必然だったと感じます。つまり、当時のイギリスはギターだけが盛んだったわけじゃない。Portisheadのようなアプローチが出てくる土壌はあったと思います。」
Naomi:
「私としては、スペインから見てもイギリスの音楽シーンは刺激的な要素が多かったんです。ブリットポップは世界的なムーブメントになっていたし、同時にアンダーグラウンドではエレクトロニカやドラムンベース、そしてトリップホップが活発。いろいろな音楽が共存するからこそ、新しいジャンルが生まれる。そして、『Dummy』が世界的に評価されたことで、“イギリスにはこんな陰鬱な魅力を持つ音楽もあるんだ”と広く知らしめるきっかけになったんじゃないでしょうか。」
技術的アプローチと“アナログ感”
──Naomiさんはエレクトロニカやシンセポップを専門にされている立場から見て、『Dummy』のサウンドはどのように捉えていますか?
Naomi:
「一聴すると打ち込みが中心なのかな、と思うかもしれないですが、その実、すごくアナログ的な手触りがあるんですよね。ターンテーブルのスクラッチやローファイなビート、古いマイクを使ったようなボーカルの録音などが混ざり合っていて、温度感があるのか無いのか、はっきりしない不思議な質感を醸し出している。コンピュータでピカピカに整えたサウンドとは違う、ちょっとした“曖昧さ”が逆にリアルな“情感”を呼び起こすんだと思います。」
Sophie:
「確かに。テクノロジーの進化に伴って、サウンドはどんどんクリアになっていく傾向があるけど、Portisheadは意図的に“汚れ”を残している印象があります。しかも、その汚れが音楽的にとても魅力的に活かされている。そういう意味では、モダンなサウンドの“冷たさ”とはちょっと違う、ヴィンテージ感を伴った“冷たさ”と言いましょうか。時代を超越した雰囲気さえ漂っていますよね。」
Naomi:
「そうそう。そしてその“時代を超越した”感覚が、映画のフィルムっぽさにもつながっている。私はそこが“ノスタルジックな冷たさ”をより際立たせていると感じます。」
アルバムのメッセージ性
──では、『Dummy』はそのサウンドの裏側で、社会的・文化的にどんなメッセージを持っていたのでしょうか?
Sophie:
「イギリスが当時抱えていた社会状況も少なからず反映されていると思います。ブリットポップが国民的に盛り上がり、“クール・ブリタニア”なんて言葉がメディアで踊っていた一方で、地方都市や一部の地域では依然として不況や社会的な分断があった。そうした影の部分が『Dummy』に投影されているんじゃないかと感じますね。明るく派手なロックスターの裏で、人々の孤独や不安、そして切ない感情が潜んでいる――そこをダークなサウンドで描き出した作品だと思います。」
Naomi:
「音楽を通して直接的な政治的メッセージを発信しているわけではないけれど、ダウナーな雰囲気の中に“現実社会への倦怠感”みたいなものを感じることはありますよね。大きな声で訴えるんじゃなくて、内面に溜め込んだやるせなさを音楽で具現化するっていうスタイル。それが多くのリスナーに共感を呼んだ要因でもあると思います。」
後続アーティストへの影響
──『Dummy』はその後の音楽シーンにも大きな影響を与えました。特にどのような形で受け継がれたと考えますか?
Sophie:
「やはり女性ボーカルとエレクトロニックなサウンドの掛け合わせが、大きな道筋を作ったと思います。90年代後期にはLambやHooverphonic、Sneaker Pimpsなんかも出てきましたし、その後もゼロ年代以降に出てきたエレクトロ・ポップ系のアーティストにとって、“雰囲気を重視したダウンテンポのトラック”はひとつのテンプレートになったのではないでしょうか。」
Naomi:
「あと、ヒップホップ的なビートの使い方も、幅広いジャンルのアーティストに影響を与えたと思います。特にインディーロックやポストロックのシーンでも、ダウンテンポで重心の低いビートを取り入れるケースが増えましたよね。ある種、実験的な音楽を作る上で、トリップホップの手法が新たな可能性を示したんじゃないかと思います。」
現代の視点で再評価すると
──今改めて『Dummy』を聴くと、どんな発見がありますか?
Naomi:
「やっぱり生々しいエモーションが詰まっているな、という再認識ですね。最新のDAW環境ならもっと綺麗に音を整えられるはずなんですけど、そこをあえてローファイにしている。そのアナログ感が、デジタル時代の現代にも強く訴えかけてくるんです。むしろ今の方が、このアルバムの“曖昧な余白”にこそ温かみや人間味を感じるリスナーが多いんじゃないでしょうか。」
Sophie:
「今聴くと、ある意味で“クラシック”とも呼べる立ち位置に来ていると思います。90年代の特定の音楽ムーブメントとしてではなく、“いつ聴いても不思議な感覚に浸れる音楽”として時代を超越している。特に、Beth Gibbonsのボーカルは他に代えのきかない存在感がありますし、サウンドメイキングも実験的でありながら耳に残るメロディをしっかり持っている。これは長く愛される要素ですよね。」
インタビュアーのまとめ
──お二人の深い洞察を伺って、改めて『Dummy』がなぜここまで評価されているのか、その理由がよくわかりました。派手さやわかりやすいキャッチーさがあるわけではないのに、リスナーの心を揺さぶり続ける。この「冷たさ」と「感情」の絶妙なバランスこそが、Portisheadの唯一無二の魅力なのかもしれませんね。
それでは最後に、読者の皆さんにひと言ずつメッセージをいただけますか?
Naomi:
「今の時代だからこそ、いろんなプラットフォームで気軽に『Dummy』をチェックできるのが素晴らしいですよね。ヘッドホンでじっくり聴くと、小さなサンプル音やスクラッチ音がこんなにも“物語”を持っているんだと驚かされるはず。ぜひ夜の静かな時間や、ちょっと疲れているときにこのアルバムを流してみてほしいです。心の中にある小さな声がかき立てられるかもしれません。」
Sophie:
「私としては、イギリスの90年代シーンという文脈の中でこの作品を位置づけてみるのも面白いと思います。ブリットポップが好きな人も、また違う角度でイギリス音楽の懐の深さを感じられると思いますよ。一度『Dummy』の世界観に引きこまれると、ほかのトリップホップやダウンテンポ系の作品にも興味が湧いてくるんじゃないでしょうか。そこから先はもう、魅惑的な深い深い音楽の森へ誘われるはずです。」
ラップアップと読者への問いかけ
──今回の対談を通じて、“トリップホップ”というジャンルの曖昧さや、『Dummy』が象徴する「冷たさ」と「感情」の二面性が、いかにリスナーの心を捉え続けるかを再確認できました。ブリストルという土地が生んだ独創的なサウンド、そしてBeth Gibbonsのボーカルが放つ孤独と美しさ。その微妙なニュアンスは、時代を超えて多くのアーティストに影響を与えています。
読者の皆さんも、ぜひ改めて『Dummy』に耳を傾けてみてください。そして、今だからこそ発見できる新しい魅力や、感じるものがあったら、あなたなりの言葉でぜひ共有してみてはいかがでしょうか? 皆さんにとって、このアルバムが持つ“冷たさ”や“感情”の深淵はどんなふうに映るのか――その感想を、ぜひ聞かせてください。



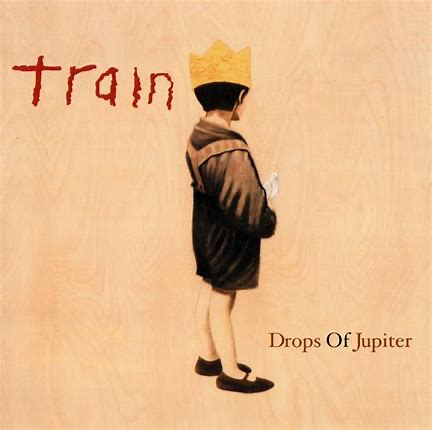
コメント