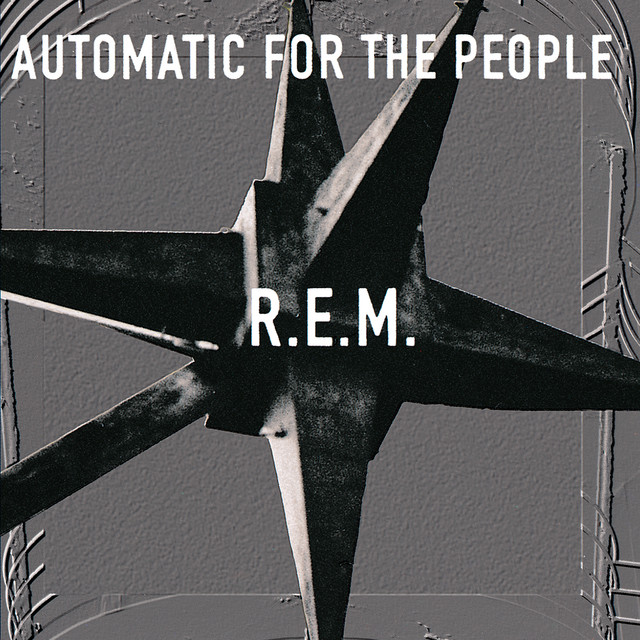
1. 歌詞の概要
「Drive」は、R.E.M.が1992年に発表したアルバム『Automatic for the People』の冒頭を飾る楽曲であり、同時に先行シングルとしてリリースされた、ミステリアスかつ詩的な魅力を湛えたロックバラードである。
「Drive」というタイトルは、直訳すれば「運転する」「駆動する」といった意味になるが、この曲においてはもっと抽象的で広い意味を持つ。“何かを駆り立てる力”“導く存在”“人を操るシステム”など、多義的に響くこの言葉を軸に、R.E.M.は現代の若者に向けた静かな挑発と呼びかけを行っている。
繰り返されるフレーズ “Hey, kids, rock and roll / Nobody tells you where to go” は、かつて反抗の象徴だったロックンロールが既に“誰かに導かれたもの”になってしまったことを暗示するようでもあり、時代と個人の自由に対する醒めたまなざしと、再び自らの意思で動き出すことへの促しが込められている。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Drive」は、R.E.M.が1980年代から築いてきたインディーロックの文脈を経て、より成熟した芸術性と社会意識を打ち出す新たなフェーズの始まりを象徴する楽曲である。
この曲は、アメリカの政治的状況やメディア支配、あるいは当時の若者文化──特に“MTV世代”が受動的に与えられる価値観への批判と、「君自身で選び、動け」という静かなアジテーションが込められている。マイケル・スタイプ自身も、この曲について「若者に向けた“権力から目を逸らすな”というメッセージ」と語っている。
また、この曲のタイトルには**映画『Two-Lane Blacktop(邦題:断絶)』**の影響があるともされており、無目的な“走行”と“人生の行方”が重ねられている。さらに、楽曲構造にはニール・ヤングやデヴィッド・ボウイからの影響も見られ、R.E.M.が“アメリカーナ”という深層の風景を掘り下げるアルバムの導入として、非常に象徴的な役割を果たしている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下は象徴的なフレーズの一部(引用元:Genius Lyrics):
Hey, kids, rock and roll / Nobody tells you where to go
ねぇ、子どもたちよ、ロックンロールをやろう
誰も君にどこへ行けなんて言わない
Baby, baby, baby, crank the music up / Whoo!
ベイビー、音楽をもっと大きくして
Smack, crack, Bush whacked / Eyes black, t-shirt hitchhiked
ドラッグ、暴力、ブッシュの一撃
黒ずんだ目 Tシャツでヒッチハイク
We’re talking to you / Hey, kids, where are you?
これは君たちに言ってるんだよ
おい、子どもたちよ、どこにいるんだ?
こうした断片的な言葉の羅列は、まるでメディアの雑音や社会の喧騒をコラージュしたようであり、明確な意味を避けることで逆に“自分で考えること”を促す構造になっている。
「Drive」という単語そのものが、“自分自身を運転する力”を象徴しており、この曲は“受動”から“能動”への移行を象徴的に描いているともいえる。
4. 歌詞の考察
「Drive」は、R.E.M.がその成熟したフェーズで提示した、最も内省的かつ政治的な表現のひとつである。激しい主張や怒りの爆発ではなく、静かな音の中に込められた問いかけ。それがこの楽曲の最大の特徴である。
ここで描かれているのは、ただのロックンロール礼賛でもなければ、単純な反体制のアジテーションでもない。むしろ、“すでに無力化されたロック”に向けた問いであり、かつて自由を象徴した音楽が、いまや誰かに管理され、方向づけられてしまっているという皮肉な構図への警鐘でもある。
スタイプはあえて明確な答えを提示せず、誰かを責めることもない。代わりに、リスナー自身に「君はどこにいる?」「誰のために、何のために動いている?」と問いかけるのだ。
このように、「Drive」は、沈黙の中に鋭さが光る、音楽による哲学的なコミュニケーションであり、R.E.M.というバンドが単なるポップバンドではなく、文化と社会に対して対話を挑み続けたアーティストであることを証明する1曲である。
(歌詞引用元:Genius Lyrics)
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- The Needle and the Damage Done by Neil Young
社会的メッセージを内省的に語りかける、静かな反抗の歌。 - Heroes by David Bowie
自己の尊厳と自由を掲げるアンセムでありながら、どこか仄暗い光を湛えた名曲。 - Street Spirit (Fade Out) by Radiohead
冷たさと優しさ、絶望と希望が交錯する、ポスト90年代的バラード。 - Strange Currencies by R.E.M.
同じく『Monster』期のメランコリックなラブソングで、音楽的余白が共通する。 - Hurt by Nine Inch Nails(あるいはJohnny Cashバージョン)
自己破壊と内面の葛藤を極限まで掘り下げた、極めてパーソナルな楽曲。
6. “誰が君を動かしている?”:静かなる革命としての『Drive』
「Drive」は、時代の喧騒に飲まれそうになる中で、“本当に自分の意志で動いているか?”という根源的な問いを静かに突きつける。
それは政治的なプロテストではなく、音楽という形を借りた哲学的な一撃なのだ。
マイケル・スタイプがこの曲を「若者に向けたメッセージ」としたように、この曲は今も変わらず、無数の“受け身でいることに慣れてしまった私たち”の背中を押してくれる。それは叫びではなく、囁きのような声で。
“Drive”とは、誰かに操縦されることではなく、自ら舵を握るという選択。
その小さな意志の火が、この静かな曲の中で、今も確かに燃えている。


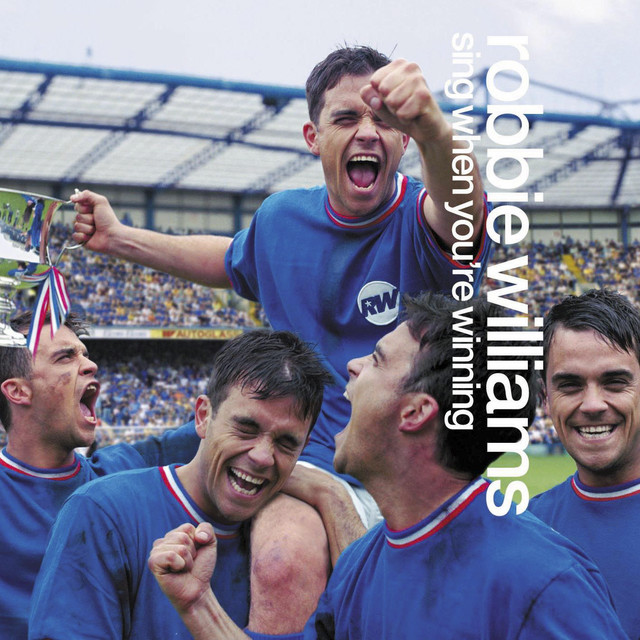
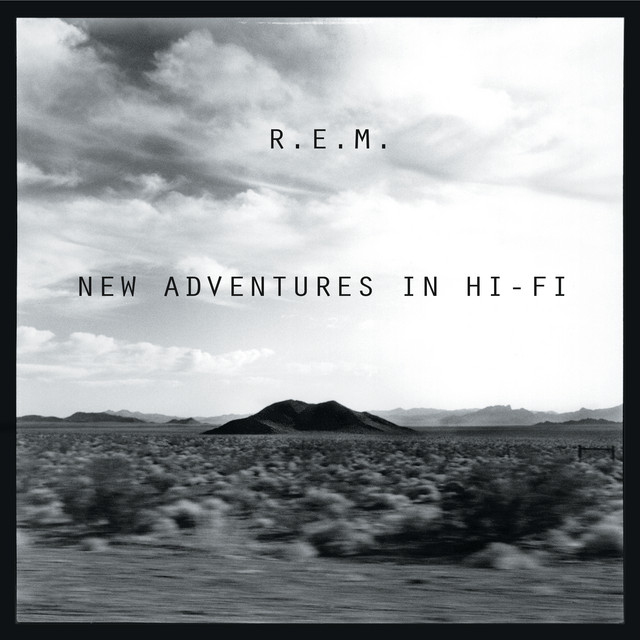
コメント