
1. 歌詞の概要
「Crushed by the Wheels of Industry」は、Heaven 17が1983年にリリースした2ndアルバム『The Luxury Gap』の収録曲であり、同年シングルとしても発表された楽曲である。日本ではそれほど知られていないかもしれないが、本国イギリスではUKシングルチャート17位を記録し、シンセポップと政治的メッセージの融合という点で、当時の音楽シーンの中でも際立った存在感を放っていた。
この曲の主題は明確だ――産業社会の圧力に押しつぶされる個人、それがタイトルにもある「Crushed by the Wheels of Industry(産業の歯車に押し潰されて)」というメタファーで強く示されている。
華やかに思える経済や労働システムの裏で、多くの人々が“消耗品”として扱われる現実。Heaven 17はこの曲を通して、80年代の労働者階級、資本主義の矛盾、そして労働とアイデンティティの危うい関係を痛烈に描いている。
とはいえ、その語り口は決して陰鬱でも絶望的でもない。むしろシンセファンク調のエネルギッシュなグルーヴに乗せて、ポップに、ダンサブルに“告発”するというスタイルが貫かれており、それが彼らの魅力の核でもある。
2. 歌詞のバックグラウンド
1980年代初頭のイギリスは、マーガレット・サッチャー政権下での新自由主義政策により、急激な経済改革が進められた時代である。製造業が縮小され、伝統的な労働者階級のコミュニティが解体される一方で、金融業など都市型ホワイトカラーが栄え、「勝ち組」と「負け組」の格差が急激に広がっていた。
Heaven 17は、そうした社会の変化に対して鋭い視線を持っていたバンドであり、「(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang」や「Let Me Go」といった楽曲同様、本作でもポップミュージックを使って社会構造を批評するという姿勢を貫いている。
「Crushed by the Wheels of Industry」は、労働そのものの意義が失われ、「働くこと=生きること」と言い切れなくなった時代の空気を反映しており、それをエレクトロファンクという軽快な形式に落とし込んでいる点で、音楽的にも政治的にも非常に挑戦的な作品である。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、本楽曲の印象的なフレーズを抜粋し、日本語訳を添える。
Crushed by the wheels of industry / Crushed by the wheels of industry
→ 産業の歯車に押し潰されていく 働け、そして沈めTake this job and shove it / I ain’t working here no more
→ こんな仕事、もうたくさんだ ここでなんて、もう働かないKeep your nose to the grindstone / They told me that was right
→ 粉骨砕身で働け それが正しい生き方だって、教えられたよBut I can’t stand the strain / Of the nine to five fight
→ でも毎朝9時から夕方5時までの戦いには、もう耐えられないAll the dreamers / With their heads in the clouds / Should be brought back to earth
→ 空想家たちは 夢を見てる暇なんてない 地に足をつけろと言われて
引用元:Genius Lyrics – Heaven 17 “Crushed by the Wheels of Industry”
歌詞のなかには、労働賛歌を逆手に取ったような皮肉と、現実の過酷さに直面した者の生々しい声が交錯している。
4. 歌詞の考察
「Crushed by the Wheels of Industry」は、そのタイトルが示す通り、個人が“産業社会”というシステムに従属し、やがてそれに飲み込まれていく構造を皮肉たっぷりに描いている。
注目すべきは、歌詞のなかで描かれる語り手の“二重の意識”である。彼は働くことの意味を信じようとしてきたが、その信念は雇用の不安定さ、過酷な労働条件、上からの無責任な命令によって砕かれていく。
「9時から5時の戦い」という言葉は、労働が生活の糧であるだけでなく、精神をすり減らす“戦場”でもあるという認識を示している。
また、「夢を見るな」「現実を見ろ」という周囲の声に対して、語り手は明確な反発を覚えている。これは、“自己実現”や“創造性”といった人間の本来的な欲求が、合理化と生産性に圧殺されていくプロセスに対する怒りの叫びでもある。
このように、楽曲は単なる「労働批判」ではなく、労働が人間の尊厳を奪いかねない構造そのものへの異議申し立てを行っており、それをダンサブルなサウンドで包み込むことで、聴き手を“思考しながら踊る”状態へと導いている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Working for the Clampdown by The Clash
若者が搾取され、組織に取り込まれていく恐怖を描いた政治的パンク・アンセム。 - Opportunities (Let’s Make Lots of Money) by Pet Shop Boys
資本主義と成功願望への皮肉を込めた、ダンスミュージック形式の社会批評。 - She Works Hard for the Money by Donna Summer
女性労働者の現実をポップに歌いながら、抑圧と尊厳のせめぎ合いを描く一曲。 -
Career Opportunities by The Clash
失業と労働の現実に直面する若者の怒りをストレートに叫ぶ。 -
Life During Wartime by Talking Heads
日常化した非常事態、個人の消耗と社会構造の不気味な関係を描いた都市の断章。
6. “踊る抵抗”という方法論
「Crushed by the Wheels of Industry」は、Heaven 17の楽曲群のなかでもとりわけメッセージ性の強い作品であり、社会構造とポップカルチャーの交差点に立つ楽曲である。
本来、クラブミュージックとは一種の“逃避”の手段でもあった。
だが、Heaven 17はその音楽的逃避装置を逆に利用し、「そのビートの下で起きている現実を見ろ」と語る。
それは、“踊ること”と“気づくこと”が両立可能であるという、新しい抵抗のかたちを提示している。
今の時代にも通じる問い――働くとは何か、搾取とは何か、そして自分はどこへ向かっているのか――を、
重々しくではなく、軽やかに、しかし誠実に問うこの曲は、80年代シンセポップの文脈を超えて、今もなお有効な社会批評として響き続けている。



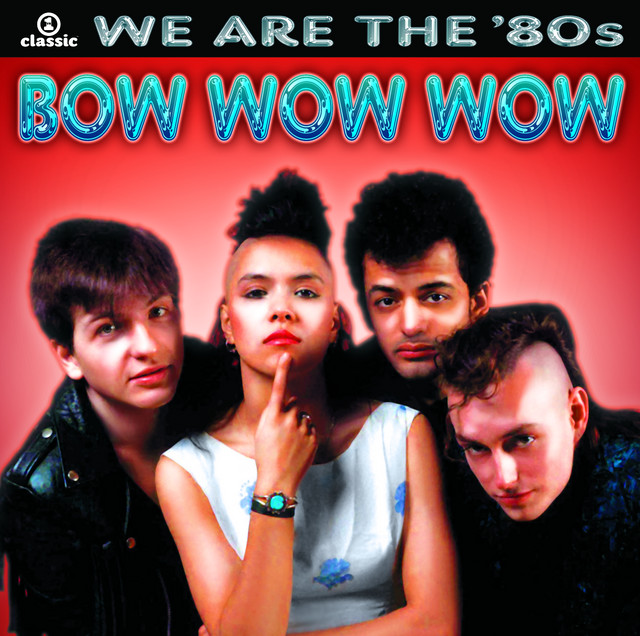
コメント