
発売日: 2022年2月25日
ジャンル: インディー・ロック、パワー・ポップ、オルタナティヴ・ロック
2. 概要
『Wild Loneliness』は、ノースカロライナ州チャペルヒルのインディー・ロック・バンド、Superchunk が2022年に発表した12作目のスタジオ・アルバムである。
前作『What a Time to Be Alive』(2018)が、トランプ政権下のアメリカへの怒りを前面に押し出した、鋭くパンク寄りのプロテスト盤だったのに対し、本作はパンデミック以後の世界で静かに胸の内を見つめ直す作品になっている。
レコーディングは、COVIDロックダウン下のノースカロライナで進められた。
メンバーがそれぞれの拠点で録音し、その素材をもとに音像を組み立てていく“距離のある制作”でありながら、耳に届くのは驚くほど親密で、柔らかなギターとコーラスのアルバムである。
ミックスを手がけたのは Wally Gagel。彼は1995年作『Here’s Where the Strings Come In』も担当しており、90年代のSuperchunkと2020年代の彼らを一本の線で結ぶ存在でもある。
サウンド面の大きな特徴は、“うるさいギター”よりも“瑞々しいアレンジ”が前に出ていることだ。
Owen Pallett のストリングス(「City of the Dead」「This Night」)、Teenage Fanclub の Norman Blake と Raymond McGinley(「Endless Summer」)、R.E.M. の Mike Mills(「On the Floor」)、Camera Obscura の Tracyanne Campbell(「This Night」)、Wye Oak の Andy Stack のサックス(「Wild Loneliness」)、そして Sharon Van Etten(「If You’re Not Dark」)といった豪華なゲスト陣が、各曲に繊細な色彩を加えている。
一方で、歌詞が見据えているのは決して“のどかなロック・ライフ”ではない。
Pitchfork は本作を“よりムーディーで抑制された作品”と評しつつ、「環境や社会の崩壊に直面した恐怖やアンビバレンス」に切り込むアルバムだと書いている。
気候変動、パンデミック、政治的不安、そしてそれらに慣れてしまう自分自身――そうした21世紀の重さが、穏やかなメロディの裏側で静かに軋んでいるのだ。
にもかかわらず、『Wild Loneliness』はどこか希望の感触を手放さない。
それは、Superchunk がここでも“アンセム”を書くことをやめていないからである。
「Endless Summer」や「If You’re Not Dark」に漂うのは、完全な諦めではなく、“それでもまだ何かを感じたいし、誰かと分かち合いたい”という、かすかな欲望だ。
批評家からの評価も高く、Metacritic では好意的なレビューが並び、Pitchforkは7.9点という高スコアを与えている。
パンデミック期に制作された作品としては珍しく、“閉塞感そのもの”ではなく、“閉塞感の中でなお鳴り続けるギター・ポップ”を提示したアルバムとして、2020年代のインディー・ロック史に位置づけられる一枚である。
3. 全曲レビュー
1曲目:City of the Dead
アルバムの幕開けを飾る「City of the Dead」は、いきなりストリングスが広がる中速ナンバーである。
Owen Pallett のアレンジによるヴァイオリンが、マックのギターと並走しながら、街の上空を滑空するようなラインを描く。
タイトルは“死者の街”と物々しいが、歌詞が描くのは、パンデミックで人通りの消えた都市や、ニュース映像の中にしか現れない“死”の統計に囲まれた現代の日常であるように思える。
静まり返った街路、閉じた店、窓の中から世界を覗く人々――そうしたイメージが、ストリングスの陰影とともにじわじわと浮かび上がる。
サウンドは決して暗黒一辺倒ではなく、アコースティック・ギターの響きやコーラスに、どこかフォーク・ロック的な温度がある。
“死んだ街”を見つめながらも、そこで生きている人間の温度までは失わない視線が、アルバムのトーンを象徴している。
2曲目:Endless Summer
先行シングルとしてリリースされた「Endless Summer」は、Teenage Fanclub の Norman Blake と Raymond McGinley がゲスト・ボーカルとして参加した、アルバムのハイライトの一つだ。
明るいタイトルとは裏腹に、ここで歌われる “終わらない夏” は、気候変動により延々と続く猛暑や、パンデミックの長期化による“終わらない異常事態”のメタファーとしても読める。
ギターは軽快に鳴っているのに、歌詞には“こんな終わり方を想像していただろうか?”といった問いが忍び込み、違和感のある高揚感を生み出しているのだ。
Teenage Fanclub 勢の柔らかなハーモニーが加わることで、90年代オルタナ〜ギター・ポップの“永遠の夏”の記憶が、2020年代の不穏な夏と重なっていく。
懐かしさと不安が同居する、非常に2020年代的なサマー・ソングである。
3曲目:On the Floor
「On the Floor」には、R.E.M. の Mike Mills がコーラスで参加し、さらに Franklin Bruno のピアノが彩りを添える。
タイトルの“On the Floor”は、ダンスフロアとも、床に崩れ落ちる感覚とも読める多義的な言葉だ。
歌詞では、ニュースやSNSから押し寄せる情報の波に飲み込まれ、地面すれすれでなんとか呼吸を続けているような心情が綴られる。
サウンドは、Superchunk にしては比較的柔らかく、ピアノのアルペジオとギターが優しく絡み合う。
そこに Mills のコーラスが乗ると、ほんの一瞬だけ R.E.M. 的なオルタナ・ポップの空気が立ち上がり、“インディー世代の継承”という文脈も感じさせる。
“床に倒れ込みそうになりながらも、まだここで鳴っている”という感覚が、今のSuperchunkらしい。
4曲目:Highly Suspect
「Highly Suspect」は、ホーン隊をフィーチャーした、アルバムの中で最もカラフルな1曲である。
Kelly Pratt が手がけたホーン・アレンジが、ギター・リフとユニゾンしたり、裏側からふわりと浮き上がったりしながら、曲全体に“湿った華やかさ”を与えている。
“Highly Suspect(かなり怪しい)”というタイトルが示すように、歌詞は日常の中で感じる漠然とした疑念や不信感を扱っている。
誰を信じればいいのか、どの情報が本当なのか分からない世界で、“何もかも怪しい”という諦めに近い感情が滲む。
その一方で、ビートは軽快で、ホーンが入ることで一種の祝祭感すら生まれている。
疑念と祝祭が同時に鳴るこの感触は、パンデミック以後の世界に特有の“ねじれたポジティヴさ”をうまく掴んでいるように思える。
5曲目:Set It Aside
「Set It Aside」は、アルバム前半の中でもひときわシンプルで、ストレートなギター・ポップである。
2分強のコンパクトな尺の中に、疾走ビートとキャッチーなサビがぎゅっと詰め込まれている。
“Set It Aside(いったん脇に置いておこう)”というフレーズは、直面し続けるには重すぎる問題――ニュース、SNS、気候、政治――を、一時的にでも棚上げしなければ心がもたない、という感覚を表しているように聞こえる。
逃避とも自己防衛とも言える行為だが、マックの歌い方はそれを責めるでも美化するでもなく、“そうするしかない夜もあるよな”というトーンなのだ。
テンションを上げながらも、どこか肩の力を抜かせてくれる位置にある曲で、A面の締めとして機能している。
6曲目:This Night
B面頭を飾る「This Night」は、Owen Pallett のストリングスと、Camera Obscura の Tracyanne Campbell のコーラスが加わる、甘くも切ないナンバーである。
歌詞は、一見するとロマンティックな“今夜”の情景を描いているが、その背後には“この夜もいずれ過去になる”という時間意識が常につきまとう。
花火のように一瞬だけ輝く親密さ、そしてその先に待つ孤独――そんな気配が、ストリングスの揺らぎに乗って立ち上がる。
Tracyanne の柔らかな声がマックと重なる瞬間、90年代以降のインディー・ポップが共有してきた“やわらかい憂鬱”が凝縮される。
パンデミック下で “この夜” を誰と、どのように過ごすかが以前よりずっと重くなってしまったことを思い出させるような楽曲である。
7曲目:Wild Loneliness
タイトル曲「Wild Loneliness」は、アルバムの概念を凝縮したような3分少々のギター・ポップだ。
ここでは Wye Oak の Andy Stack がサックスで参加し、柔らかく波打つようなフレーズで曲を包み込む。
“Wild Loneliness(野生の孤独)”という言い回しは、単なる寂しさではなく、制御不能で、時に高揚感すら伴う孤独の感覚を示しているように思える。
誰とも会えない時間が長く続くうちに、感情が内側で暴れ始める。その奇妙な“野生化”を、軽やかなメロディの下に潜ませている。
ギター・コードは明るく、サビも口ずさみやすい。
にもかかわらず、聴き終わった後に残るのは、“人と会えるようになった今でも、この孤独はどこか続いているのではないか”という感触だ。
タイトル曲として、アルバムのテーマをとても上手く言語化している。
8曲目:Refracting
「Refracting」は、“屈折”を意味するタイトルが象徴的な曲である。
光が水やガラスを通る時に進路を変えるように、言葉や感情が周囲の状況によってねじ曲がって届いてしまう――そんなイメージが浮かぶ。
サウンドは比較的ソリッドで、ギターの刻みとビートが前に出ている。
ただし、90年代的なノイジーさではなく、音数を抑えたミニマルな構成になっており、リズムの“少しのズレ”が曲名通りの“屈折感”を生んでいる。
歌詞では、真っ直ぐ届いてほしかった言葉が途中で意味を変えてしまったり、SNS上のコミュニケーションが思わぬ方向へ転がってしまうことへの戸惑いが描かれる。
“まっすぐ進もうとしても、どこかで必ず曲がってしまう”世界で、それでもなお誰かに届いてほしいと願う気持ちがにじむ。
9曲目:Connection
「Connection」は、アルバム終盤に置かれた、タイトル通り“つながり”をめぐる楽曲である。
テンポはミドルで、コードはどこかセンチメンタル。サビではコーラスが厚くなり、一瞬だけ“みんなで歌う”イメージが立ち上がる。
歌詞上の“コネクション”は、Wi-FiやSNSの接続でもあり、人間関係としての接点でもある。
電波状況は良好なのに、心の方はどこか繋がりきらない――そんな状態を、“オンライン接続”のメタファーと重ね合わせて描いているように読める。
ここまでの曲で描かれてきた“孤独”のテーマが、この曲で一段抽象度を上げて総括される。
孤独を前提にしながらも、なお“connection”を求める姿勢が、穏やかながら確かな芯を持って響く。
10曲目:If You’re Not Dark
ラストの「If You’re Not Dark」は、Sharon Van Etten をゲスト・ボーカルに迎えた、アルバムのクライマックスである。
“もし暗くないのなら/少しでもいいから暗い部分がないのなら/一体何をやっているの?/それを少し分けてくれないか?”
Pitchfork が引用したこのフレーズは、2020年代を生きる多くの人間の本音を代弁しているようにすら聞こえる。
つまり、“この時代に何も暗い部分がないなんて、おかしい。もし本当にそんなふうに生きられるなら、その秘訣を少し分けてほしい”という、半ば嫉妬混じりの言葉なのだ。
世界がここまで不穏になってしまった今、“ダークであること”はある種の正常反応であり、むしろ完全なポジティヴィティの方が不自然に見える、という感覚がある。
サウンドは決してヘヴィではないが、コード進行やコーラスの重ね方に、どこかゴスペル的な高揚感がある。
Sharon Van Etten の声がマックのリードと交差することで、“個人の暗さ”が“世代全体の暗さ”へと少しずつ広がっていく。
アルバムは、明るい希望ではなく、“暗さを自覚した上で、なお前に進もうとする感情”を残して幕を閉じる。
4. 総評
『Wild Loneliness』は、Superchunk のディスコグラフィの中で、“パンデミック期の章”を象徴するアルバムである。
『Majesty Shredding』『I Hate Music』『What a Time to Be Alive』と続いてきた“第二幕”の流れの中で、本作は明らかにトーンを変えている。
怒りのパンクでも、ノスタルジックなギター・ポップでもない、“静かな拡がり”と“内向きの不安”が同居する作品なのだ。
サウンド面で言えば、これはSuperchunkにとってもっとも“アレンジ志向”のアルバムのひとつである。
Owen Pallett のストリングス、ホーン、サックス、ピアノ、複数のゲスト・ボーカル……。
これだけ外部ミュージシャンを招きながらも、作品全体は驚くほど一貫していて、“豪華コラボ盤”というより、“長く続けてきたバンドが、信頼する友人たちを自然に呼び込んだ”という印象なのだ。
一方で、ギター・ロックとしての手触りはしっかり保たれている。
「Set It Aside」や「Refracting」には、90年代の彼らを思わせる軽快なカッティングとタイトなビートがあり、「Endless Summer」にはTeenage Fanclubと共通するラフなギター・ポップのDNAが流れている。
ただし、音数や歪みの量は抑えられており、“うるさくすることで勢いを出す”のではなく、“隙間を作ることで言葉が届く余地を確保する”ような設計になっている。
歌詞面では、『I Hate Music』で顕在化した“喪失と加齢”のテーマが、より広いスケールへと拡張されている。
そこでは、個人的な友人の死だけでなく、環境危機や民主主義の揺らぎ、情報過多による心の摩耗といった問題が、日々の散歩や夜の会話、部屋の窓から見える風景と結びつけられている。
Pitchfork が指摘するように、本作は“環境的・社会的な破局の前で抱く恐怖や迷い”にじっくり向き合うアルバムなのである。
それでも『Wild Loneliness』が救いのない作品に感じられないのは、
Superchunk が、あくまでも“誰かと一緒に歌えるメロディ”を手放していないからだ。
「Endless Summer」のコーラス、「Connection」のサビ、「If You’re Not Dark」のリフレイン――どれも歌詞だけ取り出せばかなりシリアスだが、メロディは一貫して開放的で、口ずさむと少しだけ気持ちが軽くなる。
この“明るい曲調で暗いことを歌う”という手法は、彼らが『I Hate Music』で確立したものだが、『Wild Loneliness』ではそこに“アレンジの広がり”が加わり、より繊細なニュアンスを描けるようになっている。
また、本作の“距離のある制作”という状況と、アルバム・タイトルの“孤独”は、やはり切り離せない。
メンバーは同じ部屋に集まることが難しい状況の中で、ファイルのやり取りを通じて演奏を重ねていく。
そうして出来上がった音は、ライヴ・バンドとしてのSuperchunkの疾走感とは違う、“宅録ならではの密やかなグルーヴ”を持っている。
そこにゲストたちの声や弦、管が重なり、まるでリモート会議のように“離れている人たちの存在感”がゆるやかに混ざっていく。
“野生の孤独”をテーマにしたアルバムが、これほど多くのコラボレーションによって成立している、という事実は皮肉でもあり、希望でもある。
孤独は消えないし、完全には埋められない。
しかし、それでも誰かの演奏や声が、ファイルという形で自分の曲に入り込み、気づけば“孤独の輪郭が少しだけ変わっている”――
『Wild Loneliness』は、そんな21世紀の新しい“バンドの在り方”を、静かに提示しているようにも思える。
後続の『Songs in the Key of Yikes』(2025)が、再びギター中心のパンク寄りサウンドに振り戻した“引き締まった”アルバムだとすれば、
『Wild Loneliness』はその直前に広がった“青々とした空”のような一枚である。
怒りと不安に満ちた時代の中で、一度立ち止まり、遠くの雲や、空を横切る鳥を眺める。
そんな時間をサウンドにしてみせたことこそ、このアルバムの大きな意義なのだろう。
5. おすすめアルバム(5枚)
- I Hate Music / Superchunk(2013)
喪失と加齢をテーマにした、ポスト再始動期の代表作。
『Wild Loneliness』の内省的な歌詞世界はここから続いており、パーソナルな悲しみが、やがて社会全体の不安へ広がっていく流れを知るうえで、セットで聴きたい一枚である。 - What a Time to Be Alive / Superchunk(2018)
トランプ政権への苛立ちを前面に押し出した、政治色の濃い作品。
怒りをそのままパンク・サウンドに変換した前作から、パンデミック期の『Wild Loneliness』へと移ることで、バンドが“外側への抗議”から“内側の不安”へ視点を移していく過程が見えてくる。 - Here’s Where the Strings Come In / Superchunk(1995)
90年代中期の代表作で、本作同様 Wally Gagel がミックスを担当したアルバム。
弦やコーラスを含む“厚みのあるギター・ロック”という意味で、『Wild Loneliness』との響き合いも多く、時代を超えた連続性を感じられる。 - Songs in the Key of Yikes / Superchunk(2025)
『Wild Loneliness』の“lush, expansive(豊かで広がりのある)”サウンドのあとに、再びギター中心のパンク寄りサウンドへ舵を切った13作目。
パンデミック後の社会不安と個人的な疲弊を、よりソリッドな形で鳴らしており、両作を往復することで、近年のSuperchunkのモードがより立体的に見えてくる。 - Teenage Fanclub / Songs from Northern Britain(1997)
『Wild Loneliness』で共演したNorman BlakeとRaymond McGinleyを擁するバンドの名盤。
穏やかなギター・ポップと、成熟したメロディ・センスという意味で、本作と通じる部分が多く、“大人になってもギター・バンドを続けること”の魅力をもう一つの角度から確認できる。
6. 制作の裏側
『Wild Loneliness』の制作過程を語る上で外せないのが、“パンデミック中のノースカロライナで録られた”という事実である。
バンドは地元に留まりつつ、ロックダウンの制約の中で録音を進めた。
結果として、従来のスタジオ一発録りではなく、よりファイルベースの積み重ねに近い形での制作になったが、それがサウンドの“空気の層の多さ”につながっている。
ミックスを担当した Wally Gagel は、前述の通り『Here’s Where the Strings Come In』とも関わりが深い。
90年代当時のラフで勢いのあるギター・ロックと、2020年代の柔らかなサウンドスケープ、その両方を知るエンジニアだからこそ、
ゲストを多く招いた今回の素材を、一つの統一感あるアルバムとしてまとめ上げることができたのだろう。
ゲスト陣の参加形態も、“ポスト2020年代の録音スタイル”を象徴している。
Teenage Fanclub の2人、Sharon Van Etten、Mike Mills、Tracyanne Campbell、Andy Stack らは、それぞれ自宅や別スタジオからトラックを送り、
Owen Pallett はストリングスの譜面と録音を遠隔で提供した。
顔を合わせないまま進むコラボレーションが当たり前になった時代に、こうした“ファイル越しのバンド感”をいかに保つか――その答えの一つが『Wild Loneliness』なのである。
Merge Records のサイトやインディー系ショップの解説は、このアルバムを“Superchunk史上もっとも瑞々しい作品のひとつ”と形容している。
たしかに、録音やミックスのクレジットを眺めると、音を詰め込むというより、楽器ごとの距離感や残響時間を丁寧にデザインした作りになっていることが分かる。
パンデミックで“空間の距離”を強制されたバンドが、音の中で“別の距離のとり方”を探った結果として、この豊かな音場が生まれたのだと考えると興味深い。
9. 後続作品とのつながり
『Wild Loneliness』の後、Superchunk は2023年にB面集+レアトラック集『Misfits & Mistakes: Singles, B-Sides & Strays 2007–2023』をリリースし、
“ポスト再始動期”のアウトテイクやシングルを総括した。
そこには『Wild Loneliness』期の楽曲や、同時期のセッションから生まれた曲も含まれており、この時期の創作量の多さがうかがえる。
続く13作目『Songs in the Key of Yikes』(2025)は、Pitchfork が“Wild Loneliness の lush, expansive な輪郭のあとに、よりストリップド・ダウンされたギター・ロックへ回帰した作品”と評している。
ここからも、『Wild Loneliness』がSuperchunkにとって“アレンジ面での実験と拡張”のピークであり、その次のフェーズではその経験を踏まえたうえで再びシンプルな編成に立ち戻ったことが分かる。
また、批評家の中には、『Wild Loneliness』を“2010年代以降のSuperchunk作品における一つの到達点”として位置づける声もある。
怒りを剥き出しにした『What a Time to Be Alive』と、ソリッドに引き締まった『Songs in the Key of Yikes』の間に挟まる形で、
このアルバムは“緩やかな感情のグラデーション”を描く役割を果たしている。
『Wild Loneliness』を起点に、前後の作品を行き来すると、
Superchunk がここ10数年にわたり、社会の変化や個人的な喪失と真剣に向き合いながらも、
ギター・バンドとしてのフォーマットを柔軟に変形させ続けてきたことが、いっそう鮮明になるだろう。
参考文献
- Wikipedia “Wild Loneliness”(作品基本情報、リリース日、制作背景、ゲスト参加、批評家の評価)
- Superchunk Bandcamp “Wild Loneliness”(トラックリスト、ゲスト・ミュージシャン、ストリングス/ホーンのクレジット)
- Merge Records “Wild Loneliness”(収録曲、クレジット、作品解説)
- Pitchfork “Superchunk: Wild Loneliness Album Review”(作品全体のトーン、歌詞テーマ、評価)
- Pitchfork “Superchunk: Songs in the Key of Yikes Album Review”(『Wild Loneliness』との対比と位置づけ)
- Discogs “Superchunk – Wild Loneliness”(フォーマット情報とトラックリスト確認)
- 各種インディー系ショップ解説・レビュー(ゲスト陣と“瑞々しさ”の評価)


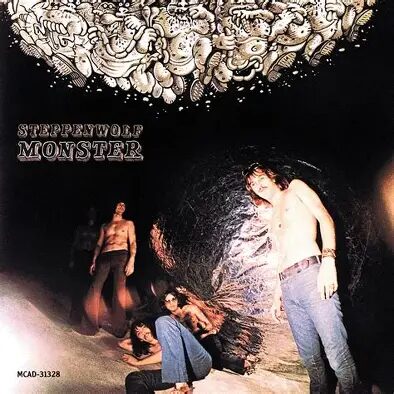
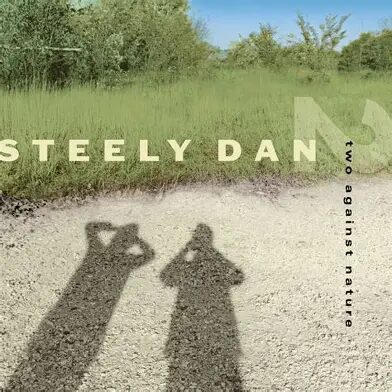
コメント