
発売日: 1975年9月
ジャンル: ハード・ロック、アシッド・ロック
2. 概要
『Hour of the Wolf』は、カナダ/アメリカのロック・バンド Steppenwolf が1975年に発表した8作目のスタジオ・アルバムである。
前作『Slow Flux』に続く、いわゆる“Epic期”3部作の真ん中に位置する作品であり、再結成 Steppenwolf のサウンドがどこへ向かおうとしていたのかを示す指標のようなアルバムなのだ。
録音は John Kay の自宅スタジオで行われ、プロデュースもバンド自身が担当。
前作ではオリジナル・メンバーの Goldy McJohn がまだ在籍していたが、本作では彼が解雇され、新たに Andy Chapin がキーボードとして加入している。
このメンバーチェンジにより、Steppenwolf の“重く荒いオルガン・サイケ”は、より滑らかな70年代型キーボード・ロックへと姿を変えていく。
ラインナップは、John Kay(Vo/Gt/Harmonica)、Jerry Edmonton(Dr)、George Biondo(Ba)、Bobby Cochran(Lead Gt)に Andy Chapin(Key)の5人編成。
そこに Tom Scott がホーン(サックス/ブラス)で参加し、オープニング「Caroline (Are You Ready for the Outlaw World)」や「Hard Rock Road」のサウンドに、ソウル/R&B寄りのニュアンスを付け加えている。
タイトルにある“Hour of the Wolf(狼の刻)”は、北欧の伝承などで“真夜中から夜明け前、もっとも不安と恐怖が増幅する時間帯”を指すことが多い。
アルバムそのものはコンセプト作ではないが、“自由とアウトロー幻想が薄れ、現実の重さだけが残った70年代半ば”という時代の空気を、このタイトルは象徴しているようにも思える。
サウンド面では、前作『Slow Flux』のブルージーなハード・ロック路線を受け継ぎつつ、全体のトーンは一段滑らかでポップ。
ホーンとキーボードが前に出たアレンジや、FM向けのミドル・テンポ曲が増え、60年代末のガレージ/サイケ的な荒々しさは少し後退している。
ある批評では「よりスムーズで、70年代的で、Dr. John 風の雰囲気も匂わせるアルバム」と形容されており、実際、ロックにソウルやシティ・ポップ的感触を織り込もうとする姿勢が見て取れる。
にもかかわらず、本作には「Born to Be Wild」「Magic Carpet Ride」のような“誰もが知るキラー・チューン”は存在しない。
Mars Bonfire 作の「Caroline (Are You Ready for the Outlaw World)」がシングル・カットされるもチャートインには至らず、アルバムも全米Billboard 200で155位止まりという、商業的には控えめな結果に終わる。
批評面でも、AllMusic などの後年のレビューは「演奏も曲も一定の水準にはあるが、過去のSteppenwolfフォーミュラをなぞりすぎている」と辛口だ。
一方で、Epic期3作をまとめたボックス『The Epic Years 1974–1976』のレビューでは、「3作の中で最もバランスが良い」「『Another’s Lifetime』『Mr. Penny Pincher』はバンド後期のハイライト」と評価する声もあり、意外と“通好みの一枚”として支持されている側面もある。
つまり、『Hour of the Wolf』は、Steppenwolf のキャリアの中で“地味だが噛めば噛むほど味が出る”タイプのアルバムなのだ。
60年代の代表曲とは違う角度から、バンドの成熟したソングライティングと70年代的なサウンド・プロダクションを味わえる作品と言えるだろう。
3. 全曲レビュー
1曲目:Caroline (Are You Ready for the Outlaw World)
オープニングを飾るのは、「Born to Be Wild」の作曲者 Mars Bonfire による提供曲「Caroline (Are You Ready for the Outlaw World)」。
ホーンとキーボードが前面に出たポップ寄りのロック・チューンで、Tom Scott のサックスがレズリー・スピーカーを通した歪んだトーンで吹きまくる。
リフそのものはSteppenwolfらしいゴツゴツした質感だが、全体の音像はかなり“ラジオ・フレンドリー”で、70年代中盤のAOR/ポップ・ロックの空気をまとっている。
歌詞の“アウトロー・ワールドに入る準備はできているか”というフレーズは、60年代末に彼ら自身が象徴していたバイカー的自由への、少しメタな視線も感じさせる。
ただし、歌の描くアウトロー像は、かつてのような反体制の英雄というより、“少し危険な大人の世界”といった軽やかなニュアンスに寄っている印象だ。
シングルとして推されたこともあり、“ヒットを狙ったSteppenwolf”という意味で象徴的な1曲。
一方で、コアなファンからは「良くできているが、らしさが薄い」とも語られることが多く、アルバム全体の評価を分ける分岐点にもなっている。
2曲目:Annie, Annie Over
Alan O’Day 作の「Annie, Annie Over」は、ややブルージーなポップ・ロック。
前曲よりもギターとオルガンのバランスが良く、Steppenwolf本来のハード・ロック寄りの顔が戻ってくる。
イントロのオルガンは70年代らしい太いトーンで、コードを塊として鳴らしつつ、ところどころで短いフィルを差し込む。
Kayのしゃがれ声と相まって、ラジオ向けの親しみやすさと、“ウルフ節”のワイルドさがちょうど中間地点で溶け合うような一曲である。
歌詞は、タイトルに登場する“Annie”との関係をめぐる物語。
過去と現在が交差し、どこか手放せない未練と、前に進まなければならない現実が同時に描かれている。
激しく叫ぶのではなく、ミドル・テンポのグルーヴの中でじわじわと感情を滲ませるタイプのラブソングと言えるだろう。
3曲目:Two for the Love of One
「Two for the Love of One」は、George Biondo と Jerry Edmonton の共作。
前の2曲に比べると、ギターの歪みが強く、よりロック色の濃いナンバーである。
ギター・リフを軸に進む“肉厚なロック・チューン”でありながら、オルガンが要所要所でフレーズを差し込むことで、Steppenwolfらしいサイケデリックな陰影も生まれている。
歌詞のテーマは、タイトルどおり“ひとつの愛に向かう二人”。
三角関係や浮気といったドロドロした世界ではなく、“ふたりでひとつの方向を見る”というポジティブなイメージが強い。
John Kay のヴォーカルも、この曲では比較的柔らかく、熱量よりも“確信”を優先した歌い方をしているように聞こえる。
アルバム前半の中では、1曲目のポップさと5曲目のヘヴィネスをつなぐ“中間地点”として機能しており、地味ながら流れを整える重要な役割を担っている。
4曲目:Just for Tonight
「Just for Tonight」は、Bobby Cochran と Jerry Edmonton による共作。
静かなイントロから始まり、サビでハード・ロック的な盛り上がりに至るダイナミクスの大きな1曲で、Epic期Steppenwolf の“バラード〜ミディアム路線”の中でも完成度が高い。
前半はクリーン・トーンのギターとキーボードが空間を作り、Kay が抑えた声で語るように歌う。
そこからドラムのフィルをきっかけに歪んだギターが入り、サビでは70年代ハード・ロック然とした高揚感が爆発する構成だ。
タイトルの“今夜だけ”というフレーズが示すように、歌詞は一夜限りの逃避、あるいは期限付きの慰めをめぐる物語。
永遠の愛や革命を歌っていた60年代のSteppenwolfからすると、ここにはずいぶん現実的で仄暗いロマンスの感覚がある。
ただ、その“限定された幸福”がサビの爆発と重なることで、曲としては非常にエモーショナルに響くのが興味深い。
5曲目:Hard Rock Road
B面頭の「Hard Rock Road」は、Jerry Edmonton が単独で書いたナンバーで、その名のとおり“ハード・ロック街道”を走り続けるバンドの自己イメージを重ねたような楽曲である。
テンポはミディアムだが、ドラムはタイトで、リフも分かりやすい。
そこにTom Scott のホーンとコーラスが乗ることで、アメリカ南部のサザン・ロックやLynyrd Skynyrd 的な要素もちらりと顔を出す。
歌詞で描かれる“Hard Rock Road”は、単なるツアー道中のことではなく、時代の変化の中で居場所を探し続けるロック・バンドの宿命の比喩にも読める。
60年代に時代の先頭を走っていた Steppenwolf が、70年代半ばの新しい潮流の中でも自分たちの道を歩き続ける――そんな決意表明のようにも感じられる一曲である。
6曲目:Someone Told a Lie
「Someone Told a Lie」は、Bobby Cochran と John Kay らによる共作。
前曲の“ロード・ソング”的な雰囲気から一転し、より内省的でミステリアスなムードを持ったロック・チューンだ。
ギターがトーキング・モジュレーター/ワウ的なエフェクトを使い、オルガンがうねることで、70年代ハード・ロックとプログレの境界線のようなサウンドが立ち上がる。
歌詞では、“誰かが嘘をついた”というシンプルな一文から、人間関係と信頼が崩れていく様子が描かれる。
それは恋愛関係かもしれないし、バンド内のことや、社会全体に対する幻滅の比喩とも読める。
サビでの“Lie”の反復は、60年代的理想主義が剥がれ落ちた後の虚無感を凝縮したような響きを持っている。
アルバム後半のハイライトのひとつであり、Bobby Cochran 期Steppenwolfの“ちょっと捻れたグルーヴ”を最も分かりやすく伝えてくれる楽曲だと言えるだろう。
7曲目:Another’s Lifetime
「Another’s Lifetime」は、外部ライター Wayne Berry による提供曲。
ブルース・バラード風の導入から始まり、じわりと熱を帯びていく構成で、アルバムの中でもとりわけメロディアスな一曲である。
ギターは抑え気味にコードを鳴らし、Biondo のベースと Chapin のキーボードが、曲の感情の起伏をゆっくりと支えていく。
歌詞のテーマは“他人の人生”。
別の誰かの人生を羨望しつつ、しかし自分自身の現実から逃れられない主人公の視点が描かれる。
“もし別の人生を生きられたなら”というモノローグは、ベトナム戦争や政治的不信を経験した70年代世代の心の奥底に、静かに響く問いでもあっただろう。
Epic期3作を俯瞰したレビューなどでは、「『Another’s Lifetime』はSteppenwolf後期の隠れた名曲」として挙げられることも多く、歌詞・メロディ・演奏のバランスが非常に高いレベルでまとまったトラックである。
8曲目:Mr. Penny Pincher
ラストを飾る「Mr. Penny Pincher」は、Van Dunson 作曲による6分超の大作。
サウンド面では、“Steppenwolf流プログレ”とでも呼びたくなるような構成を持ち、Epic期3作の中でも屈指の野心作として語られている。
Andy Chapin のキーボードが複雑なフレーズとコード・ヴォイシングを繰り出し、楽曲を引っ張っていく。
途中でテンポや雰囲気が変化し、ロック・ミュージカル的な劇的展開すら感じさせる部分もある。
“Mr. Penny Pincher”というキャラクターは、極端なケチ、あるいは金の亡者の象徴だ。
歌詞では、金勘定しか頭にないこの人物の姿を通して、資本主義社会の冷たさや、ヒューマンな価値の喪失が皮肉たっぷりに描かれている。
初期の「The Pusher」がドラッグ・ディーラーとその背後にあるシステムを批判していたのだとすれば、「Mr. Penny Pincher」は70年代型の“お金のシステム”への批評と言えるかもしれない。
Epic期ボックスのレビューでは、「キーボードの妙技が光るプログレッシヴなハイライト」「Steppenwolfが取り得たかもしれない別ルートを示す曲」と評されており、アルバムを象徴する一曲であることは間違いない。
4. 総評
『Hour of the Wolf』は、Steppenwolf のキャリアの中で、明確に“過渡期”に属するアルバムである。
ひとつには、キーボーディストの交代。
Goldy McJohn のオルガンが作り出していたサイケデリックで荒々しい質感は、Andy Chapin のスマートで多彩なキーボード・ワークへと置き換えられた。
これにより、サウンドはぐっと70年代的になり、同時代のハード・ロック/プログレ/AOR的な要素がミックスされた“複合的なロック・サウンド”へと変化している。
もうひとつは、レーベル事情とバンドの立ち位置だ。
Mums Records が畳まれた後、Steppenwolf は Epic 本体のロースターの一部となったが、レーベル側が“受け継いだカタログ”程度にしか見ていなかったという証言もあり、プロモーション面では決して恵まれていなかった。
実際、シングル「Caroline」はチャートに乗れず、アルバムもBillboard 200で155位と振るわない。
音楽的にはどうか。
AllMusic のような一部の批評は「過去のSteppenwolf・フォーミュラに頼りすぎた凡作」と手厳しいが、Epic期3作を俯瞰したレビューやファンの声では、「3枚の中で最もソングライティングが安定している」「『Another’s Lifetime』『Mr. Penny Pincher』は後期Steppenwolfの代表曲」と高評価するものも少なくない。
実際に耳を傾けると、アルバムの前半は“70年代FMロックとしてのSteppenwolf”が強く打ち出されている。
ホーンとキーボードを前面に出した「Caroline」、ポップ寄りの「Annie, Annie Over」、ミドル・テンポのロック「Two for the Love of One」、バラードから轟音まで行き来する「Just for Tonight」。
ここには、当時のDoobie Brothers的なウェストコースト・ロックや、Uriah Heep の鍵盤推しハード・ロックと共振するようなアレンジが見られる。
一方で、後半の「Someone Told a Lie」「Another’s Lifetime」「Mr. Penny Pincher」では、より内省的でプログレッシヴな側面が顔を出す。
ここでは、ポップなヒットを狙うモードから離れ、バンド自身が興味を持っていたであろうハーモニーや構成の実験が前に出てくる。
Epic期ボックスのレビューの言葉を借りれば、「退屈な瞬間もあるが、静かな曲や『Mr. Penny Pincher』のような複雑な曲は、バンドが取り得た代替的な進化の道を示している」作品なのである。
同時代のバンドと比べると、このアルバムの立ち位置も見えてくる。
たとえば、The Doors の『L.A. Woman』や、Uriah Heep、初期のDoobie Brothers など、ブルース/ソウルの要素とハード・ロックを交差させた作品が70年代前半には多数存在した。
『Hour of the Wolf』は、その文脈の中で、“Steppenwolfなりの大人のロック”を模索した作とも言える。
ただし、彼らはすでに“Born to Be Wild”という巨大なイメージを背負っており、その期待値と比較されるがゆえに、どうしても過小評価されがちなアルバムでもある。
音響的には、Roy Halee のミキシングもあって、サウンドは非常にクリアでレンジが広い。
ドラムとベースはタイトかつドライに録られ、キーボードは楽曲によってオルガン、ピアノ、シンセ系の音色を使い分けている。
60年代のDunhill期作品と比べると、“ラジオで鳴らすことを意識した70年代ロック・アルバム”としての作り込みがはっきりと感じられるだろう。
総じて、『Hour of the Wolf』は“代表曲がないが、アルバム単位で聴くとじわじわ効いてくる”タイプの作品である。
Steppenwolfをベスト盤や初期の3〜4枚で止めているリスナーにとっては、“バンドの70年代後期像”を知るための重要なピースと言えるだろう。
ポリティカルでドラッギーな60年代のイメージから離れ、成熟したロック・バンドとしてのSteppenwolfを捉え直す――その目的に、最も適した一枚のひとつが、この『Hour of the Wolf』なのだ。
5. おすすめアルバム(5枚)
- Slow Flux / Steppenwolf(1974)
同じEpic期3部作の1作目。
「Straight Shootin’ Woman」「Smokey Factory Blues」など、よりブルージーで60年代寄りのハード・ロックが楽しめる。
『Hour of the Wolf』と聴き比べると、キーボード・サウンドやアレンジの変化がよく分かる。 - Skullduggery / Steppenwolf(1976)
Epic期3部作のラスト。
タイトル曲や「Life Is a Gamble」など、ファンや批評家から評価の高い曲を含みつつ、バンドのエネルギーが尽きつつある様子も垣間見える。
『Hour of the Wolf』の翌年作品として、バンドの終着点を確認する意味でもおすすめである。 - Steppenwolf 7 / Steppenwolf(1970)
「Snowblind Friend」「Who Needs Ya」などを収録した中期の名盤。
まだGoldy McJohn のオルガンがフルに活躍しており、サウンドはよりヘヴィでサイケ寄り。
この作品と『Hour of the Wolf』を聴き比べることで、70年代前半〜中盤にかけてのバンドの変遷が立体的に浮かび上がる。 - Monster / Steppenwolf(1969)
ベトナム戦争とアメリカ史をテーマにした、もっとも政治色の強いコンセプト・アルバム。
マクロな政治批評に徹した『Monster』と、日常や個人的感情を主題にした『Hour of the Wolf』を対比すると、10年足らずの間に変わったもの/変わらなかったものが見えてくる。 - L.A. Woman / The Doors(1971)
同じくアメリカのロック・バンドが、ブルースやR&Bを取り込みつつ、都市の闇と幻滅を描いた作品。
直截なサイケから一歩引き、大人びたハード・ロックへと移行するプロセスが、SteppenwolfのEpic期とどこか響き合っている。
ウェストコースト/アメリカン・ロック全体の流れの中で、『Hour of the Wolf』を位置づける手がかりとなる一枚だ。
8. ファンや評論家の反応
『Hour of the Wolf』の評価は、発売当時から現在に至るまで、やや分かれ気味である。
まず、商業的な指標を見ると、アルバムは全米Billboard 200で155位。
シングル「Caroline (Are You Ready for the Outlaw World)」は“Born to Be Wild”の作者 Mars Bonfire による楽曲という期待もあったが、チャート入りには至らなかった。
70年代半ばのロック市場の中では、すでに“往年のバンドによる地味な新作”という受け取られ方だったと考えられる。
批評の面では、AllMusic が「曲はどれも一定のレベルにあるが、すでにやり尽くされたSteppenwolfのフォーミュラに頼りすぎている」と否定的なレヴューを残している。
また、一部のコラムでは「このアルバムは、もはやSteppenwolfとは呼べない瞬間を示す作品」「ミッド70年代のロック・サブジャンルを無理に追いかけた結果、方向性がぼやけてしまった」と辛辣な評価も見られる。
しかし近年、Epic期3作をまとめたボックス『The Epic Years 1974–1976』のリリース以降、評価はかなり揺り戻されつつある。
イギリスやヨーロッパのロック・メディアでは、「3枚の中で最もまとまったアルバム」「キーボード主導のサウンドがUriah Heep的で、70年代ハード・ロックとして再評価されるべき」といったポジティブなレビューも増えている。
特に、「Mr. Penny Pincher」は“プログレッシヴで、時代を先取りした1曲”“ロック・ミュージカル的なダイナミクスを持つ異色曲”として、批評家・ファン双方からハイライトに挙げられることが多い。
また、「Another’s Lifetime」や「Someone Told a Lie」も、歌詞とアレンジの両面で後期Steppenwolfの代表格として評価されつつある。
一方で、ファン・コミュニティの声を見ていくと、“Steppenwolfの中で必須ではないが、聴き込むと手放せなくなるアルバム”“ベスト盤だけでは分からないバンドの深みが出ている作品”という位置づけが一般的だ。
特に、長らくCD/LPともに入手が難しかったこともあり、“ようやく聴けたら予想以上に良かった”という感想も目立つ。
総じて、『Hour of the Wolf』は“評価が割れたまま埋もれてきた作品”から、“一部のリスナーに強く支持されるカルト的名盤”へと、ゆっくりと位置を変えつつあるように思える。
Steppenwolf の60年代的イメージに縛られない耳で聴くとき、そこに現れるのは、70年代の空気を吸い込みながらも、独自の声を保ち続けた中年期のロック・バンドの姿なのである。
参考文献
- Wikipedia “Hour of the Wolf”(アルバム基本情報、トラックリスト、パーソネル、チャート/シングル情報)
- Wikipedia “Steppenwolf (band) / Discography”(再結成期の経緯、Epic期3作の位置づけ、チャートデータ)
- Discogs “Steppenwolf – Hour Of The Wolf”(クレジット、Tom Scottのホーン参加、各曲クレジット)
- Rockasteria “Steppenwolf - Hour Of The Wolf (1975…)”(制作背景、Andy Chapin加入、音の傾向に関する記述)
- AllMusic “Hour of the Wolf – Steppenwolf”(後年の辛口レビュー、スタイル評)
- Record Collector / Burning Ambulance ほか “Slow Flux & Hour Of The Wolf / Steppenwolf Epic Yearsレビュー”(“よりスムーズで70年代的”という評価、ポップ寄りのサウンド分析)
- Ever-Metal / MusicStreetJournal / Echoes and Dust / Keys and Chords “The Epic Years 1974–1976” レビュー(Epic期ボックス全体像、『Mr. Penny Pincher』『Another’s Lifetime』などの高評価)


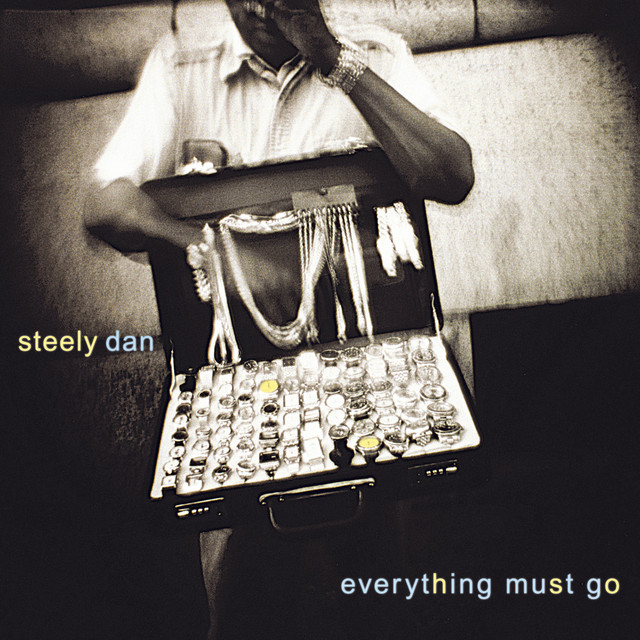

コメント