
発売日: 1971年9月
ジャンル: ルーツ・ロック、アメリカーナ、フォークロック
概要
『Cahoots』は、The Band が1971年に発表した4作目のアルバムである。
アメリカ音楽の伝統を深く吸い上げながら、壮大な物語性と“歴史のうねり”を感じさせる音楽をつくり出した彼らにとって、本作はひとつの転換点となった。
1968年『Music from Big Pink』、1969年『The Band』という二枚の革命的作品を経て、バンドは“アメリカ音楽の語り部”として世界的な評価を獲得した。だが、70年代に入り、その重責やツアー疲れ、そして時代の劇的な変化がメンバーの精神を徐々に蝕み始める。
そんな空気の中で制作された『Cahoots』には、初期2作のような素朴で温かい神話性だけではなく、時代への違和感、焦燥、陰りといった新たな感情がはっきりと刻まれている。
作曲の中心である Robbie Robertson は、アメリカ文化の荒廃、都会と田舎の断絶、機械文明、人の孤独といったテーマを歌詞に盛り込み、The Band を“懐古的ルーツロックの英雄”ではなく、“変わりゆくアメリカの観察者”へと変化させた。
同時に、Levon Helm、Rick Danko、Richard Manuel の個性的なボーカルが、それぞれ異なる情緒を与え、本作の多彩な物語性を形づくっている。
音楽的にはフォーク、カントリー、ゴスペル、ニューオーリンズ・ジャズ、ブルースを混ぜ合わせた、The Band らしいアメリカーナの継続だが、同時にどこか疲れや哀愁を帯びたサウンドが特徴となっている。
ゲストには Van Morrison が参加しており、彼のスピリチュアルな声がアルバム後半の雰囲気を一段と深めている。
The Band の代表作として語られることは少ないが、
“1970年代のアメリカの影と光をもっとも正直に写し取った作品”
として、現在では重要度が再評価されつつある。
全曲レビュー
1曲目:Life Is a Carnival
タイトルどおり、人生をカーニバルに例える皮肉と祝祭が混ざる一曲。
ニューオーリンズ風のブラスが跳ね、後期 Band の“雑多で賑やか、しかしどこか切ない”空気を象徴している。
リズムは軽やかだが、歌詞には社会の欺瞞や現実の厳しさへの洞察があり、陽気さと影が同居する名オープニング。
2曲目:When I Paint My Masterpiece
ボブ・ディラン作の名曲をThe Bandが豊かに解釈したヴァージョン。
Levon の土臭い歌声が“旅する芸術家”の気分を自然体で描き出し、アコーディオンとマンドリンが異国の風景を連れてくる。
The Band という存在の“物語性”と相性の良い楽曲であり、アルバムのハイライト。
3曲目:Last of the Blacksmiths
アメリカの古い職人文化の消失を描いた重たいテーマの曲。
Richard Manuel の繊細で儚い声が“消えゆくもの”の悲しみを深く表現する。
都会化・機械化のなかで失われる技と記憶を悼む、The Band の良心が光る一曲。
4曲目:Where Do We Go from Here?
未来への不安と迷いを歌ったブルーズ寄りの楽曲。
Rick Danko のあたたかい歌声が、混乱の時代でもなお前を向こうとする優しい精神を感じさせる。
シンプルな構成ながら、深い余韻がある。
5曲目:4% Pantomime
Van Morrison が参加したソウルフルなロック・ナンバー。
彼のスピリチュアルな叫びと Rick Danko の粘っこい歌声が絡み、濃厚なグルーヴを生み出す。
酔いと混乱の物語をモチーフにしつつ、音楽には強烈な生命力が宿っている。
6曲目:Shoot Out in Chinatown
アジア文化を題材にした“都会の寓話”のような曲。
物語性が強く、暗がりの裏通りを歩くようなムードが漂う。
Garth Hudson のキーボードワークが光り、映画的な広がりを作り上げる。
7曲目:The Moon Struck One
喪失、子ども、罪、許しといったテーマが複雑に絡み合うバラード。
Richard Manuel の声が胸に迫り、アルバムの中でも最も感情的なトラックのひとつ。
静かな夜の祈りのような雰囲気がある。
8曲目:Thinkin’ Out Loud
フォークロックらしい明るさを持ちつつ、歌詞は手放すべき過去や変わりゆく時代をめぐるもの。
軽快さの裏に、The Band の“年輪”がにじむ。
9曲目:Smoke Signal
ネイティブ・アメリカンの文化を象徴する“狼煙”を題材にした曲。
壮大なテーマを扱いながらも、音はシンプルでスピリチュアル。
Garth Hudson のオルガンが聖なる雰囲気をもたらす。
10曲目:Volcano
強いビートと熱を帯びた演奏が印象的な楽曲。
“噴火”という比喩を用いて、抑え込んだ感情の爆発を描く。
アルバム終盤を盛り上げるダイナミックな曲。
11曲目:The River Hymn
静けさと敬虔さに満ちたゴスペル調の曲でアルバムは幕を下ろす。
女性コーラスの温かみと Richard Manuel の深い情感が重なり、
川=人生の流れ を象徴的に描いた美しいラスト。
The Band の“祈り”のような余韻が残る。
総評
『Cahoots』は、The Band の“輝かしい神話時代”の後に訪れた、
成熟と疲労、変化への戸惑い が入り混じる複雑なアルバムである。
初期2作の土の香りが漂う無垢なアメリカーナとは異なり、
ここには“時代の影”がはっきりと入り込んでいる。
文化の崩壊、機械化、都市化、人間の孤独。
彼らが愛したアメリカの姿が揺らぎ始める中で、その現実を正直に記録した作品ともいえる。
そのため、本作は派手な名曲こそ少ないが、
“失われつつあるアメリカの情景”を描いた貴重なドキュメント
としての価値が高い。
ボーカルの三人はそれぞれの感情を深く掘り下げ、
Garth Hudson のキーボードは神話よりも“現実の重さ”を照らし出す。
Van Morrison との共演も、本作のスピリチュアルな深みを際立たせている。
The Band の旅路を語るうえで欠かせない、
“揺れる70年代を生きた彼らの姿” が記された一枚だ。
おすすめアルバム(5枚)
- The Band / The Band (1969)
アメリカーナの金字塔。『Cahoots』との対比がもっとも鮮明に分かる必聴作。 - Music from Big Pink / The Band (1968)
ルーツロックの革新作。初期の無垢な精神を感じられる。 - Stage Fright / The Band (1970)
心の不安と名声の重圧を描いた、より内省的な作品。本作の直接的前章。 - Northern Lights – Southern Cross / The Band (1975)
成熟期の名盤。70年代後半の華やかさと深みが交差する。 - Moondance / Van Morrison (1970)
『Cahoots』に参加した Van Morrison の名作。スピリチュアルなソウル感が本作と響き合う。


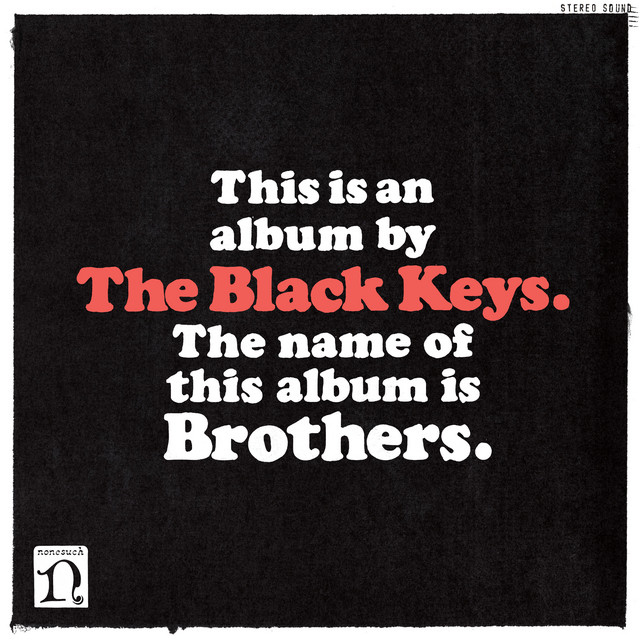

コメント