
発売日: 1972年10月
ジャンル: フォーク、カントリーフォーク、アダルトコンテンポラリー
概要
『Old Dan’s Records』は、ゴードン・ライトフットが1972年に発表したスタジオアルバムであり、
彼の音楽的成熟と自然体の表現が心地よく融合した、穏やかで温かみのある作品である。
前作『Don Quixote』が理想と現実を見つめる叙情詩的世界だったのに対し、
本作ではよりプライベートな感覚に近く、
日常生活、旅路、愛、そして人生の小さな瞬間が静かに描かれている。
全体を通して、
フォークとカントリーを自然にブレンドしたリラックスした音作りが特徴であり、
ライトフットの飾らない歌声と優しいギターサウンドが、
聴く者に静かな親密さを感じさせる。
全曲レビュー
1. Farewell to Annabel
別れた恋人へのほろ苦い思い出を、
軽やかなリズムに乗せて歌った、優しい別れの歌。
2. That Same Old Obsession
忘れられない恋心に囚われ続ける葛藤を描く、内省的なフォークバラード。
3. Old Dan’s Records
アルバムタイトル曲。
古いレコードに針を落とすたびに蘇る思い出を、
懐かしさと温かみを込めて描いた、ライトフットらしい小品。
4. Lazy Mornin’
ゆったりとした朝の情景を切り取った、のどかでリラックスしたナンバー。
5. You Are What I Am
自己肯定感と愛への感謝をテーマにした、明るく親しみやすいカントリーポップソング。
6. Can’t Depend on Love
恋に期待してしまう脆さと失望を、軽快なビートに包んで歌う。
7. My Pony Won’t Go
人生の思い通りにいかない苦笑いを、
ユーモラスに、しかしどこか切なく描いたナンバー。
8. It’s Worth Believin’
希望と信念の大切さを、静かに、しかし確かに訴える心温まるバラード。
9. Mother of a Miner’s Child
労働者階級の女性を主人公に据えた、
社会的な視線を滲ませたフォークバラード。
ライトフットのストーリーテリングが冴える。
10. That’s What You Get for Lovin’ Me
自身のヒット曲のセルフカバー。
皮肉混じりの別れの歌を、原曲よりも軽やかに再演している。
総評
『Old Dan’s Records』は、
ゴードン・ライトフットがフォークの詩人としてだけでなく、
人間味あふれるストーリーテラー、
そしてリスナーに寄り添う温かなシンガーとしての側面を見せたアルバムである。
派手さはないが、
一曲一曲がまるで古い日記をめくるような親密さを持ち、
日常の中に潜む美しさと哀しみを、そっとすくい取っている。
音楽的にも、
フォーク、カントリー、アダルトコンテンポラリーのバランスが絶妙で、
1970年代初頭のアメリカン・ミュージックシーンに自然に溶け込む柔軟さを備えている。
『Old Dan’s Records』は、
特別な出来事ではなく、
普通の日々のかけがえのなさを歌った、静かな傑作なのである。
おすすめアルバム
- Gordon Lightfoot / Don Quixote
より叙事詩的なテーマとスケール感を持つ前作。 - John Denver / Rocky Mountain High
自然と人生の喜びを歌う、同時代の代表的フォークポップアルバム。 - James Taylor / One Man Dog
シンプルで親密なサウンドと、家庭的な叙情を描いた作品。 - Willie Nelson / Phases and Stages
愛と喪失をテーマにした、カントリーミュージックの名盤。 - Jim Croce / You Don’t Mess Around with Jim
1970年代初頭のアメリカ的叙情を軽やかに描いたシンガーソングライター作品。
歌詞の深読みと文化的背景
1972年――
アメリカは依然としてベトナム戦争の影を引きずり、
カナダでも社会的緊張が続く中、
若者たちは理想と現実の狭間で、新しい生き方を模索していた。
そんな時代に『Old Dan’s Records』が描くのは、
政治や社会運動ではなく、
もっと小さな、しかし確かな日常の情景である。
「Old Dan’s Records」で歌われる、
古いレコードに針を落とす瞬間に蘇る思い出、
「Mother of a Miner’s Child」で描かれる、
社会の片隅で生きる女性たちの物語――
ライトフットは、
時代の喧騒とは距離を取りながら、
**”普通の人間のささやかな営みこそが、
最も大切な物語なのだ”**というメッセージを、
静かに、そして誠実に紡いだ。
『Old Dan’s Records』は、
そんな**時代を超えて寄り添い続ける、”日々の歌”**なのである。



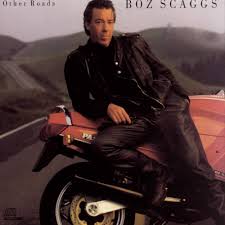
コメント