イギリスのロック史を振り返るとき、グラムロックやブリティッシュ・ハードロックの影に隠れがちな存在ながら、ひときわ強い個性を放つバンドがいる。
それがMott the Hoopleである。
“地味なようでいて大胆、脆いようでいて激しい”といった二面性を抱え、1970年代初頭にグラムロックの洗礼を受けた彼らは、一瞬の閃光のようにシーンを駆け抜けていった。
Mott the Hoopleは、デヴィッド・ボウイの後押しを受けて大ブレイクしたバンドとして語られることが多い。
しかし、その背後にはメンバー間の個性的な化学反応と、イギリス特有の階級社会が生む若者の鬱屈、そしてロックへの情熱が渦巻いていたのだ。
このバンドが生み出したアルバムや楽曲を丁寧に辿ると、彼らが単なる「ボウイの庇護下の存在」ではなく、独自の輝きを放つロック・バンドであったことに気づかされるはずだ。
バンドの結成と初期の背景
Mott the Hoopleの前身は、ギタリストのミック・ラルフスが中心となって結成された“Silence”というバンドである。
ベースのピート・オーヴァーエンド・ワッツ、ドラマーのデイル・“バッフォ”・グリフィン、そしてオルガン担当のヴァーデン・アレンらが在籍し、ブリティッシュ・ロックの伝統を受け継いだブルージーなサウンドを鳴らしていた。
しかし当時、シーンを席巻していたのはレッド・ツェッペリンやブラック・サバスといったヘヴィなグループであり、Silenceはなかなか突出した存在になれなかった。
そんな状況を打開するため、バンドは新たなフロントマンを探すことになり、そうして迎え入れられたのがイアン・ハンターだった。
もともとロックだけでなくフォークやR&Bにも影響を受けていたイアンの参加により、バンドには独特のメロディセンスや歌詞世界がもたらされることになる。
音楽ジャーナリストでありレコード・プロデューサーでもあったガイ・スティーヴンスの手助けを得て、Silenceは“Mott the Hoople”という奇妙なバンド名でデビューを飾る。
その名前はウィルラード・マナスの小説『Mott the Hoople』から拝借したとされ、“アウトサイダー感”を全面に押し出す彼らの立ち位置を象徴するものとなった。
音楽性と影響――グラムロック以前の姿
初期のMott the Hoopleは、ブルースやR&Bを基調としたラフで重厚なサウンドを鳴らしていた。
デビューアルバム『Mott the Hoople』(1969年)はディランの「Like a Rolling Stone」をカバーするなど、アメリカン・ルーツへの接近が感じられる一方で、イギリス的な叙情も微かに香り、バンドの“土臭さ”がリスナーを引きつけた。
続くセカンド『Mad Shadows』(1970年)やサード『Wildlife』(1971年)でも、やはりブルース・ロックやフォーク寄りのテイストが目立つ。
後にグラムロックの光を浴びて華やかな存在になっていく彼らだが、この頃の作品を聴くと、“無骨さと繊細さ”の境界を揺れ動くような、荒削りながらも味わい深いバンドの姿が垣間見える。
当時のロック・シーンはレッド・ツェッペリンやディープ・パープルが台頭してきており、ハードかつ派手なパフォーマンスが主流になりつつあった。
一方でイアン・ハンターのボーカルはややしゃがれつつも憂いを帯び、歌詞には“孤独”や“挫折”といったテーマが色濃く描かれていた。
こうした感情表現が、従来のハードロック・バンドとの差別化につながっていくのである。
デヴィッド・ボウイとの邂逅――「All The Young Dudes」での大転機
キャリア序盤の作品が思うように売れず、解散を決意しかけていたMott the Hoopleを救ったのが、当時“ジギー・スターダスト”として絶頂期を迎えていたデヴィッド・ボウイだった。
ボウイはバンドの熱狂的ファンを公言し、自ら彼らのプロデュースを申し出る。
こうして生まれたのが、1972年の「All The Young Dudes」である。
この曲はボウイが書き下ろしたもので、若者の時代を讃えるアンセミックなメッセージと、グラムロックの華やかさが見事に融合していた。
イアン・ハンターの気怠げながらもエネルギッシュなボーカルが、ボウイの作り出す時代感を増幅させ、結果的に全英チャート3位という大ヒットを記録する。
「All The Young Dudes」の成功は、バンドにとって単なるヒット曲誕生以上の意味を持っていた。
それまでのブルージーでやや地味なイメージを一新し、ファッションやステージ・パフォーマンスの面でも華やかなグラムロックの要素を取り入れることで、新たなオーディエンスを獲得したのだ。
同名アルバム『All The Young Dudes』は、バンドにとって大きな転機となり、その後の活動方針を左右するほどの影響をもたらした。
代表曲の解説
All The Young Dudes
言わずと知れたMott the Hoople最大のヒット曲。
デヴィッド・ボウイのグラムロック的感性が注入され、若者特有の閉塞感と熱情が入り混じった青春アンセムとなっている。
イアン・ハンターのボーカルは、希望と諦めの間を行き来するような独特のニュアンスを湛えており、これが楽曲に深みを与えている。
Honaloochie Boogie
次作『Mott』(1973年)からシングルカットされた楽曲で、グラムロックの色合いが濃厚ながらも、キャッチーなメロディが耳に残る一曲。
ギターリフとイアンのボーカルが軽快に絡み合い、当時の英国ロック・チャートでも高い人気を博した。
バンドの持つ“雑多でエネルギッシュ”な魅力が詰まっているナンバーといえるだろう。
All the Way from Memphis
アルバム『Mott』のオープニングを飾るロックンロール調の楽曲。
ミック・ラルフスのギターとイアン・ハンターの歌声が軽妙な掛け合いを見せ、聴き手を冒険心で満ちたロードムービーへと誘うような雰囲気がある。
ライブでも定番曲として取り上げられ、ファンには特に愛されている。
アルバムごとの進化
Brain Capers(1971年)
グラムロックに傾倒する以前の最後の作品とされる4作目。
荒々しいブルースロックやサイケデリックの名残を感じさせる一方、鬱屈としたエネルギーが滲み出ており、後に花開く“危うい煌めき”の片鱗が見え隠れする。
商業的には苦戦したが、バンドの“無頼漢”的なロック性を知る上では興味深い一枚といえる。
All The Young Dudes(1972年)
ボウイのプロデュースで一気にグラムロック路線へ舵を切った作品。
表題曲だけでなく、ルー・リードの「Sweet Jane」のカバーなども収録され、“地下”から“地上”へと這い出てくるバンドの姿が鮮烈に描き出されている。
イギリスの若者たちの支持を集め、時代の流れに乗る形でバンドは注目度を急上昇させた。
Mott(1973年)
バンドの最高傑作と評されることも多い6作目。
グラムロックの華やかさと、イアン・ハンターが紡ぎ出すメロディアスなソングライティングが高いレベルで融合しており、「All the Way from Memphis」や「Honaloochie Boogie」などの名曲が揃う。
同時に、孤独や混乱をテーマに据えた歌詞が多く、明るさと陰鬱さが同居する独特の世界を構築している。
The Hoople(1974年)
イアン・ハンターが在籍した最後のアルバム(ただし、この後もバンド名義で作品は続いていく)。
「Roll Away the Stone」などの華麗なロックナンバーを収録し、グラムロック期の総決算的な仕上がりとも言える。
しかし、メンバー間の方向性のズレや疲弊が色濃くなり、アルバムリリース後にイアンはバンドを去ってしまう。
メンバーの変遷とその後の展開
バンドの中心的存在となったイアン・ハンターとミック・ラルフスの組み合わせが生む楽曲には、どこか“青春の痛み”を思わせる哀愁が漂っていた。
だが、ヒットと引き換えに内側では緊張感や不和が蓄積していき、やがてミック・ラルフスはバッド・カンパニー結成のために脱退。
さらにイアン・ハンターもソロ活動を始めることで、Mott the Hoopleの黄金期は終焉を迎える。
その後は、残ったメンバーが“British Lions”という名義で活動を続けるなどの試みがあったが、やはりイアンやミックといった主要ソングライターが離れたことで、バンドは徐々に影を潜める形となった。
ただし、イアン・ハンターのソロ作品は根強い人気を保ち、またミック・ラルフスが所属するバッド・カンパニーも大きな成功を収めるなど、彼らの才能は別の形で開花していった。
後世への影響と再評価
Mott the Hoopleが放ったグラムロック的な煌めきや、イアン・ハンターの文学的な歌詞世界は、後のパンク・ニューウェーブ世代にも影響を与えた。
特にイギー・ポップやクイーンのフレディ・マーキュリーは、インタビューで「Mott the Hoopleにインスピレーションを得た」と語っており、後続のアーティストにとっても大きな存在だったことがうかがえる。
1970年代後半から1980年代にかけて、バンドの名は一時的に忘れられかけたが、グラムロック再評価の波とともに再び脚光を浴びるようになる。
2000年代以降は再結成ライブが何度か行われ、往年のファンだけでなく若い世代にも歓迎された。
「All The Young Dudes」はロック・アンセムとして映画やドラマのサウンドトラックでもしばしば取り上げられ、時代を超えてリスナーの胸を打ち続けている。
まとめ
Mott the Hoopleは、イギリス特有の憂いや反骨精神を抱えたロックバンドとして、1970年代初頭に強烈な足跡を残した。
デヴィッド・ボウイとの共闘による「All The Young Dudes」の大ヒットが有名だが、そこに至るまでのブルース/R&B色の強い作品や、グラムロック期に映し出されたきらびやかさと哀愁の同居は、バンドを“単なる一発屋”では済ませない奥行きを持たせている。
メンバーそれぞれが歩んだ道は多岐にわたるものの、イアン・ハンターのハスキーな歌声とミック・ラルフスのギターが紡いだ“荒涼としたロックの詩情”は、今もなお色褪せることなく心に残る。
その儚い魅力は、青春の喪失感を抱きつつも疾走していく若者の姿を象徴しているかのようだ。
もしMott the Hoopleの真髄を味わうなら、まずは「All The Young Dudes」とアルバム『Mott』を聴いてみるのがよいだろう。
華やかなグラムの衣をまといながらも、どこか影を引きずったロックの燃え上がる瞬間がそこにはある。
一度そのサウンドの中に飛び込めば、時代の波間に消えそうで消えない“危うい煌めき”をリアルに感じ取ることができるはずだ。




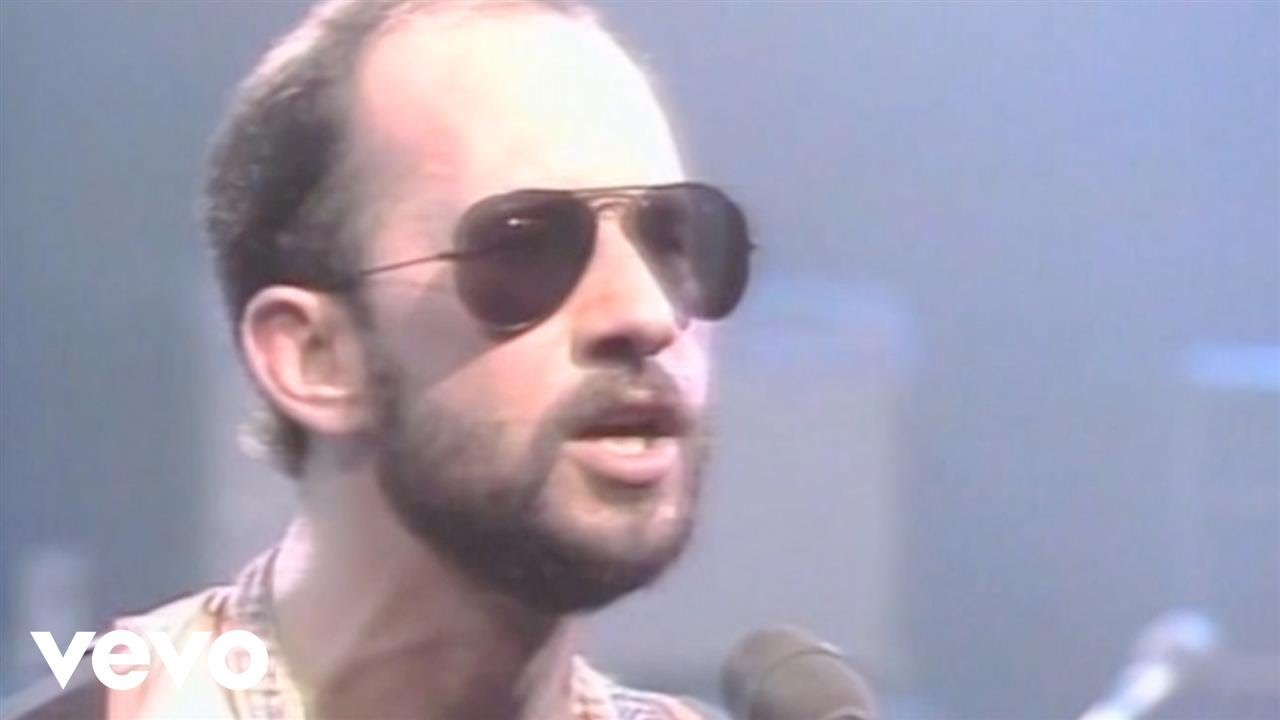
コメント