
発売日: 1988年10月18日
ジャンル: シンセポップ、ハウス、ダンスロック、アートポップ
バブルの向こうで——ポップスターが試みた“沈黙とダンス”の再構築
Big Thingは、Duran Duranにとって6作目となるスタジオ・アルバム。
前作Notoriousでファンク色へと舵を切った彼らが、さらにその先へ踏み込んだ、実験と変容の記録である。
80年代後半の音楽潮流——ハウスミュージックの台頭、エレクトロニック・サウンドの深化、MTV以後のポップの過渡期——それらを大胆に取り入れながら、Duran Duranは“ポップアイドル”としての自らを一度解体し、新たなサウンドアートのかたちを模索していた。
このアルバムには、華やかなスタジアムポップやエキセントリックなニューウェーブの影は少ない。
代わりにあるのは、機械的でミニマルなグルーヴ、内省的なリリック、そしてダンスフロアに潜む孤独感である。
それはまさに、“Big Thing(大きなもの)”というタイトルに反して、静かに心を侵食する“小さな問い”の連なりなのだ。
全曲レビュー
1. Big Thing
タイトル曲は、インダストリアル的なビートと不穏なシンセが交差するイントロダクション。
ロボティックなヴォーカルが、“大きなもの”の空虚さを皮肉るように響く。
2. I Don’t Want Your Love
ハウス的なビートとアシッドなシンセが際立つ先行シングル。
冷たく拒絶するようなサビが、クラブサウンドと感情の乖離を象徴する。
3. All She Wants Is
この時期のDuran Duranの代表的トラック。
リズムの反復とヴォイス・サンプルの連打が、90年代テクノの萌芽を感じさせる異色作。
4. Too Late Marlene
60年代ポップスの香りを持つバラード。
甘美で懐かしい旋律の裏に、時代への郷愁がにじむ。
5. Drug (It’s Just a State of Mind)
アグレッシブなビートと実験的エレクトロが交差する、サイケデリックなダンスナンバー。
“ドラッグは状態にすぎない”という主張が、感覚の拡張と冷笑を同時に奏でる。
6. Do You Believe in Shame?
穏やかなメロディとストリングスが美しいバラード。
故友アンディ・ウォーウィックに捧げられた、喪失と赦しの詩。
7. Palomino
アートポップ的な浮遊感を持つトラック。
“パロミノ=黄金の馬”をモチーフに、夢と逃避を描く詩的世界が展開する。
8. Interlude One
実験的な短いインストゥルメンタル。
ミニマリズムとコラージュ感覚がアルバムの流れを途切れさせずに繋ぐ。
9. Land
スケールの大きなシンセポップ。
理想郷“ランド”への渇望と、それが崩れていく風景を幻想的に描いている。
10. Flute Interlude
フルートを用いた短い音響作品。
アルバム後半の内省性をさらに強調するような繊細な瞬間。
11. The Edge of America
静謐なイントロと、アメリカという存在の“縁”を旅するような抒情的ロック。
政治と個人の間に生まれる“ずれ”を浮かび上がらせる。
12. Lake Shore Driving
アルバムを締めくくるインストゥルメンタル・ロック。
ギターとビートが滑走するように疾走し、“都会”という風景を映し出す。
総評
Big Thingは、Duran Duranが“80年代の寵児”としてのイメージを脱却し、音楽的自我を再構築しようとするプロセスの中で生まれた実験的な傑作である。
ここには煌びやかなカメラフラッシュも、スタジアムを沸かせるアンセムもない。
だがその代わりに、時代の終わりと次の時代の始まりを鋭く察知する視線と、静かに跳ね返すビートが存在している。
この作品は、商業的にはRioやSeven and the Ragged Tigerほどの成功を収めなかったかもしれない。
しかし音楽的には、後のエレクトロニカやブリットポップ以降のアートロックの予兆を感じさせる、Duran Duranの真の実験精神が息づいたアルバムなのだ。
おすすめアルバム
-
Spirit of Eden by Talk Talk
——静寂と実験が交錯するアートポップの金字塔。 -
Technique by New Order
——ハウスとロックの融合点を示した1989年の名作。 -
Violator by Depeche Mode
——機械と感情の境界線で揺れる、ダークなエレクトロポップ。 -
Low-Life by New Order
——ダンスと内省のバランスが、Big Thingと共鳴する。 -
So Red the Rose by Arcadia
——Duran Duranの別ユニットによる、耽美で実験的なサウンド。


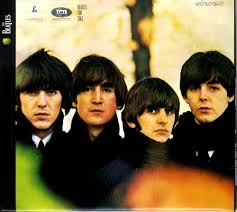
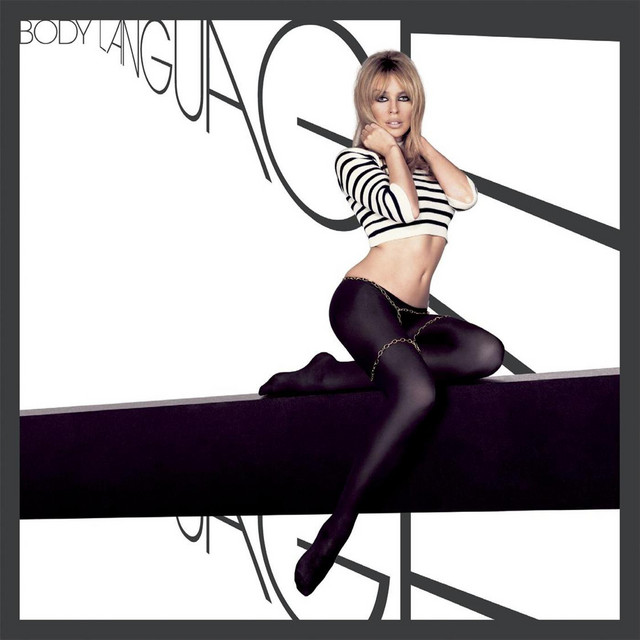
コメント