
1. 歌詞の概要
「Script for a Jester’s Tear」は、イギリスのプログレッシブ・ロック・バンド、マリリオンの記念すべきデビュー・アルバム『Script for a Jester’s Tear』のオープニングを飾る楽曲であり、同時にバンドの音楽性と詩的世界観を象徴する存在でもある。この曲は、フィッシュ(Fish)による深い感情表現、文学的な歌詞、そして複雑で劇的な音楽構成を通して、失恋、喪失、孤独、芸術家の苦悩を多層的に描いている。
歌詞は、恋人に去られた語り手の視点から語られ、喪失感と怒り、そして芸術家としての自己表現の葛藤が交錯している。タイトルにある「ジェスター(道化師)」は、愛に傷つきながらも、それを舞台の上で演じる“アーティストの象徴”であり、フィッシュ自身の投影でもある。「私はただの一編の戯曲だったのか?君のための一時の幻想だったのか?」という痛切な問いかけの中に、恋愛の儚さと、表現者としての存在の危うさが宿っている。
この楽曲は、単なる失恋の物語ではなく、自己喪失と芸術の誕生という二重構造のドラマとして展開し、リスナーに強烈な心理的インパクトを与える内容となっている。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Script for a Jester’s Tear」は、1983年にマリリオンが発表したデビュー作の冒頭曲であり、バンドのリーダーであるフィッシュがソングライターとしての才能を世に知らしめた作品である。フィッシュは、ピーター・ガブリエル時代のジェネシスに大きな影響を受けたことで知られているが、この楽曲では、より私的かつ演劇的なアプローチを通して、プログレッシブ・ロックに新たな情念を注入している。
彼はこの曲について、「これは、実際の失恋から始まり、そこから生まれる演劇性を自己認識として構築していった詩だ」と語っており、自分の感情の断片を“道化師”というキャラクターに昇華させることで、単なる自己吐露を越えた普遍的な物語へと変換している。
また、マリリオンは当時、“プログレッシブ・ロックの再興”として期待されていたバンドであり、この曲はその期待に応えるだけでなく、80年代以降のプログレの方向性を再定義する試金石ともなった。ピアノ、シンセ、ギター、リズムが複雑に絡み合う構成は、バンドの演奏力の高さを証明し、クラシカルなプログレ要素を維持しながらも、より感情的なアプローチを提示している。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、「Script for a Jester’s Tear」の印象的なフレーズを抜粋し、和訳とともに紹介します(出典:Genius Lyrics)。
“So here I am once more / In the playground of the broken hearts”
「そしてまたここにいる / 壊れた心たちの遊び場で」
“I’m losing on the swings / I’m losing on the roundabouts”
「ブランコでも、回転木馬でも負けてばかりだ」
“A script for a jester’s tear”
「道化師の涙のための台本」
(愛に傷ついた魂が、その痛みを演劇として表現する)
“Can you still say you love me?”
「それでも君は、まだ僕を愛していると言えるのか?」
“And I never did write that love song / The words just never seemed to flow”
「結局あのラブソングは書けなかった / 言葉がうまく流れてこなかったんだ」
“The fool escaped from paradise / Will look over his shoulder and cry”
「楽園から逃げ出した道化師は / 振り返って涙を流すだろう」
これらのフレーズは、恋愛の終焉と芸術の苦悩を同時に抱えた語り手の心理を、劇的かつ詩的に表現している。
4. 歌詞の考察
「Script for a Jester’s Tear」の歌詞には、愛と芸術の境界線があえて曖昧に描かれている。語り手は、恋人を失ったことによる喪失感を正面から受け止めながら、それを自らの“創作の原動力”として舞台上に表現する。しかしその過程で、彼は自分自身が“ジェスター=道化師”というキャラクターに飲み込まれ、本来の自己を見失っていく。
「台本(script)」というキーワードは、芸術における演出と現実の感情とのせめぎ合いを象徴しており、自分の人生が“誰かのための悲劇”になってしまったという虚無感すら漂う。また、「書けなかったラブソング」や「ブランコと回転木馬での敗北」といった比喩は、恋愛と自己表現の不全を象徴しており、感情の出口を失った人間の苦悩が深く描かれている。
そして、何よりこの歌の核心には、“痛みを演じることでしか癒せない魂”というフィッシュ独特の文学的視点が息づいている。彼にとって芸術とは、自己救済であり、同時に呪縛でもある。
この楽曲がリスナーにとって強烈な印象を残すのは、その矛盾を真正面から描き出しているからに他ならない。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- “The Cinema Show” by Genesis
幻想と現実が交錯するジェネシスの代表曲。フィッシュの影響源でもある。 - “Fugazi” by Marillion
精神的崩壊と芸術の葛藤をさらに深化させた、マリリオンのドラマティックな名曲。 - “The Great Gig in the Sky” by Pink Floyd
感情の極限を音楽として表現したバラード。無言で語る“叫び”が「Script…」と呼応。 - “Chelsea Monday” by Marillion
同アルバム収録の哀愁漂う楽曲。夢と現実の境界に佇む青春の姿。 - “Grendel” by Marillion
神話と文学的世界観が融合した初期マリリオンの大作。劇的構成を好む人におすすめ。
6. プログレッシブ・ロックの再定義:80年代に蘇った“叙情と演劇”
「Script for a Jester’s Tear」は、80年代というシンセ・ポップやニューウェーブが主流の時代に、70年代の叙情的なプログレッシブ・ロックの精神を継承しながら、新たな世代に向けて再定義した重要な作品である。特に、マリリオンはジェネシスやピンク・フロイドの精神性を受け継ぎつつ、より感情的でドラマティックな表現へと昇華させたバンドであり、その方向性がもっとも鮮明に打ち出されたのが本楽曲である。
さらに、歌詞における“道化師”というキャラクターは、現代におけるアーティスト、あるいは感受性の高い人間のメタファーとして機能しており、表現することと傷つくことの等価性を鋭く問いかけている。
それゆえこの曲は、時代やジャンルを超えて、すべての“何かを創る者”の魂に深く訴えかけてくるのである。
マリリオンの「Script for a Jester’s Tear」は、芸術と感情、恋と喪失、演技と現実が交差する、極めて文学的なロック叙事詩である。傷ついた心を“台本”に変え、涙を“道化”として演じるこの曲は、聴く者の内面に深く入り込み、未だに解けない“感情の迷宮”へと誘う。
そして、そこにある問い――「君のために僕は、ただの一幕の戯曲だったのか?」――その響きは、今なお多くの人の心に共鳴し続けている。


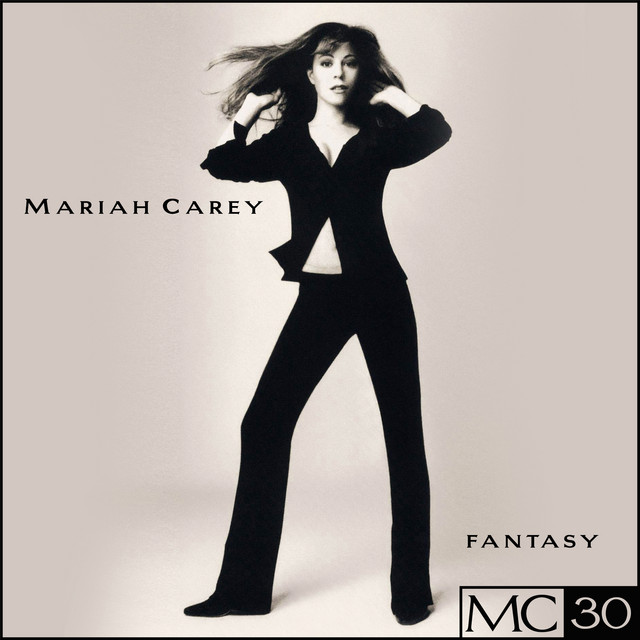
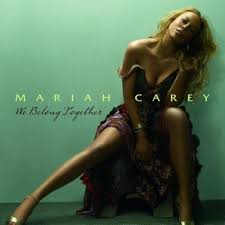
コメント