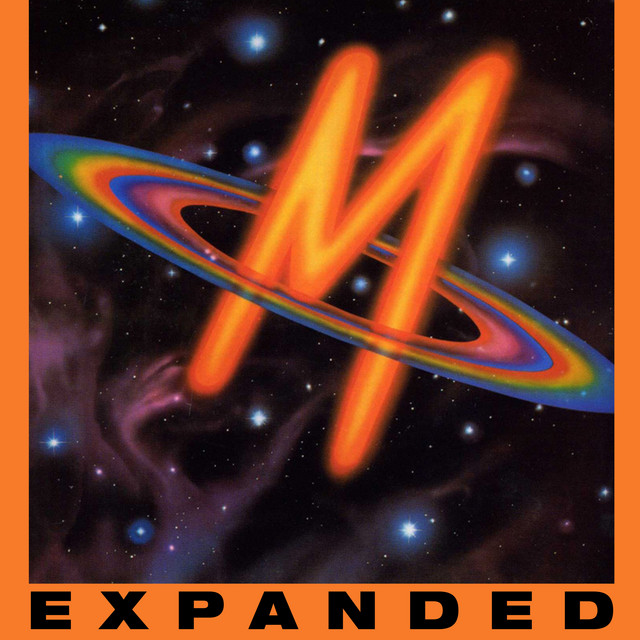
1. 歌詞の概要
「That’s the Way the Money Goes」は、Robin Scott のプロジェクト M による1980年のアルバム『The Official Secrets Act』に収録された一曲で、同アルバムの中でもとりわけ経済システムと個人の関係に焦点を当てた、シニカルかつ批評的なポップソングです。
タイトルの「That’s the Way the Money Goes(それが金の流れる仕組みさ)」というフレーズは、もともと英国の童謡「Pop Goes the Weasel」の一節から引用されたもの。Mはこの古典的な言葉遊びを用いながら、資本主義社会におけるお金の循環と、その中で翻弄される人々の姿を描き出しています。
繰り返されるリズムと抑制されたエレクトロポップのサウンドの上で、スコットは“お金がどう動き、誰に集まり、誰がそれを失うのか”を皮肉まじりに語り続けます。「労働と報酬」「階級と搾取」「欲望と消費」というテーマが、ポップな形式の中で静かに、しかし確かに響きます。
2. 歌詞のバックグラウンド
1979年から80年にかけてのイギリスは、サッチャー政権が発足した直後で、緊縮財政や民営化政策が本格化し始めた時代でした。その中で、格差の拡大や失業率の上昇、労働者階級の不満が社会全体に渦巻いており、Mはそうした背景を鋭敏に捉え、この曲に込めています。
Robin Scottはアートスクール出身の知識人であり、単なるエンターテインメントとしての音楽ではなく、ポップというフォーマットを用いて社会的・政治的メッセージを発信するというコンセプトのもと、アルバム『The Official Secrets Act』を制作しました。その中でも「That’s the Way the Money Goes」は特に、日常の中に潜む資本の論理と、その不条理さをシンプルな言葉で浮き彫りにした楽曲です。
音楽的には、機械的なベースライン、繰り返しの多いシンセサイザーのモチーフ、非感情的なボーカルという構造で、無機質な経済の流れと、人間の主体性の喪失を巧みに表現しています。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、「That’s the Way the Money Goes」の象徴的な歌詞の一節を抜粋し、日本語訳を添えて紹介します。
引用元:Genius Lyrics – M “That’s the Way the Money Goes”
That’s the way the money goes / Down the drain and out the nose
それが金の流れる仕組みさ
排水口を通って、鼻血のように消えていく
Work all day and sleep all night / Still can’t keep my pockets tight
一日中働いて、夜は眠る
それでもポケットの中はスカスカさ
Buy the dream and sell the soul / That’s the way the money rolls
夢を買って、魂を売る
それが金の回るやり方ってもんさ
Round and round the system spins / Watch it chew and spit you in
システムはぐるぐる回る
お前を噛み砕いて、飲み込むのさ
このように、言葉はシンプルでありながらも、現代社会の経済システムにおける労働者の無力感と、消費者としての同一化が強く描かれています。“買うこと”が“生きること”にすり替えられ、“魂”までもが資本の中に取り込まれていくというポップ・ミュージックには珍しい、資本主義批判のトーンが全編を貫いています。
4. 歌詞の考察
「That’s the Way the Money Goes」は、メロディとリズムの面では耳障りのよいポップソングでありながら、その歌詞の内容はきわめてアイロニカルかつ思想的です。何より印象的なのは、その冷笑的なユーモアと、語り手の諦めを含んだ口調です。
「働けども金は貯まらず」「夢を買うために魂を売る」「システムに飲み込まれていく」というモチーフは、まるでジョージ・オーウェルのディストピア小説や、テリー・ギリアムの『Brazil』のような近未来的な風刺世界を想起させます。
また、歌詞の繰り返しとリズム構造は、楽曲自体が“経済のループ”の象徴として機能する構造的メタファーとなっており、聴き手はそのビートに乗りながら、知らず知らずのうちに「金に踊らされる側」に立たされているような錯覚を覚えます。これはまさに、Robin Scottの“ポップでありながら批評的である”というMの美学の核心です。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- “Opportunities (Let’s Make Lots of Money)” by Pet Shop Boys
資本主義的野心とその虚しさを、皮肉な視点から描いたシンセポップの名曲。 - “Money” by Pink Floyd
サウンド・エフェクトと実験的構成で“金”の支配性を批判したロックの金字塔。 - “She’s in Parties” by Bauhaus
メディアと名声、消費される存在について描くゴシック・ニューウェイヴ。 - “Shopping” by Pet Shop Boys
消費社会と経済のゲーム性をテーマにした知的ポップ。
6. “音楽のかたちをした経済批評”としての野心作
「That’s the Way the Money Goes」は、Mというプロジェクトが単なるポップ・アクトではなく、現代社会を見つめ直すための“音楽というメディア”の実験体だったことを明確に示す作品です。そこには、踊ること、楽しむこと、そして“気づかないふり”をすることの背後にある政治性と社会構造への鋭い洞察が宿っています。
とりわけ印象的なのは、このようなメッセージをあえてポップな形式で包み込んでいることです。耳障りが良く、口ずさめるフレーズに込められた皮肉と批評性は、まさに1980年という転換期における「ポップの可能性」と「限界」を同時に描き出していたと言えるでしょう。
「That’s the Way the Money Goes」は、現代社会の“金の流れ”と“人の価値”を、淡々としたリズムと簡潔な言葉で切り取った、音楽による資本主義批評のミニマル・アートです。楽しさの中に鋭さを、リズムの中に諦念を、そしてポップの中に哲学を――そんなMの真骨頂が、ここに詰まっています。


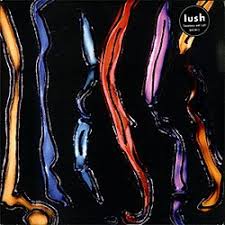
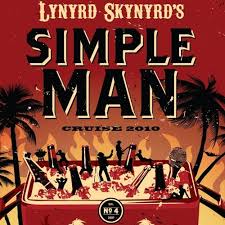
コメント