
発売日: 2020年1月17日
ジャンル: シンセ・ポップ、エレクトロ・ポップ、ニューウェーブ
80年代ポップの影を纏い、恋と現実を踊り直す——of Montrealの“最も直接的な愛のアルバム”
『UR FUN』は、of Montrealが2020年に発表した16枚目のスタジオ・アルバムであり、80年代のシンセ・ポップ/ニューウェーブの美学を全面的に取り入れた、最もストレートでパーソナルな作品である。
タイトルの「UR FUN(You Are Fun)」は、恋人に向けた甘いフレーズのようでいて、その裏にある切実な依存、自己肯定への渇望、そして関係の儚さを仄めかしてもいる。
本作の制作時、ケヴィン・バーンズは現在のパートナーと出会い、明確に“新しい愛”をテーマに据えて楽曲を書き上げている。だが、その語り口は決して楽天的ではなく、喜びと不安、ロマンスと逃避が絶えず交差する構造になっているのが特徴だ。
音楽的には、Orchestral Manoeuvres in the Dark、Yazoo、Eurythmicsといった80sシンセ・ポップの直系。シンプルな電子リズムと甘美なメロディに、バーンズの文学的で多層的な歌詞が絡むという、甘さと痛みのバランスが際立つ作品である。
全曲レビュー
1. Peace to All Freaks
“すべての変わり者たちに平和を”というメッセージで幕を開ける、愛と解放のアンセム。シンセのリフが80s風の高揚感をもたらす。
2. Polyaneurism
“ポリアモリー”と“アナーキズム”を掛けた造語。恋愛関係の柔軟性と苦しみを、軽快なメロディに乗せて語るトリッキーな一曲。
3. Get God’s Attention by Being an Atheist
皮肉と信仰、孤独と自己主張が交差する挑発的なナンバー。タイトルだけでもof Montrealらしさが炸裂している。
4. Gypsy That Remains
恋人との結びつきを儚く描いた、エレクトロ・バラード。メロディの美しさが際立つ、アルバム内でもっともセンチメンタルな楽曲。
5. You’ve Had Me Everywhere
まるで旅の記録のような愛の告白。地理的な動きと感情の変化を重ね合わせる、ロマンティックなエレポップ。
6. Carmillas of Love
タイトルは『カーミラ』に由来。吸血鬼的な愛の中毒性と、束縛的な恋愛への耽溺をテーマにしたダーク・ポップ。
7. Don’t Let Me Die in America
政治的色彩が強い楽曲。恋愛と国家、自由と不安が交錯する。タイトルの切実さはそのままバーンズの生への問いかけでもある。
8. St. Sebastian
苦悩と快楽の象徴としての“聖セバスチャン”を引き合いに、受難的な恋愛を描く。神聖さと欲望の同居がテーマ。
9. Deliberate Self-harm Ha Ha
自己破壊的な衝動を皮肉と笑いで包む、ダークでポップなトラック。重いテーマを跳ねるようなビートで消化するセンスが際立つ。
10. 20th Century Schizofriendic Revengoid-man
アルバムのクロージングは、タイトルからも分かるように混沌とアイロニーが詰まった一曲。自分自身の分裂性を受け入れ、カタルシスへと昇華していく。
総評
『UR FUN』は、of Montrealのキャリアの中でもっともアクセスしやすく、そしてもっとも“現在”のケヴィン・バーンズに近いアルバムである。
恋をテーマにしていながら、単なるラブソング集にはならないのが彼ららしい。愛に没入しながらも、同時にそこにある支配や不安、偶像化への警戒を決して手放さない。
音楽的には80年代のエレクトロ・ポップの純度が高く、どの曲も3〜4分のタイトな構成でまとめられている。そのため、過去のアルバムのような分裂的な構造や難解さがなく、ポップとしての完成度は非常に高い。
その一方で、リリックの中に見え隠れする毒や痛みが、表面的な明るさと絶妙にバランスを取っており、聴くたびに新たな感情の層が現れるような作品でもある。
おすすめアルバム
-
Dare / The Human League
80sシンセ・ポップの代表作。UR FUNの音作りの基礎となる美学を体験できる。 -
Behaviour / Pet Shop Boys
静かな哀愁と電子音のバランスが絶妙な名盤。感情と理性の距離感が共通。 -
Art Angels / Grimes
ジャンルを横断する女性的なエレクトロ・ポップの金字塔。ポップと狂気のバランスが似ている。 -
Color Theory / Soccer Mommy
恋愛と精神のバランスを探る現代的なポップ。UR FUNの内省性に響く。 -
Digital Ash in a Digital Urn / Bright Eyes
アナログな感情をデジタルで表現した名作。エレクトロニクスとエモーションの共存という意味で近い。



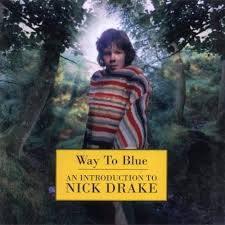
コメント