
発売日: 2014年11月10日
ジャンル: アンビエント、プログレッシブ・ロック、ポストロック
概要
『The Endless River』は、ピンク・フロイドが2014年に発表した通算15作目のスタジオ・アルバムであり、
バンドの“最終章”にして、リック・ライトへの追悼作として制作された。
タイトルが意味する「果てしない川」は、
人生と音楽、記憶と時間の流れを象徴している。
本作の大部分は、1993〜94年に『The Division Bell』のレコーディング中に録音されたセッション音源を再構築したものであり、
デヴィッド・ギルモアとニック・メイスンが中心となって仕上げた。
ギルモアは「これはリックへのラブレターだ」と語っており、
その言葉通り、本作にはライトの鍵盤が全編にわたって息づいている。
彼の温かなコード、アンビエントなハーモニー、静かな間。
それらがまるで“記憶の中のピンク・フロイド”を再生するように響く。
歌詞のある楽曲はわずか一曲。
大半はインストゥルメンタルで構成され、
“沈黙と響きの間にあるもの”を描く――それが『The Endless River』の本質である。
全曲レビュー
Disc 1:Side 1(Things Left Unsaid / It’s What We Do / Ebb and Flow)
冒頭「Things Left Unsaid(言えなかったこと)」のタイトルからして象徴的だ。
静寂の中に立ち上がるライトのオルガン、ギルモアのギターが、
まるで“言葉にならない会話”のように絡み合う。
「It’s What We Do」では、『Wish You Were Here』期を彷彿とさせるアナログ・シンセとギターの掛け合い。
「Ebb and Flow」は波打つ音の中で、記憶が遠ざかっていくような余韻を残す。
まさにタイトル通り、“潮の満ち引き”のようなイントロダクションである。
Side 2(Sum / Skins / Unsung / Anisina)
「Sum」は、70年代後期の壮大なアンサンブルを思わせる構築的インスト。
ギルモアのギターがドラマチックに旋回し、
“宇宙空間を旅するピンク・フロイド”を現代的に再現している。
続く「Skins」はニック・メイスンのドラミングを主軸にした実験的トラックで、
原初的なリズムと現代的アンビエントの融合が試みられている。
「Unsung」はリック・ライトの繊細なピアノの断片が浮かぶ静謐な曲。
そして「Anisina」ではギルモアがライトを想起させるメロディを奏でる。
東欧的な旋律を帯びたサックスとピアノが、まるで追悼の儀式のように美しい。
曲名“Anisina”はギリシャ語で“永遠の記憶”を意味するとも言われる。
Side 3(The Lost Art of Conversation / On Noodle Street / Night Light / Allons-y Parts 1 & 2 / Autumn ’68 / Talkin’ Hawkin’)
「The Lost Art of Conversation」――“失われた会話の芸術”。
『The Division Bell』のテーマを引き継ぐ曲名であり、
言葉ではなく音で対話するバンドの姿勢を象徴している。
「On Noodle Street」は、ライトの鍵盤が滑らかに流れる軽快なジャズ・グルーヴ。
続く「Allons-y (Part 1 & 2)」はアップテンポなギター主導のインストゥルメンタルで、
かつての『Run Like Hell』を想起させる疾走感を持つ。
「Autumn ’68」は1969年にアビイ・ロードで録音されたライトの未発表オルガン演奏を使用。
過去と現在が交錯する瞬間であり、まるで“時間が輪を描く”ように音が響く。
「Talkin’ Hawkin’」では再びスティーヴン・ホーキング博士の声が登場。
“話し続けよう”という言葉が、人間の理解への希望を静かに訴える。
Side 4(Calling / Eyes to Pearls / Surfacing / Louder Than Words)
「Calling」は、宇宙的なスケールで展開する瞑想的トラック。
シンセとギターが地平線のように広がり、アルバムの終盤への導入を担う。
「Eyes to Pearls」では低音のうねりとスライド・ギターが絡み、
“暗闇の中で真珠を探す”ような幻想的な響きを生む。
「Surfacing」は希望を感じさせる穏やかな楽曲。
タイトル通り、水面に顔を出し、再び呼吸する瞬間を描く。
そして、最後の「Louder Than Words」は唯一の歌入り曲であり、
『The Division Bell』で描かれた“言葉の限界”を超える、最終的な結論を提示する。
“私たちは対立しながらも、音楽ではひとつになれる”――
その歌詞はピンク・フロイドという存在の核心を突いている。
ギルモアのギター・ソロが、言葉を超えた場所で涙のように響く。
総評
『The Endless River』は、ピンク・フロイドの静かな終焉であり、
同時に“永遠の再生”を象徴するアルバムである。
ウォーターズが関与しないギルモア=ライト=メイスン体制の最終到達点であり、
言葉よりも“音の呼吸”によって語られる。
その音楽はプログレッシブ・ロックの枠を超え、
もはやアンビエント詩曲と呼ぶべき境地にある。
本作には怒りも悲しみもない。
あるのは“受容”と“記憶”。
“音が消えた後も音楽は流れ続ける”という哲学が、
タイトル『The Endless River』そのものに宿っている。
ギルモアのギターは、70年代の荒々しさではなく、
歳月を重ねた深い響きを持つ。
ライトのシンセは霧のように全体を包み込み、
メイスンのドラムは最小限の呼吸で空間を支える。
それらが一体となって、時間の向こう側に流れる音の記憶を再生する。
“終わり”を示すことなく、“永遠の流れ”の中に身を置く。
それがピンク・フロイドの最終的な美学なのだ。
おすすめアルバム(5枚)
- The Division Bell / Pink Floyd
直接の前作であり、本作の素材の多くがここから派生している。 - Wish You Were Here / Pink Floyd
“喪失と記憶”というテーマの源泉。 - Ambient 1: Music for Airports / Brian Eno
アンビエント音楽の原点として比較的文脈で聴ける作品。 - On an Island / David Gilmour
本作の情緒をそのまま引き継いだギルモアのソロアルバム。 - Talk Talk / Spirit of Eden
静寂と音の間にある“祈り”を描いた作品。共鳴する美学を持つ。
制作の裏側
『The Endless River』の録音は、
1993〜94年の『The Division Bell』セッション音源をベースに、
2013年から新たにギルモアとメイスンが加筆・編集を行った。
プロデューサーにはフィル・マニザン、ユース、アンディ・ジャクソンらが参加。
ギルモアは、ライトの残した録音を“彼と再び演奏しているようだった”と語っており、
制作過程そのものが友情と追憶の儀式であった。
また、リック・ライトの家族が許可を与えたことで、
未発表フレーズの多くが正式に使用された。
歌詞の深読みと文化的背景
2010年代初頭、世界はデジタル化と孤立が進み、
“つながりながら断絶している”という矛盾を抱えていた。
『The Endless River』は、そのような時代における沈黙のコミュニケーションをテーマにしている。
“言葉を超えた理解”“時間を越える記憶”“死後の共鳴”――
これらはすべて、リック・ライトという存在を通じて語られている。
最後の「Louder Than Words」でギルモアが歌う、
“私たちのすることは言葉より雄弁だ”という一節は、
ピンク・フロイドの半世紀にわたる活動の結論そのものだ。
ビジュアルとアートワーク
ヒプノシスの流れを汲むストーム・ソーガソンのチームによるアートワークは、
“雲海の上をボートで進む男”という幻想的なビジュアル。
これは“現実と記憶のあいだを旅する魂”を象徴している。
光と空、そして水――ピンク・フロイドの象徴的モチーフがすべて揃い、
最終作にふさわしい荘厳さと静謐さを兼ね備えている。
『The Endless River』は、ピンク・フロイドという旅の“余韻”であり、
終わりなき音の流れそのものである。
静かながら、これ以上に完璧な幕引きは存在しない。
音は止んでも、川は流れ続けている――永遠に。



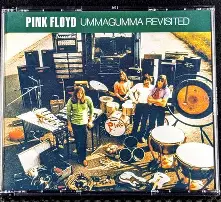
コメント