
発売日: 1984年9月27日
ジャンル: インディーポップ、ポストパンク、ニューウェイヴ
概要
『Spring Hill Fair』は、The Go-Betweensが1984年に発表した3作目のスタジオ・アルバムであり、バンドが“メジャー感”と“実験性”の狭間でもがきながらも、確実に進化を遂げた過渡的作品である。
前作『Before Hollywood』でポップと詩性のバランスを確立した彼らは、本作でさらに洗練されたアレンジとより多彩な楽器編成、そしてより大胆なプロダクションに挑戦している。
レコーディングはフランス南部のスタジオで行われ、プロデューサーはジョン・ブランド(Orange JuiceやAztec Cameraも手がけた人物)が務めた。
そのため、サウンドには洗練されたヨーロピアン・ポップの風合いと、80年代中期のポストパンク〜ニューウェイヴ的な音の広がりが強く現れている。
タイトルの「Spring Hill Fair」は、ブリスベンのローカルなお祭りを指しており、身近な記憶とノスタルジーを、普遍的な音楽体験へと昇華するというGo-Betweensらしい視点が通底している。
本作では新たにドラマーとしてロバート・ヴァン・バイクが正式加入し、バンドのアンサンブルがよりタイトになっているのも特筆点である。
全曲レビュー
1. Bachelor Kisses
マクレナン作の美しいポップソングにして、本作のリードシングル。
“キスだけの恋”というセンチメンタルなテーマが、彼の優しいメロディと繊細な歌唱で昇華されている。
ストリングス風のシンセとソフトなリズムが、アルバムの“メジャー化”を象徴する一曲。
2. Five Words
フォースターによるユーモラスかつ風刺的なナンバー。
“たった5つの言葉が、すべてを変えてしまう”というリリックが、不穏と愛嬌の間で揺れる。
ギターのリフが曲全体を牽引する構造。
3. The Old Way Out
不安定なコード進行と流れるようなギターが印象的な曲。
“昔ながらの抜け道”というタイトルが示すように、逃避と過去への回帰がテーマ。
短いながらも、余韻の残るポストパンク的名曲。
4. Spring Rain (デモ原型)
※『Spring Hill Fair』には収録されていないが、後年の名曲「Spring Rain」の萌芽はこの時期に確認されている。
季節と感情をリンクさせる彼らの表現力が芽生えつつある段階。
5. River of Money
タイトル通り、資本と流通をテーマにした社会批評的な楽曲。
鋭いギターとリズムの反復が、現代生活の機械的な側面を浮かび上がらせる。
知的でありながら躍動感がある、Go-Betweensらしいバランス感覚。
6. Unkind and Unwise
柔らかいメロディの裏に、鋭い批評性が込められたマクレナンの曲。
“優しくないし、賢くもない”というタイトルの皮肉が、恋愛と人間関係の複雑さを炙り出す。
7. Man O’Sand to Girl O’Sea
フォースターによる最高傑作の一つとの呼び声も高いナンバー。
荒々しいギターと流れるようなリズムの中に、恋愛の不条理と詩的な暴力性が同居する。
演奏のエネルギーと歌詞の構造が完全に一致した、Go-Betweens屈指の名曲。
8. Part Company
マクレナンによる別れのバラードであり、静かな情熱が流れる珠玉の一曲。
“距離をとろう”という言葉に込められた、愛と痛みの微妙なバランス。
ギターのアルペジオが涙腺を刺激する。
9. Draining the Pool for You
フォースターらしい、鋭い観察眼と冷ややかなアイロニーが光る曲。
プールを空にするという行為が、無意味な労働や支配構造のメタファーとして提示されている。
サビの引っ掛かりが癖になる。
10. This Girl, Black Girl
ゆるやかで牧歌的なアレンジが印象的な、異色のラブソング。
黒髪の彼女=“異国性”への憧憬として描かれ、フォースターの幻想性が際立つ。
11. You’ve Never Lived
アルバムラストにふさわしい、“生きたことがないなら、何も知らない”という哲学的問いを投げかけるナンバー。
静かで荘厳なエンディングが、アルバム全体の余韻を残す。
総評
『Spring Hill Fair』は、The Go-Betweensがアーティストとしての信念とポップシーンにおける役割の両立に本格的に挑んだ作品であり、結果的にその緊張感が“ゆらぎ”として結晶化した一枚である。
『Before Hollywood』の内省的な完成度と比べると、構成はやや散漫に見えるが、その代わりに音楽的レンジと感情の振れ幅は大きく広がっており、バンドとしての可能性が一気に開花している。
この時期のGo-Betweensはまだ“シーンの外側にいる者たち”であり、チャートを意識しつつも妥協しない姿勢が、どの楽曲にもにじんでいる。
詩とポップ、情緒と分析、記憶と観察――そのどれもが完全に混ざらず、しかし不思議な調和を見せるこのアルバムは、未完成の美と前進する勇気を形にした、忘れがたい作品である。
おすすめアルバム(5枚)
-
Orange Juice / Rip It Up (1982)
ポストパンクのポップ化という点で同時代の親近性が高い。 -
The Smiths / Hatful of Hollow (1984)
文学性とメロディ、内省とユーモアのバランスが響き合う。 -
Aztec Camera / Knife (1984)
洗練されたギター・ポップと詩的な歌詞の融合。 -
Lloyd Cole and the Commotions / Easy Pieces (1985)
知的で都会的なポップにおける叙情の極み。 -
The Triffids / Treeless Plain (1983)
同郷バンドによるフォークとポストパンクの交差点。


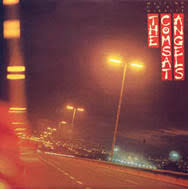
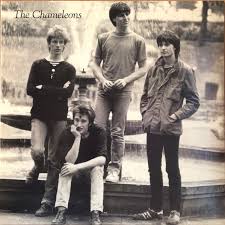
コメント