
発売日: 1993年2月10日
ジャンル: インディー・ロック、オルタナティヴ・ロック、パンク・ロック
2. 概要
『On the Mouth』は、アメリカ・ノースカロライナ州チャペルヒルのインディー・ロック・バンド Superchunk が1993年に発表した3作目のスタジオ・アルバムである。
レーベルは前作と同じく Matador Records。90年代USインディーの中心的存在となる前夜の、きわめて重要なタイミングで世に出た作品である。
録音は1992年9月14日〜20日にかけて、ロサンゼルスの West Beach Studios で行われた。
エンジニアは Donnell Cameron、プロデュースは Rocket from the Crypt/Drive Like Jehu の John Reis とバンド自身。
前作『No Pocky for Kitty』の Steve Albini 録音とはまったく違う環境・布陣で、Superchunk はサウンドをさらに推し進めることになった。
バンドのラインナップとしても転機の一枚である。
本作からドラマーが Chuck “Chunk” Garrison から Jon Wurster に交代し、以後長年続く“黄金編成”がスタートする。
Wurster のタイトで推進力のあるドラミングは、Superchunk のスピード感とメロディアスなソングライティングを、より精密なロック・バンドのグルーヴへと押し上げた。
バンド側の言葉を借りれば、『On the Mouth』制作期の Superchunk は、Rocket from the Crypt、Drive Like Jehu、Polvo などツアー仲間のバンドから多くの影響を受けていたという。
しかし、出来上がったアルバムを聴くと、結局“これは完全に Superchunk のレコードだ”と彼ら自身は語っている。
エモ/ハードコア寄りの緊張感と、パワー・ポップ的なメロディの親しみやすさ、そのどちらもを失わずに統合している点が、この作品の強さである。
音楽的には、前作『No Pocky for Kitty』での“爆裂インディー/パンク”路線を受け継ぎつつ、楽曲の骨格と構成がより緻密に組み上げられている。
オープニングの「Precision Auto」から最後の「The Only Piece That You Get」まで、ほとんど失速する瞬間がない一方で、単に速いだけのパンクには終わらない起伏とダイナミクスがある。
批評的にも、『On the Mouth』は Superchunk のカタログの中で非常に高く評価されている。
Rolling Stone は当時のレビューで、本作を「メジャー化した“オルタナ”に対する、インディー側からの回答」のように位置づけ、“Buzzcocks を思わせるメロディと轟音ギターの組み合わせ”を称賛した。
のちに Stereogum が行ったアルバム・ランキングでも、『On the Mouth』は堂々2位に置かれており、“不安と性急さをメロディに蒸留した、もっともエキサイティングな Superchunk の一作”と評されている。
また、『On the Mouth』は“後続への影響”という点でも大きな意味を持つ。
冒頭曲「Precision Auto」は後に Jimmy Eat World をはじめとするポスト・ハードコア〜エモ勢にカバーされ、Merge Records のコンピでも複数のバンドに取り上げられている。
つまり本作は、90年代初頭のUSインディー・ロックを象徴するだけでなく、その後のエモ/インディー・パンク系バンドが共有する“教科書”としても機能しているのだ。
グランジがチャートとファッション誌の表紙を席巻していた1993年、“次の Nirvana”と目されながらもメジャーを選ばなかった Superchunk。
『On the Mouth』は、彼らがインディーにとどまりながら、同時代のメジャー・オルタナ作品にも匹敵する密度と勢いを手にした瞬間を記録したアルバムなのである。
3. 全曲レビュー
1曲目:Precision Auto
アルバムの幕開け「Precision Auto」は、Superchunk の代表曲のひとつとして名高い。
開始数秒で一気にトップギアに入るような超高速ナンバーで、Jon Wurster のドラムがいきなりアルバム全体のテンポを決定づける。
ギターは2本がユニゾン気味に硬質なリフを刻みつつ、要所でオクターブ・リードが飛び出す構成。
コード自体はシンプルだが、シンコペーションのずらし方とブレイクの入れ方が巧みで、ただ速いだけで終わらない“スリルのある疾走感”を生み出している。
歌詞は、高速道路のファストレーンを舞台に、“追い越すならちゃんと行け、途中で減速するな”というニュアンスのフレーズが繰り返される。
これは単なる交通マナーではなく、時代のスピード感や、青春の焦燥をそのままメタファーにしたようなイメージと言えるだろう。
“ちゃんと走る気がないなら、無理に前に出てくるな”という苛立ちは、90年代初頭のインディーの矜持とも重なって聞こえる。
アルバム全体の“スピード”と“苛立ち”をまとめて提示する、完璧なオープニング・トラックである。
2曲目:From the Curve
「From the Curve」は、「Precision Auto」のストレートな加速に対し、ややひねくれたリズム感とメロディを持つ曲である。
イントロのギターは、拍の裏側にアクセントを置いたカッティングとパワーコードを交互に行き来し、軽くよろめくようなグルーヴを作り出す。
サビに向かうにつれて、メロディはセンチメンタルなラインを描き、Mac McCaughan の細身の声と相まって、一種の“エモ”的高揚を生む。
ここでのコーラスの重ね方は、のちの『Foolish』以降の感情表現の下地になっているようにも聞こえる。
歌詞に登場する“カーブから見える景色”は、直線的な進路から外れた視点=メインストリームのど真ん中ではない立ち位置を暗示しているかのようだ。
高速道路を真っ直ぐ突っ走る「Precision Auto」と、カーブの外側から世界を見る「From the Curve」という、冒頭2曲の対比も面白い。
3曲目:For Tension
「For Tension」は、タイトルどおり“緊張”を主題にしたような曲だ。
序盤からギターはやや不穏なコードを鳴らし、ドラムはタイトな8ビートに小刻みなフィルを挟み込んで、落ち着きのない空気をつくっている。
メロディ自体は比較的メジャー寄りで、サビでは一気に開けた印象になる。
しかしコードの選び方がどこか不安定で、完全なカタルシスには達しない“宙吊り感”が残る。
この“抜けきらなさ”が、アルバム全体の焦燥とよく響き合っている。
歌詞では、関係の軋みや、内面から消えない緊張感が断片的に描かれる。
はっきりとした物語を語るのではなく、単語やイメージで感情の輪郭だけを提示するタイプのリリックで、聴き手の経験に応じた解釈を許す作りになっている。
4曲目:Mower
「Mower」は、インディー・ロック然としたキラーフックを持つ中盤のハイライト。
イントロのギター・リフは、パワーコードと開放弦を組み合わせた、どこか “泣き”を感じさせる流麗なフレーズで、1度聞いただけで耳に残る。
リズムは疾走しながらも若干タメがあり、ベースがメロディの隙間を縫うように動き回ることで、サウンドに立体感が生まれている。
サビではコードがわずかにマイナー寄りに傾き、ボーカルが高めのキーで伸びることで、切実さが増幅される。
“芝刈り機(Mower)”というモチーフは、一見すると日常的で取るに足らないが、その単語を反復することで、何かを根こそぎ刈り取ってしまう行為の暗喩のようにも響く。
関係の終わり、感情の削ぎ落とし、あるいは過ぎ去ってしまう時間の暴力性が、ぼんやりと浮かび上がる曲である。
5曲目:Package Thief
「Package Thief」は、短く鋭いパンク・チューン。
Precision Auto ほどのハイテンポではないが、スネアの連打とギターの刻みが絶えず前のめりで、2分台ながら強い印象を残す。
メロディはメジャーキーを基調としつつ、フレーズの末尾にわずかな陰りを落とすことで、単純な“陽性パンク”で終わらないニュアンスを与えている。
サビのヴォーカル・ラインは、観客が一緒に叫べるような素朴な構造で、ライヴでのアンセム性が強い。
タイトルの“荷物泥棒”は、比喩として読むと、期待や約束を奪ってしまう存在、あるいは自分自身の不安や後悔を象徴しているようにも感じられる。
“軽快なのにどこか切ない”という、Superchunk 独特の感情のブレンドがよく表れた一曲である。
6曲目:Swallow That
アルバム前半のクライマックスとも言えるのが「Swallow That」。
ここではテンポを大きく落とし、ドローン気味のベースと重たいドラムの上に、ギターが長いトーンを引き伸ばす。
Superchunk の定番スタイルからあえて外れた、“ネオ・グランジ”的ともいえるドス黒いサウンドである。
歌メロは意外なほど抑制されており、フレーズを何度も反復することで、着実に緊張を高めていく。
中盤から後半にかけては、ノイズに近いギターのうねりが増量し、曲全体がひとつの大きなうねりになっていく。
“それを飲み込め(Swallow That)”というフレーズは、感情を抑え込むこと、納得がいかない現実を無理やり呑み込むことを示唆しているようにも聞こえる。
“青春パンク”的な外向きのエネルギーとは対照的な、内側に沈んでいく怒りと鬱屈を描いた、実験的かつ重要なトラックだと言える。
7曲目:I Guess I Remembered It Wrong
「I Guess I Remembered It Wrong」は、ギターのアルペジオとポップなメロディが印象的なミドルテンポ曲。
イントロにはアコースティック・ギター的な質感もあり、Rolling Stone が指摘したように、Jam のような UK パンク/モッズからの影響も垣間見える。
歌メロははっきりと“歌もの”志向で、Aメロからサビにかけて自然に高揚していく。
ここではドラムが細かいフィルを抑え、むしろ曲の“歌心”を前に出す役割に徹している。
“記憶違いだったのかもしれない”というタイトルどおり、歌詞は過去の出来事と向き合う視点を持つ。
ただし、詳細なストーリーを語るのではなく、“記憶”それ自体の不確かさや、そこにまとわりつく感情だけを手触りとして残す書き方が、いかにも Mac らしい。
8曲目:New Low
「New Low」は、アルバム中盤に配された、スピードと落ち込みが同時に走るような一曲である。
テンポは速めで、ギターは相変わらず前のめりに鳴り続けるのに、メロディとコード進行が妙にメランコリックで、“新しい底(New Low)”というタイトルがそのまま曲の雰囲気を言い表している。
歌詞は、自己評価の低さや、繰り返してしまう失敗への嫌悪感を思わせる断片で構成されている。
しかし、サウンドは沈みきることなく、むしろテンションを上げて走り抜ける。
感情的には落ち込んでいるのに、身体はなぜか前に進んでしまう――そんな矛盾した状態を音で描いたかのようだ。
9曲目:Untied
「Untied」は、やや長めの構成と、ルーズに始まって徐々に締まっていくダイナミクスが特徴的な曲。
イントロはギターのフレーズがやや自由に動き、ドラムもオープンなフィルで空間を開けている。
そこから徐々にリズムが揃い、サビではタイトなアンサンブルへと収束する。
“ほどかれた(Untied)”というタイトルは、結びつきや拘束からの解放とも、バラバラになってしまった関係とも読み取れる二重の意味を持つ。
音楽的にも、解き放たれたギターの響きと、サビでのまとまりの良さが、その二面性を体現している。
曲終盤にかけては、コーラスが重なりつつ、ギターがオクターブやノイズ的フレーズを挿し込むことで、カタルシスを高めていく。
ライヴでも“伸びていく”タイプの楽曲だろう。
10曲目:The Question Is How Fast
タイトルが示すとおり、「The Question Is How Fast」は“どれくらい速く行けるのか”をテーマにしたような楽曲だ。
リズムは再び高速寄りに戻り、ギターとベースが一体となってひたすら同じ方向へ突き進む。
歌詞では、“問題はどれくらい速いかであって、止まるかどうかではない”という姿勢が感じられる。
ここでの“速さ”は、人生の決断、関係の変化、時代の変容など、さまざまなもののメタファーとして機能しているようだ。
サビのフレーズはシンプルだが、その反復が曲全体のテーマを強く刻印する。
Superchunk の作品全体を見渡しても、“スピード”へのこだわりをこれほど露骨な言葉で示した曲は珍しく、本作のコンセプチュアルな重要曲といえる。
11曲目:Trash Heap
「Trash Heap」は、ややざらついたギターと、ロールの多いドラムが印象的な中速ナンバー。
イントロからコードが細かく変化し、Aメロで一度落ち着いてからサビに向かってせり上がる構成が、アルバム終盤に新たな表情を与えている。
“ゴミの山(Trash Heap)”というタイトルは、過去に積み重ねられた失敗や、どうしようもなくなって捨ててきたものの象徴に見える。
歌詞はそれを直接説明するのではなく、メタファーのまま残しておくことで、聴き手それぞれの“Trash Heap”を投影させる余地を残している。
12曲目:Flawless
「Flawless」は、そのタイトルとは裏腹に、完璧とは程遠い人間の感情を描いたような曲だ。
テンポは速めだが、ギターのフレーズやメロディラインにはどこか不安定さがあり、“欠けていることの魅力”を逆説的に表現しているかのようである。
サビではボーカルが一段と高い音域に達し、若干裏返りぎみの声が、完璧ではないが生々しい叫びとして響く。
ここでも Wurster のドラムが曲全体をしっかりと支え、少々ヨレても走り続けられるバンドの生命力を感じさせる。
13曲目:The Only Piece That You Get
ラストを飾る「The Only Piece That You Get」は、アルバム全体を締めくくるにふさわしい、凝縮度の高いパンク・ポップ・チューンである。
尺は短いが、イントロのギター・リフ、Aメロの駆け抜け方、サビのフック、どれもが的確に配置されている。
“あなたが手にする唯一の断片”というタイトルは、時間・記憶・関係性など、さまざまなものが“完全ではなく一部しか残らない”という感覚を示唆している。
アルバム一枚を聴き終えたリスナーにとって、この作品自体が“90年代インディーのひとつの断片”として残ることを思わせる、象徴的な締めくくりだ。
4. 総評
『On the Mouth』は、Superchunk のキャリアにおいて“第一章の完成点”のような位置づけにある。
デビュー作『Superchunk』と2nd『No Pocky for Kitty』で提示された、パンクの衝動とポップなフックを兼ね備えたサウンドは、本作で明確な形を得る。
まずサウンド面での転換として、ドラマー Jon Wurster の加入が大きい。
彼のドラミングは、単に速く叩くだけではなく、曲ごとのダイナミクスに応じて細かなニュアンスを付与している。
「Precision Auto」「The Question Is How Fast」での疾走感、「Swallow That」での重く引きずるようなグルーヴなど、どの曲も“走り方”が異なる。
この多彩さが、『On the Mouth』を単なるハイテンション・パンクの連続にせず、一枚のアルバムとしての起伏を支えている。
プロダクションの面では、前作の Steve Albini 録音が“生々しく荒々しいライブ感”を強調していたのに対して、本作は John Reis らしいタイトで構造的な音像になっている。
ギターとドラムの分離がよく、各パートの役割がクリアに聞き取れる一方で、全体としてはまとまった“壁”として迫ってくる。
インディー・ロックのアティチュードを保ちながら、メジャー流通作品にも引けを取らないスケールを手にしたサウンドだと言える。
楽曲面でも、『On the Mouth』は Superchunk のソングライティングが飛躍した一枚だ。
「Precision Auto」「Package Thief」「The Question Is How Fast」といった直球パンク寄りの曲に加え、「Mower」「I Guess I Remembered It Wrong」「Untied」のように、メロディの起伏と感情の陰影を重視した曲が増えている。
さらに「Swallow That」のような、テンポを落として音の重さと反復で魅せる長尺曲が、アルバムのレンジを一気に広げている。
同時代のバンドとの比較をすると、その独自性はより鮮明になる。
Nirvana や Pearl Jam がメジャー・フィールドで“オルタナ”の旗手となり、Pavement がローファイとアイロニーを武器にしていたのに対し、Superchunk は“DIYインディーでありながら徹底的にポップ”というポジションを突き詰めていた。
『On the Mouth』は、Hüsker Dü や Buzzcocks の系譜を受け継ぎながら、それを90年代的なスピード感と感情の圧縮に落とし込んだ作品であり、その意味で後のエモ/ポップパンクにも強く影響を与えている。
Rolling Stone は当時のレビューで、“On the Mouth は Nevermind ではないし、そうなろうとしてもいない。むしろ、商業的にオルタナが評価される以前から Superchunk が育んできたサウンドを、洗練し、引き締めたレコードだ”と評した。
これは、まさに本作の本質を突いたコメントだろう。
メジャーの“オルタナ・ブーム”と距離を保ちながら、自分たちのペースで音楽を深めていく――そのスタンスが、このアルバムには刻まれている。
また、のちの評価では『Foolish』が“感情的な最高傑作”として語られることが多いが、その直前に位置する『On the Mouth』は、“攻撃的なインディー・パンクの頂点”として別の意味で頂点に立つ作品だとされることが多い。
Stereogum が Superchunk のアルバムを“ワースト〜ベスト”で並べた企画では、1位『Foolish』に次ぐ2位に本作が置かれており、“昨日から始まってしまった不安を、メロディに蒸留したレコード”という表現が印象的である。
焦燥とスピードが、ここまでポップに響くアルバムはそう多くない。
日本のリスナー視点で見ても、『On the Mouth』はUSインディーの“理想形”として薦めやすい一枚だ。
音はハードだがメロディは非常に掴みやすく、英語詞の抽象性もあって、意味よりも音の勢いとフレーズの耳触りで楽しめる。
そこに少しずつ歌詞の断片が聞こえてくると、“速さに取り憑かれた世代感”や、“うまく行かない対人関係のもどかしさ”がじわじわと立ち上がってくる。
現在あらためて聴くと、プロダクションの派手さや特殊なギミックに頼ることなく、ギター・バンドとしての純粋なエネルギーとソングライティングだけで勝負していることがよく分かる。
その意味で、『On the Mouth』は時代を超えて聴き継がれる“ギター・ロックの教科書”のような存在であり、Superchunk 入門としても、90年代インディー・ロックの基準点としても、非常に有効な一枚なのである。
5. おすすめアルバム(5枚)
- No Pocky for Kitty / Superchunk(1991)
前作にあたる2ndアルバム。
Steve Albini 録音による爆裂サウンドと、「Skip Steps 1 & 3」「Seed Toss」などの名曲群が収録されている。
『On the Mouth』との連続で聴くと、サウンドの変化とソングライティングの成熟がよく分かる。 - Foolish / Superchunk(1994)
『On the Mouth』の次作であり、感情的な深さではバンド屈指の名盤。
恋愛とバンド内の人間関係の崩壊を背景にした歌詞が多く、より“内省的なインディー・ロック”へ踏み込んだ作品である。
『On the Mouth』の外向きの焦燥と、こちらの内向きな痛みを対比すると、バンドの幅の広さが見えてくる。 - Here’s Where the Strings Come In / Superchunk(1995)
Superchunk が“インディーの代表格”としての風格を備え始めた作品。
アレンジの多彩さやテンポ感の幅が広がり、ストリングスや変則リズムも取り入れながらも、根幹のパワー・ポップ性は失われていない。
『On the Mouth』以降の“成熟モード”を確かめたいリスナーにおすすめ。 - Flip Your Wig / Hüsker Dü(1985)
Superchunk の源流にあるとされる、Hüsker Dü のパンク〜パワー・ポップ期の名盤。
速いビートの上にメロディアスなフックを乗せる手法は、『On the Mouth』にも直結している。
USインディー・ロックの歴史的文脈を知るうえで、セットで聴いておきたいアルバムである。 - Crooked Rain, Crooked Rain / Pavement(1994)
同じ90年代USインディーを代表する作品ながら、こちらはローファイ感とシニカルなユーモアに比重を置いたアルバム。
Superchunk との違いを意識しつつ聴くと、同じ“インディー・ロック”でも、サウンドもメンタリティもまったく別の方向へ進んでいたことがよく分かる。
90年代インディーの多面性を体感するうえで、欠かせない一枚だ。
6. 制作の裏側
『On the Mouth』の制作を語るうえで欠かせないのが、録音場所とプロデューサーの組み合わせである。
本作はロサンゼルスの West Beach Studios で録音され、プロデュースを務めたのは、後に Rocket from the Crypt や Drive Like Jehu で知られることになる John Reis とバンド自身だ。
West Beach Studios は、当時のUSパンク/ハードコア周辺バンドがよく利用したスタジオで、タイトかつラウドなギター・サウンドに定評があった。
ここでの録音は、前作の Chicago Recording Company + Steve Albini 体制とはまったく異なる性質の音を Superchunk に与えることになる。
よりドライで、各楽器の分離が良く、ライブ感とスタジオ録音の精度のバランスが取れたサウンドは、『On the Mouth』の“整理された混沌”というキャラクターを形作った。
John Reis は、自身もギタリスト/ソングライターでありながら、このアルバムでは外部プロデューサーとして、曲の構造とダイナミクスに深く関わったとされる。
Rocket from the Crypt や Drive Like Jehu のアグレッシブなギター・サウンドを思い浮かべると、Superchunk のこの時期の音像との共通点も見えてくる。
特に、ギターの歪み方とドラムの抜け方には、“90年代USインディー/ハードコア・スタジオ・サウンド”の美学がはっきり刻まれている。
制作過程の証言からは、Superchunk がこのアルバムの段階で既に“ツアーを重ねながら曲を練り上げ、その勢いのままスタジオに持ち込む”というスタイルを確立していたことが分かる。
そのため、楽曲のアレンジはスタジオでゼロから作るのではなく、ライブでの実戦経験を経たうえで最適解をレコーディングに刻む、という流れになっている。
この“ライヴとスタジオの距離の近さ”が、アルバム全体の“走りながら考えるような”スリルに直結しているのだ。
また、『On the Mouth』は Matador からリリースされた最後のフルアルバムでもあり、その後 Superchunk は自身のレーベル Merge Records へ拠点を移していく。
インディー・レーベルがメジャーと契約を結び始めるなかで、あえて自分たちのレーベルに戻る――という選択は、結果的に Merge をオルタナ/インディーシーン屈指のレーベルへと押し上げることになる。
そういう意味で、『On the Mouth』は音楽的な転換点であると同時に、ビジネス/組織の面でも大きな分岐点に立っていた作品なのである。
9. 後続作品とのつながり
『On the Mouth』の次に位置するのが、1994年の『Foolish』である。
しばしば“Superchunk 史上もっとも心をえぐるアルバム”と評される同作は、メンバー同士の恋愛関係の破綻など、バンド内の緊張が高まった状況のなかで制作された。
その激烈な感情表現は、すでに『On the Mouth』の段階で兆しが見えている。
たとえば「Swallow That」の重苦しいビルドアップや、「I Guess I Remembered It Wrong」の“記憶”をめぐる自省的な視点、「New Low」の自己嫌悪的なトーンなどは、後の『Foolish』に直結するモチーフである。
『On the Mouth』ではまだ、そうした感情が“スピード”と“勢い”によって外向きに吐き出されているが、次作ではそれがより内側に沈み込み、細部まで描写されるようになる。
逆に、Superchunk がその後も長く維持していく“インディー・アンセムメーカー”としての側面は、「Precision Auto」「Package Thief」「The Question Is How Fast」あたりに凝縮されている。
これらの曲に見られる、シンプルなパワーコードと覚えやすいメロディ、そしてわずかなひねくれを加えたリズム処理は、その後の『Here’s Where the Strings Come In』『Indoor Living』などでも、形を変えながら繰り返し現れる。
さらに、『On the Mouth』で確立された Jon Wurster のドラミング・スタイルは、以後30年にわたって Superchunk の“土台”であり続ける。
バンドのサウンドがポップ寄りになろうと、アレンジが複雑になろうと、その中心には常に“走れるドラマー”としての Wurster の存在がある。
その最初の一歩が、『On the Mouth』に刻まれているのだ。
こうした意味で、本作は単に“90年代前半の名盤”というだけでなく、その後の Superchunk の長いキャリアを理解するうえでの、重要なハブとなるアルバムである。
参考文献
- Wikipedia “On the Mouth”(作品の基本情報、録音日程、トラックリスト、ドラマー交代、バンドのコメントなど)monkey.org
- Wikipedia “Superchunk”(バンドの略歴、メンバー構成、レーベル移籍の流れ)
- Rolling Stone / Matt Diehl “Superchunk: On The Mouth”(当時のレビュー、サウンドと同時代性の評価)monkey.org
- Stereogum “Superchunk Albums From Worst To Best”(『On the Mouth』の位置づけと曲の解釈)
- 各種アルバム・データベース/レビューサイト(リリース情報、評価の概略確認)



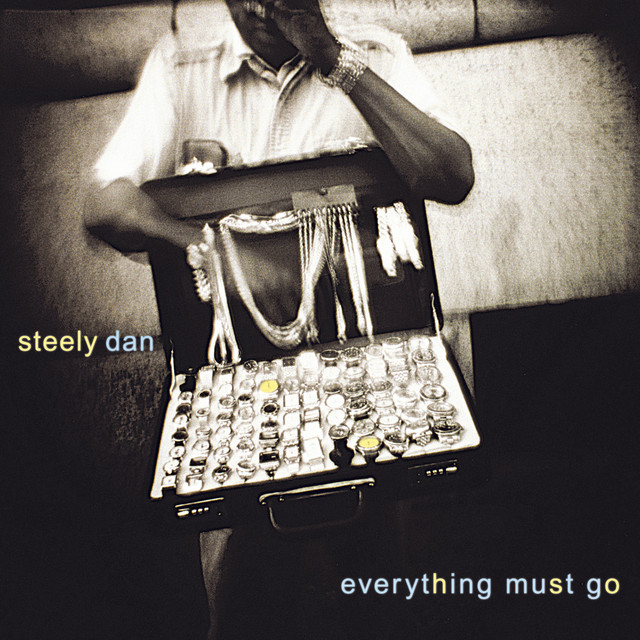
コメント