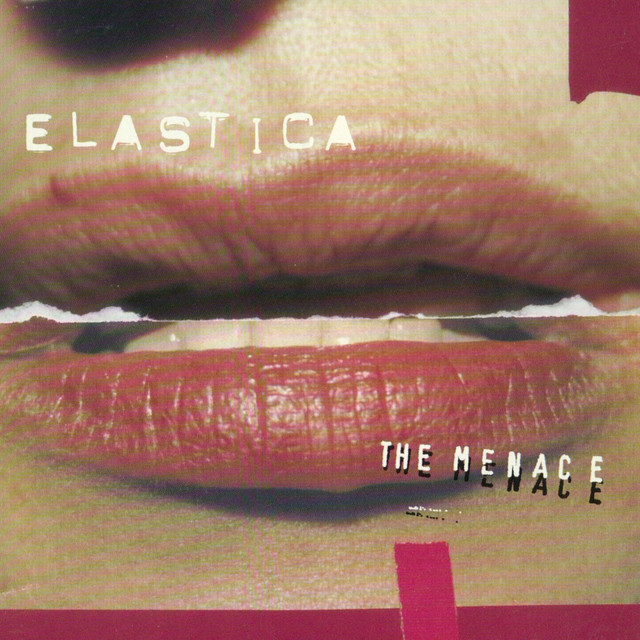
1. 歌詞の概要
「Human(ヒューマン)」は、Elasticaが2000年に発表したセカンド・アルバム『The Menace』に収録された楽曲であり、バンドがその終焉に向かう中で提示した、実験性と不安定さ、そして“人間らしさ”そのものに向き合った楽曲である。
そのタイトルが示す通り、「Human」は“人間であること”を問う歌である。しかし、そこにあるのは決して希望や温もりではなく、むしろ不完全さ、機械と化す感覚、心の空洞、そして自己の分裂といった現代的な“疎外”の感情だ。曲の中で描かれるのは、自分が「人間」であるということが、もはや実感できないという感覚である。
語り手は自らの感情や肉体、そして思考がうまく噛み合わず、何かが常に「ズレている」と感じている。それは精神的な倦怠であり、身体的な無力感でもあり、そして情報過多な都市生活の中で“自分”という存在が薄れていく、そんな時代的な不安でもある。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Human」が収録された『The Menace』は、Elasticaにとって約5年ぶりの新作でありながら、その実、バンドの終幕を予感させる作品でもあった。1995年のデビュー・アルバムの成功以降、メンバーの脱退、創作的な停滞、薬物問題などを経て、Elasticaはかつての鋭利なポップさを保ちつつも、よりダークで実験的なサウンドへと移行していた。
この曲においても、インダストリアル調のビート、ミニマルなループ、そして機械的なエフェクトが強く用いられており、初期のギター・パンクとは一線を画している。ボーカルもまた“語り”に近いモノトーンであり、人間らしい感情をわざと抑えることで、“人間とは何か”を逆説的に浮かび上がらせる演出となっている。
フリッシュマンの声は、ここでは叫びもせず、泣きもせず、ただ“存在すること”に疲弊したような静けさを帯びている。それがかえってこの曲の不穏なリアリズムを際立たせている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に印象的な一節を抜粋し、和訳を添えて紹介する。
I’m just a human being
私はただの人間なのA problem of the flesh and bone
肉と骨にまつわる問題を抱えた存在I carry all the baggage
私はすべての荷物を背負ってるA lifetime on my own
一生をひとりで過ごす覚悟でI must admit I’m feeling numb
正直に言うと もう何も感じなくなってる
※ 歌詞の引用元:Genius – Human by Elastica
これらのラインは、極めて静かで個人的な独白である。“問題のある身体”“感覚の麻痺”“孤独の継続”――それらが語られるトーンには怒りもなければ悲壮感もない。ただそこには、“人間であること”を持て余している感覚が静かに横たわっている。
4. 歌詞の考察
「Human」は、Elasticaがかつての皮肉や性政治的な怒りを脱ぎ捨て、より内面化されたテーマ――自己喪失、感情の麻痺、孤独といった“90年代終焉のメンタリティ”に踏み込んだ数少ない楽曲である。
ここで語られる“人間性”は、他者とのつながりや愛情の可能性ではなく、むしろ“重たさ”として描かれている。「肉と骨の問題」「持ち運ぶ荷物」という言葉は、身体を物理的な拘束物として描写し、“感情”もまた逃れられない負荷であることを示している。
とりわけ重要なのは、“numb(麻痺)”という言葉である。この言葉は、90年代の終わりに多くのアーティストが使ったキーワードでもある。“刺激はあるのに感じられない”“繋がっていても孤独”という感覚。Elasticaはこの曲で、その“静かな苦しみ”をドライに、しかし確かに響かせている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- How to Disappear Completely by Radiohead
存在を消したいという静かな願望が、深い孤独感と共鳴する名曲。 - Hurt by Nine Inch Nails / Johnny Cash
“自分を感じるために痛みを求める”という逆説的表現が共鳴。 - Hyperballad by Björk
“日常の破壊願望”と“再構築される自己”を優雅に描くエレクトロ・バラード。 - A Perfect Day Elise by PJ Harvey
無表情な語り口で、破綻した関係性の裂け目を暴く。 - Little Trouble Girl by Sonic Youth
“女性としての役割”を拒否しながら、その不安定さを美しく描くアヴァン・ポップ。
6. 人間性の“空洞”に触れる:Elasticaのもうひとつの終章
「Human」は、Elasticaが“声を上げる”ことから“沈黙を引き受ける”段階へと至った象徴的な楽曲である。音楽において何かを語るということは、必ずしも多弁である必要はない。むしろ、こうした“何も感じない”という歌詞こそ、深く心に残る。
Justine Frischmannはこの後、音楽活動から身を引き、ビジュアルアートや建築、環境問題の分野へと活動の場を移していくが、この曲はその“脱音楽的”な精神をも先取りしていたのかもしれない。つまり、自らの“人間性”と向き合った結果、彼女は音の外側へと向かっていったのだ。
「Human」はElasticaの中でも最も地味で、最も静かな1曲である。だが、だからこそこの曲は“語られない痛み”や“表現できない感情”の代弁者となり得る。心が何も感じなくなったとき、この曲はそっと寄り添ってくれるだろう。


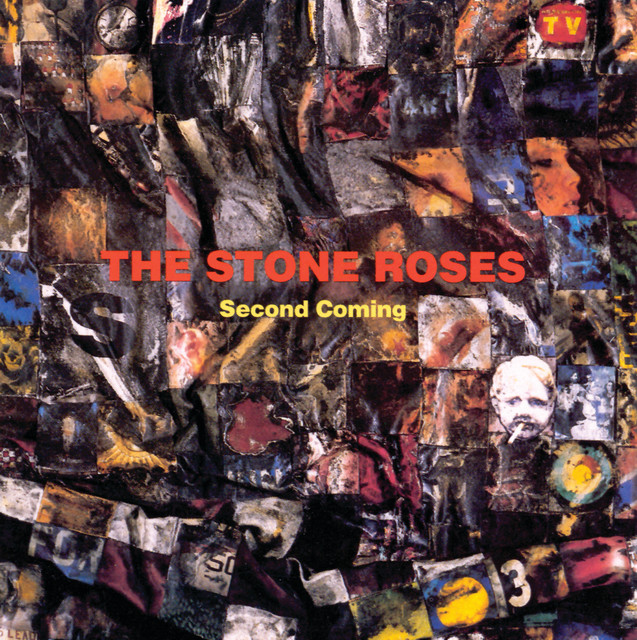
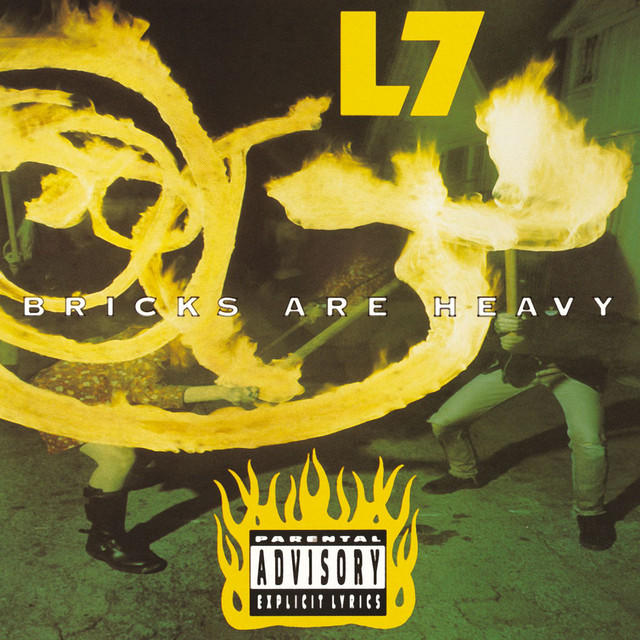
コメント