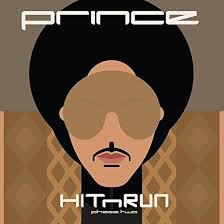
発売日:
Phase One:2015年9月7日
Phase Two:2015年12月12日
ジャンル: ファンク、R&B、ジャズ、エレクトロニック・ソウル
概要
『HITnRUN Phase One』と『HITnRUN Phase Two』は、プリンスのキャリア終盤にあたる2015年に発表された2部作であり、彼の生涯を総括するような音楽的遺言ともいえる作品群である。
両作のタイトルにある“HITnRUN”は、2000年代以降の彼のライブ形式――「突如開催され、突如終わるゲリラ的公演」――から取られている。
この名の通り、アルバムには衝動的で瞬発力のある音楽的実験が満ちており、彼の創造性が最期まで燃え盛っていたことを証明している。
『Phase One』は、当時プリンスが推進していた音楽配信プラットフォーム「TIDAL」を通じて独占リリースされ、電子的・デジタルなサウンドを基調とした現代型プリンス像を提示。
一方の『Phase Two』は、ホーン・セクションを中心とした生演奏中心のオーガニックで温かみのあるファンク/ソウル作品として仕上がっている。
両者はまるで鏡のような関係にあり、前者が「デジタル時代の閃光」、後者が「肉体と魂の帰還」を象徴している。
つまり、『HITnRUN』2部作とは、プリンスが最後に試みた**“音楽の二元論”――人工と自然、機械と人間、瞬間と永遠――の統合実験**だったのだ。
全曲レビュー(Phase One)
1. Million $ Show (feat. Judith Hill)
オープニングは華やかなコンサートの幕開けを思わせる演出的トラック。
かつての名曲「Let’s Go Crazy」の断片を引用しながら、プリンスは再び自らの神話を更新する。
ジュディス・ヒルのゴスペル的ヴォーカルが、アルバムの祝祭的なエネルギーを導く。
2. Shut This Down
エレクトロ・ファンクの極致とも言える一曲。
ノイズ混じりのシンセと歪んだベースラインが衝突し、機械と人間の共鳴を描くようなサウンドが展開される。
「止めるな、今が始まりだ」というプリンスの声が挑発的に響く。
3. Ain’t About to Stop (feat. Rita Ora)
ヒップホップとR&Bの狭間を行く都会的グルーヴ。
リタ・オラのラップ/ヴォーカルがプリンスの低音と交錯し、ジェンダーの境界を越えるデュエットとなっている。
4. Like a Mack
リズム・パターンの複雑さと、ヴォーカルの多層的処理が際立つファンク・チューン。
セクシュアルな比喩に満ちつつ、サウンド自体は極めてモダン。
2000年代以降のR&Bアーティストたちが模倣してきた“プリンス流の未来ファンク”の原点を自ら再提示している。
5. This Could B Us (Remix)
『Art Official Age』収録曲のリミックス版。
オリジナルよりもリズムが強調され、シンセベースのうねりが増している。
過去の自作を未来形に再構築するという姿勢が、本作の核にある。
6. Fallinlove2nite (feat. Zooey Deschanel)
テレビドラマ『New Girl』で共演したズーイー・デシャネルを迎えた軽やかなポップ・ナンバー。
シンセ・ストリングスが明るく弾み、プリンスのユーモアとポップセンスが光る。
7. X’s Face
わずか2分のショートトラックながら、サイバーでスリリング。
激しいドラムマシンの連打が、まるで緊迫した電子戦のように展開する。
デジタル時代のミニマリズムが凝縮された小宇宙的一曲。
8. Hardrocklover
本作のハイライトのひとつ。
プリンスが女性ロッカー像を称賛しつつ、自らのギターを官能的に重ねる。
ファンクとハードロックの境界を曖昧にするそのアレンジは、『Plectrumelectrum』の続編的文脈を持つ。
9. Mr. Nelson
自身の本名“Prince Rogers Nelson”をタイトルにした半自伝的トラック。
ラップ的フロウと未来的エフェクトが融合し、プリンス自身が神話と人間の狭間で語るような内容。
10. 1000 X’s & O’s
1980年代に未発表だった楽曲の再録。
メロウなグルーヴと柔らかなシンセが包み込み、プリンスの優しさと郷愁が感じられる。
11. June
アルバムを静かに締めくくる内省的ナンバー。
「六月、彼女が去った」と呟く声は、どこか人生の黄昏を感じさせる。
時間、愛、喪失――すべてが彼の最後の季節を象徴している。
全曲レビュー(Phase Two)
1. Baltimore
アルバムの幕開けは、2015年の米・ボルチモアでの黒人暴動を背景に作られた社会派ファンク。
「愛が足りない」と訴えるサビは、現代アメリカへのプリンスの祈りのようでもある。
ホーンとストリングスの融合が希望の響きを生み出す。
2. RocknRoll Love Affair
温かいメロディと軽快なリズムが特徴のポップ・ソウル。
「音楽は愛の言葉だ」という普遍的テーマが、晩年の穏やかな心境を映している。
3. 2 Y. 2 D.
ファンキーなギターリフとコーラスワークが印象的なグルーヴ・ナンバー。
演奏陣の一体感が抜群で、生バンドの醍醐味を存分に味わえる。
4. Look at Me, Look at U
ミッドテンポのラブソング。
落ち着いたヴォーカルのトーンに、円熟した表現者としてのプリンスが現れている。
5. Stare
ベースラインがうねる強烈なファンク。
過去の名曲「Kiss」や「Sexy Dancer」のフレーズを引用し、自らの音楽史をセルフ・サンプリングしている。
プリンスの「俺はいまもファンクの王だ」という誇りが溢れる一曲。
6. Xtraloveable
1982年に制作されながら未発表だった幻の曲の再構築版。
ホーンが加わり、より明るく躍動感のあるアレンジに。
過去の自分との対話というアルバム全体のテーマを象徴している。
7. Groovy Potential
ジャズ的コードワークとR&Bの滑らかさが交差するミドル・テンポ曲。
内省的なメロディの中に、**「まだ可能性は無限にある」**というメッセージが宿る。
8. When She Comes
スロウ・ファンクの極み。
セクシュアルなリリックを包み隠さず語るが、そこには成熟したロマンが漂う。
1980年代の官能性とは異なる、静かな情熱が印象的だ。
9. Screwdriver
ギターが唸るストレートなロック・チューン。
軽妙なリズムとシャープな演奏が融合し、プリンスがロック・バンドとして再生した姿が見える。
10. Black Muse
9分に及ぶ大作。
ジャズ、ソウル、ファンクが渾然一体となり、アフロ・アメリカン音楽への壮大なトリビュートになっている。
後半に向かってスピリチュアルな展開を見せ、プリンスの音楽的信仰を感じさせる。
11. Revelation
アルバムのクロージングを飾る美しいソウル・バラード。
柔らかなピアノとストリングスに包まれながら、プリンスは「愛こそがすべて」と繰り返す。
まるで彼自身の人生の最終章を締めくくる祈りのように響く。
総評
『HITnRUN』2部作は、プリンスの最後の創作黄金期を記録した壮大な実験である。
『Phase One』ではデジタル技術とクラブ文化を自在に操り、電子ファンクの未来像を提示。
『Phase Two』ではホーン・セクションと生演奏を中心に、人間の温もりを取り戻す音楽を展開している。
この対照性こそがプリンスの晩年のテーマ――「テクノロジーと魂の共存」――を象徴している。
彼は音楽を通じて、人工知能的な無機質さと、人間的な情感の融合点を探っていたのだ。
『Phase One』の冷たい電子ビートは、“現代”という情報過多の時代を映す鏡。
一方で『Phase Two』は、“永遠”という魂の居場所を探す旅。
両者を通して聴くと、まるで現代の預言書のように、プリンスの思想が立体的に浮かび上がる。
また、この2部作は彼のキャリア総集編でもある。
80年代のファンク、90年代のポップ、2000年代の実験性――それらすべてが自然に混在し、
「プリンスという宇宙の縮図」として機能している。
2016年の急逝を思えば、この2作が彼の最終宣言であったことは偶然ではない。
プリンスは音楽を通して、最後まで未来を語り続けた。
『HITnRUN』は、その未来がまだ続いていることを、私たちに静かに教えてくれるのだ。
おすすめアルバム
- Art Official Age / Prince (2014)
『Phase One』の直接的前身。未来的R&Bの流れを汲む。 - Plectrumelectrum / Prince (2014)
『Phase Two』に通じる生演奏重視のロック・バンド作品。 - Sign o’ the Times / Prince (1987)
社会的テーマと多様な音楽性を併せ持つ原点的傑作。 - Musicology / Prince (2004)
中期のライブ感を重視したファンク路線の代表作。 - The Rainbow Children / Prince (2001)
精神性と音楽的探求を融合させた哲学的アルバム。
制作の裏側
『HITnRUN』2部作の制作には、若きプロデューサーJoshua Weltonが深く関与しており、特に『Phase One』では彼のデジタル感覚がプリンスの音世界に新風を吹き込んだ。
プリンスは「若い世代の耳を通して、自分の音を再構築したかった」と語っており、これは世代間コラボレーションによる自己更新の試みでもあった。
『Phase Two』では再びペイズリー・パーク・バンドを中心に、生演奏主体で録音。
ホーン隊(NPG Hornz)の存在がサウンドの要となり、まるで70年代ソウルのような有機的厚みを生み出している。
また、この2作はプリンスが音楽流通の独立化を徹底的に追求した集大成でもある。
メジャー配給を通さず、自らのサイトやTIDALを通じて直接リスナーに届ける形を採用。
それは、彼が生涯をかけて求め続けた「音楽の自由」「創造の主権」の最終形態だった。
『HITnRUN Phase One / Phase Two』――この二つのアルバムは、単なるラスト・アルバムではない。
それは、プリンスが最後まで“現在進行形”であろうとした証であり、
彼の芸術が死ではなく、永遠のアップデートとして続いていることを伝える作品なのだ。




コメント