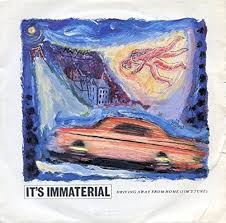
1. 歌詞の概要
「Driving Away from Home」は、1986年にリリースされた英国のバンド、It’s Immaterialの代表曲であり、彼らのデビュー・アルバム『Life’s Hard and Then You Die』に収録されたナンバーである。チャートではUKシングルチャートでトップ20入りを果たし、バンド唯一のヒット曲ともなった。
この楽曲は、ロードトリップという形式を借りながら、イギリスの風景とアイデンティティ、そして“移動”そのものがもたらす感情の変化を描いている。歌詞は淡々と語られるナレーション形式で進み、地名や風景が次々と現れる中で、聴き手はまるでその助手席に座っているかのような感覚を味わう。そこにはノスタルジー、解放感、そしてどこか拭いきれない孤独が入り混じっている。
「Driving Away from Home(家から離れていく)」というタイトルが示す通り、本楽曲は“逃避”や“出発”をテーマとしており、人生のある地点から別の地点へ向かう心の動きを象徴的に描いているのである。
2. 歌詞のバックグラウンド
It’s Immaterialは、リヴァプール出身のバンドで、ポストパンクから発展した実験的なポップ・アプローチが特徴的である。彼らの音楽は決して派手ではなく、むしろ内省的でシニカル、そしてイギリス的なユーモアと哀愁が滲むサウンドを特徴としていた。
「Driving Away from Home」は、その典型と言える。ナレーションを担当するのは、ボーカルのJohn Campbell。彼は穏やかだが断片的な語り口で、リヴァプールから始まり、プレストンやカーノフォース、マイル・エンドなど、北イングランドの地名を走り抜けていく。だがその道中で明確な目的地が語られることはない。
これは“旅”という行為が必ずしも到達点を持つものでなく、むしろその過程や風景のなかに意味があるということを示唆している。1980年代のイギリスにおいて、産業の衰退とともに多くの若者たちが持っていた「どこかへ行きたい」という衝動。その空気を、この曲は見事に音と詞で封じ込めている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
(引用元:Genius Lyrics)
Hey now, little speedyhead, the read on the speed meter says
おい、ちょっとスピード出しすぎじゃないか、スピードメーターが言ってるぜ
You have to go to Tasker’s school, you’re the kind of person who
タスカーズ・スクールに行かなくちゃいけないような奴だな、お前って
Won’t ever fit in with your kind of smile
その笑顔じゃ、どこにも馴染めやしない
But let me tell you about a trip, gonna make it up to you
でもな、旅の話をしてやるよ、それで少しは気が晴れるかもな
このように、語り手はまるで運転中の独白のように、自身や同乗者に話しかける形式で進んでいく。目的地よりも語りそのものに意味があり、リスナーはその言葉と風景の流れの中で、「どこか遠くへ行きたい」という感情を共有することになる。
4. 歌詞の考察
「Driving Away from Home」は、直訳すれば「家から離れていく」だが、ここでの“家”は単なる物理的な場所ではなく、「過去」や「慣れ親しんだ価値観」「幼少期の記憶」といった象徴的な意味を帯びている。そこから離れていく行為は、“自立”であり、“逃避”であり、“探求”でもある。
また、特筆すべきはその語り口である。ほぼ話し言葉の延長のようなリリックは、ストーリーテリングというよりも“現在進行形の実況”に近い。これはリスナーに強い臨場感を与えると同時に、語られていない背景に想像を巡らせる余白を残している。
楽曲全体を包むシンセとシンプルなドラム、そして穏やかなギターは、派手な展開こそないが、まるで郊外をひたすら車で走っているかのような無時間的な空気を生み出している。これが、旅における“間(ま)”の感覚、つまり思考が宙に浮いているような瞬間と完全に重なってくる。
「どこかへ行きたい」「この場を離れたい」という思いを抱えたすべての人に、この曲は静かに語りかけてくる。そしてその旅路には、明確な答えも救いもないが、風景とリズムが静かに寄り添ってくれるのである。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Life in a Northern Town by The Dream Academy
同じく北イングランドを舞台にした哀愁と希望が交錯するロードソング的名曲。 - Road to Nowhere by Talking Heads
どこにも辿り着かない旅、それでも走り続けるという行為自体を描いた哲学的ポップ。 - Driving by Everything but the Girl
都会の孤独を背景にしたドライビングソング。無音に近い余白が際立つ一曲。 - Cars and Girls by Prefab Sprout
アメリカン・ドリームの虚構性を叙情的に綴った、UKインディ・ポップの名作。 - Ghost Town by The Specials
サッチャー政権下の荒廃した都市風景を、スローで不穏なレゲエ・サウンドで描いた社会派の傑作。
6. “どこにも行かない”ことの豊かさ
「Driving Away from Home」は、外的な移動のように見えて、実は内的な思索の旅を描いている。目的地はなく、終わりもない。その旅にあるのは、流れる風景、すれ違う名前の知らない町、そして心のなかで浮かんでは消えていく記憶や思考のかけらたちである。
1980年代のイギリスという時代背景を抜きにしても、この曲が現代でも愛される理由は、“移動”そのものがアイデンティティの再構築に繋がるという普遍的なテーマを描いているからだ。ときに人は、答えを見つけるためではなく、ただ“家から離れる”ために車を走らせる。
その感覚に静かに寄り添うこの曲は、派手さこそないが、日々の喧騒の中で“ふと遠くへ行きたくなる瞬間”にそっと寄り添う、まさに英国ポップ史における詩的な一片なのである。


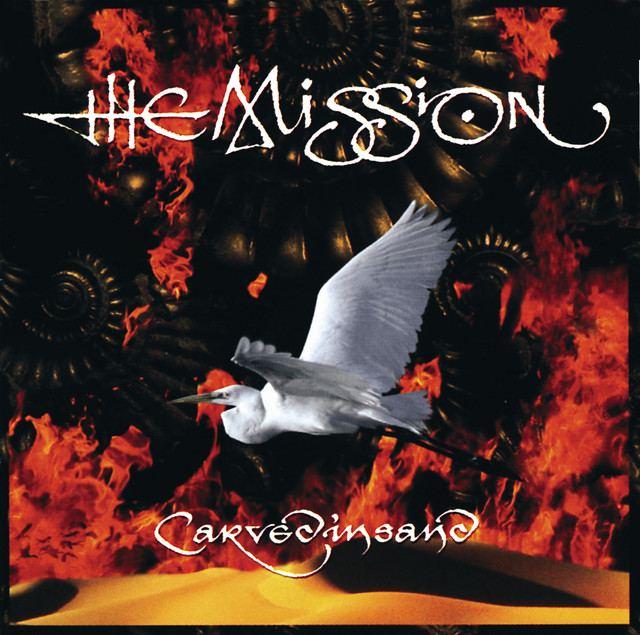
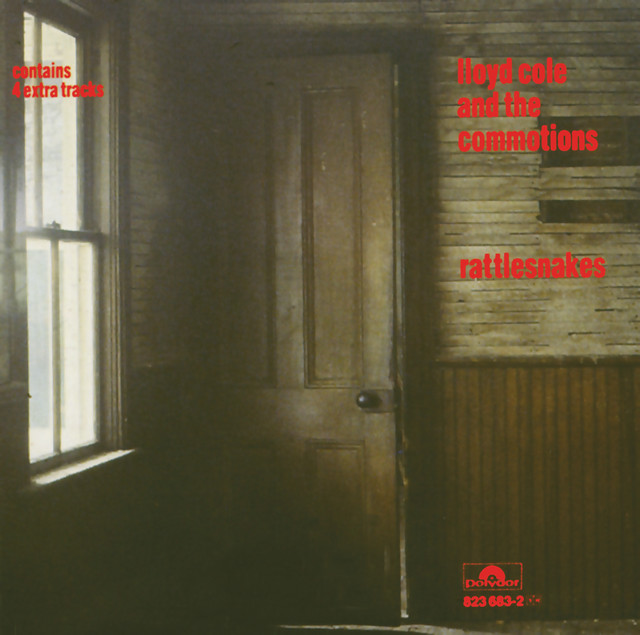
コメント