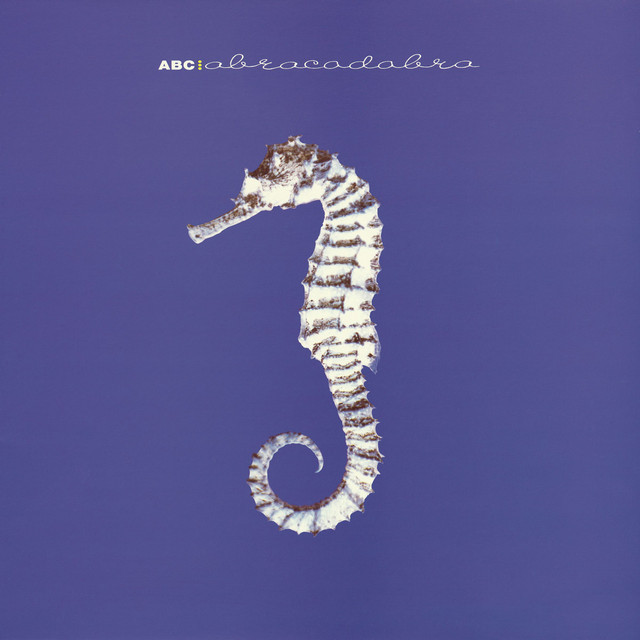
発売日: 1991年8月
ジャンル: ポップ、ブルー・アイド・ソウル、ダンス・ポップ
概要
『Abracadabra』は、ABCが1991年に発表した6作目のスタジオ・アルバムであり、80年代的ポップ・アイコンとしての彼らが、90年代にどのように自らをアップデートするかという問いに対する、一つの回答を試みた作品である。
前作『Up』でハウス・ミュージックへの接近を果たした彼らは、本作で再びポップスとソウルの王道へと立ち戻る。
だが、それは『The Lexicon of Love』のような甘美でオーケストレーション豊かな世界ではなく、90年代的な感覚——すなわちデジタル化、ビート主導、そして大衆性への配慮を含んだ、よりスリムなポップ・フォーマットへと再構成されたものであった。
アルバム・タイトルの“Abracadabra”は、魔法の呪文であると同時に、音楽や言葉が持つ“魅了する力”を象徴する言葉でもある。
ABCはこのアルバムを通じて、かつて自らが作り上げた「スタイリッシュな虚構」と、90年代のより「現実的なポップ」に橋をかけようとしたのである。
サウンド面では、マーティン・フライとマーク・ホワイトによるセルフ・プロデュースが中心。
アナログ感を残しながらも、打ち込みとサンプルが絶妙に融合したプロダクションとなっている。
しかし商業的には大きな成功を収めることはできず、この作品を最後にマーク・ホワイトがABCを脱退。
バンドとしてのABCは、このアルバムを境に新たなフェーズへと進むことになる。
全曲レビュー
1. Love Conquers All
冒頭から軽快なビートと希望に満ちたメッセージで幕を開ける。
“愛はすべてに打ち勝つ”というテーマは、ABCにしては珍しくストレートで、90年代の新しいリスナー層への意識を感じさせる。
2. Unlock the Secrets of Your Heart
メロウなグルーヴとセクシュアルなリリックが交差するミディアム・ナンバー。
内面への鍵を開けるという比喩は、愛と欲望の間の曖昧さを巧みに表現している。
3. Say It
先行シングルとしてリリースされた楽曲で、繰り返される“Say it”のフレーズが中毒性を持つ。
エレクトロ・ファンクの要素も含み、クラブ寄りのサウンドが特徴。
4. All That Matters
穏やかなストリングスとピアノによるバラード。
“本当に大切なものは何か”を問う、哲学的ともいえるラブソングであり、ABCのバラード志向の進化が感じられる。
5. This Must Be Magic
アルバムタイトルに通じる“魔法”というモチーフを使ったファンタジックな一曲。
チープになりかねないテーマを、上品なアレンジと丁寧なヴォーカルで昇華している。
6. Say It (Black Box Mix)
イタリアのハウス・ユニットBlack Boxによるリミックス・バージョン。
本編以上にクラブ仕様となっており、90年代のダンス・フロアへの意識が強い。
7. Love is Its Own Reward
ソウルフルでスローなテンポが心地よい。
“愛そのものが報酬である”というテーマは、どこか諦念と再出発を同時に含むような奥行きを持つ。
8. Spellbound
“呪縛”をテーマにしたサイケデリック・ポップ寄りの実験的楽曲。
ABCにしては珍しく、不穏なコード進行とエフェクトが印象的。
9. Lingering
別れた後も残る“余韻”をテーマにした曲。
しっとりとした演奏とメランコリックな旋律が、情緒豊かな空気を生む。
10. All That Matters (Reprise)
再び登場するバラードのリプライズ。
この構成はアルバム全体を一つの物語として捉える姿勢を表しており、トータル性を感じさせる。
総評
『Abracadabra』は、ABCが「時代に追いつく」のではなく、「時代を受け入れる」ことを選んだアルバムである。
サウンドはよりコンパクトで、90年代初頭のポップ・トレンドに沿っており、過去作のようなオーケストラや過剰な演出は控えめである。
しかし、その代わりに浮かび上がってくるのは、マーティン・フライのパーソナルでナイーブな表現であり、“語り”としてのポップ・ソングの奥深さである。
この時期、ポップ・シーンはグランジやUKマンチェスター・ムーブメントなど、新しい波が台頭していた。
そんな中でABCは、きらびやかでも前衛的でもなく、“大人のポップス”としての静かな佇まいを保っていた。
それは時代に翻弄されることなく、自らの「美意識」に忠実であろうとした姿勢であり、むしろ潔さを感じさせる。
決して派手な作品ではない。
だが『Abracadabra』は、ABCというアーティストが持つ持続可能なスタイルと、成熟への道を静かに照らすランプのような存在なのだ。
おすすめアルバム(5枚)
- Swing Out Sister – Get in Touch with Yourself (1992)
洗練されたソウル・ポップとしての立ち位置や、90年代的成熟感に共通点がある。 - Everything but the Girl – The Language of Life (1990)
アーバンなジャズ・ポップの中に感情の深みを溶け込ませた名盤。 - Prefab Sprout – Jordan: The Comeback (1990)
叙情性とポップ・アートのバランスが絶妙な作品。ABCの知的ポップと並べて聴きたい。 -
Lighthouse Family – Ocean Drive (1995)
滑らかなグルーヴとリラックスしたテンションで、同系統の“聞き心地”を提供する作品。 -
Paul Weller – Wild Wood (1993)
ポップ・ソウルを90年代的に再構築した好例として、異ジャンルながら通じるものがある。
歌詞の深読みと文化的背景
『Abracadabra』の歌詞には、幻想や魔法といった非現実のモチーフが散見される一方で、その根底にあるのは“現実との和解”である。
これは、恋愛や人生における過度な理想ではなく、不完全さや曖昧さを受け入れる態度と読み取れる。
たとえば「Spellbound」では、魅了されることの危うさが描かれ、「Lingering」では関係が終わった後にも残る感情の“亡霊”がテーマになる。
それらは、単なるポップ・ソングのロマンスではなく、心理的な余韻を大切にする、まさに90年代的な“感情の地図”なのだ。
また、「Say It」に代表されるような直接的な言葉への欲求——つまり“語ること”自体の重要性も、このアルバムの一貫したテーマである。
ABCは本作を通じて、80年代の虚構から脱却し、言葉と音によって「本音」を伝えようとしたのかもしれない。


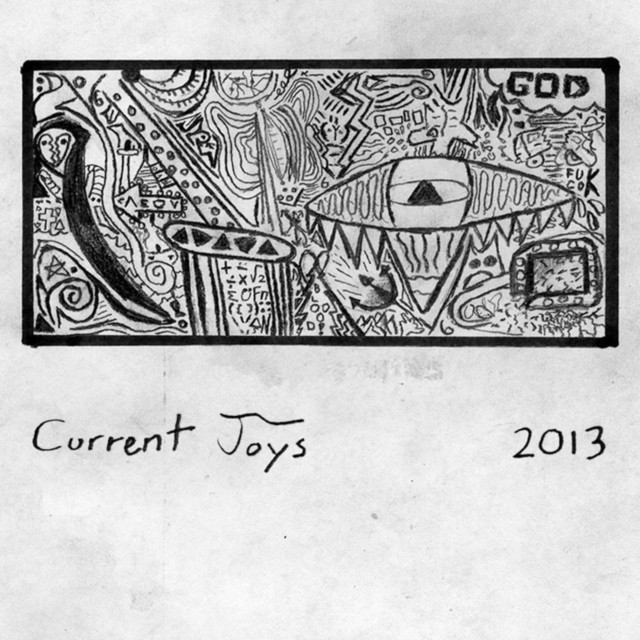

コメント