
発売日: 1996年9月16日
ジャンル: ネオサイケデリア、オルタナティヴ・ロック、エレクトロニカ、ノイズポップ
概要
『C’mon Kids』は、The Boo Radleysが1996年にリリースした5作目のスタジオ・アルバムであり、前作『Wake Up!』で獲得したポップな成功とメインストリームでの注目を“自らぶち壊す”という大胆な芸術的選択を示した、挑発的かつ複雑な作品である。
前作の代表曲「Wake Up Boo!」で“明るく祝祭的なブリットポップ・バンド”として認知された彼らだったが、本作ではそのイメージを徹底的に解体し、ノイズ、歪んだエレクトロ、サイケデリックな展開、そして意味深で抽象的な歌詞によって、リスナーを戸惑わせるような音世界を築き上げた。
結果として商業的には前作から大きく後退したものの、批評家からは「真のオルタナティヴ・スピリットの体現」として高く評価され、90年代後半UKインディーの転換点として重要な位置を占める作品となった。
このアルバムは、“子どもたちよ、目を覚ませ。これは本物の音楽だ”というメッセージとしても読める。
その矛盾に満ちた音像と情動の奔流こそが、『C’mon Kids』の本質である。
全曲レビュー
1. C’mon Kids
ギターのノイズとエレクトロニクスが混ざり合う、衝撃的なオープニング。
タイトルに反して“ウェルカム”な雰囲気は皆無であり、前作のファンを一撃で裏切る挑戦的トラック。
2. Meltin’s Worm
ヒップホップ的ビートとダブ処理されたベース、歪んだシンセが交錯。
サイケとローファイ・ビート・カルチャーが融合した、奇妙なミニチュアのような楽曲。
3. Melodies for the Deaf
ノイジーなギターと陰影のあるメロディが印象的。
「耳の聞こえない人のためのメロディ」というタイトルに、音楽そのものへのアイロニーが滲む。
4. Get on the Bus
勢いのあるポップ・パンク的ナンバー。
“バスに乗り遅れるな”というメッセージが、希望と皮肉の両義性を帯びて響く。
5. Everything Is Sorrow
タイトル通りの鬱屈と静けさを持つバラード。
シンプルなアコースティック・コードのなかに、人生の不確かさがじんわりと染み出す。
6. Bullfrog Green
再び轟音ギターとひねくれた展開が襲いかかる。
子供番組のようなタイトルとは裏腹に、不穏な展開と攻撃的なサウンドが炸裂。
7. Heaven’s at the Bottom of This Glass
最もメランコリックな1曲。
アルコールと喪失、虚無と癒しが入り混じるような、大人のためのサイケ・ポップ。
8. What’s in the Box? (See Whatcha Got)
本作の中では最も“シングル向け”な楽曲でありながら、やはり普通では終わらない。
ポップなフックの裏に、混沌としたエフェクト処理と冷笑的な歌詞が潜む。
9. Four Saints
穏やかなイントロからノイズが徐々に侵食してくる中編。
宗教的な言葉遊びがサウンドと絡まり、意味の深読みを誘う。
10. New Brighton Promenade
ノスタルジックなシンセとメロディが印象的なミディアム・ナンバー。
バンドの地元・リバプールの風景が幻想として描かれる。
11. Fortunate Sons
緊張感のあるリズムと幻覚的なギター・ループが続く、サイケデリックなドローン・ポップ。
「幸運な息子たち」というタイトルは皮肉の響きを持ち、階級と文化の問題をほのめかす。
12. Ride the Tiger
ジャングルビートとサイケギターが融合した実験的楽曲。
“虎に乗ってしまったら、降りられない”というメタファーがアルバム全体のテーマと響き合う。
13. One Last Hurrah
アルバム終盤に現れる、多幸感と終焉感が同居する異色のトラック。
終わりなき宴のラストダンスのような、陶酔と疲弊の入り混じる1曲。
14. Altamont
アルバムを締めくくるにふさわしい、静かで破滅的なナンバー。
60年代ロックの終焉を象徴するオルタモント事件を引用し、夢の崩壊と醒めをメタフォリカルに描いている。
総評
『C’mon Kids』は、The Boo Radleysが“ポップスターになること”を拒否し、“自分たちであり続けること”を選んだ音楽的声明である。
祝祭的な『Wake Up!』の後にこれほど攻撃的で難解な作品を出すという判断は、商業的には明らかにリスクだったが、芸術的には崇高な行為だったとも言える。
その結果、本作はリスナーをふるいにかけるような作品となり、熱狂的な支持と困惑の両方を招いた。
だが今あらためて聴き返すと、『C’mon Kids』は時代に媚びなかったがゆえに、むしろ“時代を超える響き”を手に入れていたことに気づく。
複雑で予測不能、だけど本物。
このアルバムは、90年代UKオルタナティヴの良心であり、勇気の記録でもある。
おすすめアルバム
- Radiohead / The Bends
ポップと実験の狭間で揺れる作品。90年代半ばの内向と跳躍の象徴。 - Super Furry Animals / Radiator
カラフルかつ破天荒な実験ポップ。Boo Radleysの精神的後継者のひとつ。 - The Beta Band / The Three EPs
ロック、ヒップホップ、サイケを融合した自由奔放な音世界。 - Mercury Rev / See You on the Other Side
サイケと幻想の交差点にある、孤高の実験作。 - Primal Scream / Vanishing Point
ダブ、サイケ、ジャングルを取り込んだ、90年代UKロックの“裏の正史”。
ファンや評論家の反応
リリース当時、批評家からは好意的に迎えられ、「The Boo Radleysが本当にやりたかった音楽がここにある」と絶賛された。
一方、前作『Wake Up!』の軽快なポップを期待していた一般リスナーからは困惑の声も多く、チャート的には低調に終わった。
しかし、のちに本作は“過小評価された名作”として再評価され、ブリットポップが商業主義に向かうなかで、逆方向に進んだ例外的存在として語られるようになる。
『C’mon Kids』は、賑やかな時代のなかで「一歩立ち止まって考える」ための音楽だったのかもしれない。


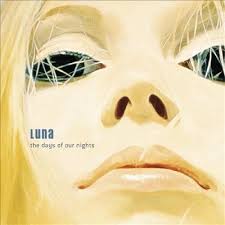
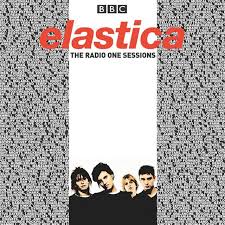
コメント