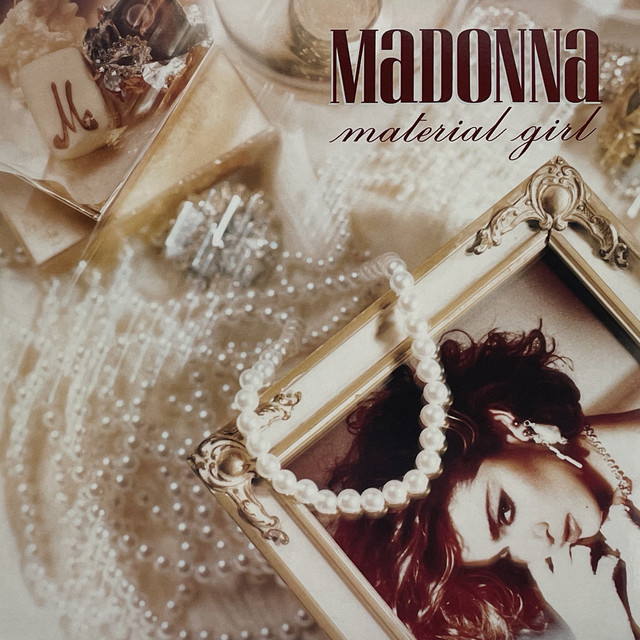
1. 歌詞の概要
マドンナの「Material Girl」は、1984年にリリースされた2作目のアルバム『Like a Virgin』からのシングルであり、彼女のイメージを決定づけたアイコニックな楽曲の一つである。この曲では、“物質的な世界に生きる女の子=Material Girl”を自称する主人公が、恋愛や人間関係において経済力やステータスを重視するというスタンスを、軽快でアイロニカルなポップソングとして表現している。
歌詞はシンプルで反復的ながら、その中には当時の消費社会、ジェンダーのダイナミクス、女性の主体性という重要なテーマが潜んでいる。「Cause we are living in a material world, and I am a material girl(私たちは物質世界に生きている、そして私は物質的な女の子)」というサビのフレーズは、80年代という時代精神を象徴し、マドンナ自身のパブリック・イメージと密接に結びついていった。
その一方で、この楽曲は単なる拝金主義の礼賛ではなく、むしろその価値観を逆手に取った自己演出、あるいはアイロニーとして解釈されることも多い。マドンナはこの曲を通じて、“消費社会における女性像”を強烈に可視化し、同時にそれを自分の手に取り戻す術を提示しているのである。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Material Girl」は、ソングライターのピーター・ブラウンとロバート・ランズによって書かれた楽曲で、マドンナがこれを採用したのは、アイコニックなイメージを確立するうえでの計算された自己演出の一環だったとされている。彼女自身もインタビューで、この曲が自分の本質を表しているわけではなく、「ある種のキャラクターを演じている」と語っている。
ミュージックビデオでは、マドンナがマリリン・モンローの『紳士は金髪がお好き』でのパフォーマンス「Diamonds Are a Girl’s Best Friend」をオマージュし、ピンクのドレスに身を包みながら、ダイヤモンドや贈り物に囲まれて踊る姿が印象的に描かれている。この演出は、マドンナの中に“セックスシンボル”と“自己決定権を持つ女性”という二面性を同居させ、その後のキャリアにおけるフェミニズム的アプローチの出発点とも言える。
この曲の影響は非常に大きく、「Material Girl」はマドンナ自身の代名詞となり、彼女は以後何年にもわたり“マテリアル・ガール”と呼ばれ続けた。だが皮肉なことに、マドンナは後にこのレッテルを「自分を制限するもの」と捉え、距離を置くようになっていく。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下は、楽曲の象徴的なラインの一部とその和訳です(出典:Genius Lyrics)。
“Some boys kiss me, some boys hug me / I think they’re okay”
「キスしてくれる男の子もいれば、抱きしめてくれる子もいる / まあまあね」
(愛情表現にはあまり関心がない様子を軽妙に語る)
“If they don’t give me proper credit, I just walk away”
「でも、ちゃんと評価してくれなきゃ、私はすぐに去るの」
(自分の価値を認めない相手とは付き合わない、という自己主張)
“‘Cause we are living in a material world / And I am a material girl”
「だって私たちは物質世界に生きてるの / 私はマテリアル・ガールなのよ」
(このフレーズが曲全体の核となり、皮肉とも宣言ともとれる)
“The boy with the cold hard cash / Is always Mister Right”
「現金を持った男の子こそが、理想の相手」
(金銭的な力が恋愛市場における“正解”であるという価値観の強調)
“Experience has made me rich / And now they’re after me”
「経験が私を豊かにしたの / だから今度は男たちが私を追ってる」
(逆転した力関係と、自信に満ちた女性像の提示)
このように、歌詞はユーモアとアイロニーに満ちており、単なる金銭崇拝ではない深みを持っている。
4. 歌詞の考察
「Material Girl」の歌詞は、一見すると「お金がすべて」と言っているようにも聞こえるが、実際にはそれを演じることによって、マドンナは“女性が物質主義の世界でどう生き延びるか”という問いを提起している。彼女が提示する「マテリアル・ガール」は、男性からの贈り物や地位に依存しているように見えつつも、実はその力を逆手に取って主導権を握る存在である。
マドンナはこのキャラクターを通じて、従来の“受け身の女性像”を解体し、欲望の主体としての女性を描いている。「愛」ではなく「評価(proper credit)」を求める彼女の姿勢は、恋愛を通じて自己実現を図るのではなく、自らの価値を他者に認めさせようとする現代的な女性像を体現している。
さらに興味深いのは、「経験が私を豊かにした」というラインである。これは物質的な“rich”だけでなく、精神的、知識的な豊かさをも示唆しており、最終的には“選ばれる側”から“選ぶ側”への転換を強く印象づけている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” by Marilyn Monroe
マドンナのビデオの元ネタであり、女性と富の関係をユーモラスに描いた名曲。 - “She Works Hard for the Money” by Donna Summer
労働と自己価値を歌い上げる女性アンセム。社会的文脈を重ねて聴きたい。 - “Rich Girl” by Hall & Oates
金銭と人間関係の境界線を描いたポップソング。Material Girl的視点と対比的。 - “Just a Girl” by No Doubt
90年代以降のフェミニズム的ポップソング。マドンナの精神をパンク風に継承。 - “Confident” by Demi Lovato
自己肯定感とセクシュアリティを前向きに描いた現代の“強い女性”ソング。
6. “マテリアル・ガール”というレッテルの功罪
「Material Girl」は、マドンナにとって最も有名な楽曲の一つであると同時に、最も誤解されやすい楽曲でもある。この曲の大ヒットにより、彼女は“拝金主義の象徴”のように見なされることもあったが、マドンナ自身は後に「自分の本質ではなく、演じていたキャラクターが一人歩きした」と語っている。
しかし、結果としてこの楽曲は、ポップミュージックにおける女性の立ち位置を変える大きな転換点となった。単に「美しくいること」が女性の価値だった時代から、自分自身のルールと価値観で人生を築く女性像へと、ポップソングが描く理想像をシフトさせたのである。
マドンナの「Material Girl」は、消費社会を生き抜く女性の仮面と本音を、ポップの言語で鮮やかに描き出した革新的な作品である。彼女は“物質的”であることを一種の武器として利用し、同時にその内側にある自己決定と誇りを、ユーモアとアイロニーで包み込みながら提示した。この曲を聴くたびに、“あなた自身の価値は、誰が決めるのか?”という問いが、リズムの裏から立ち上ってくる。


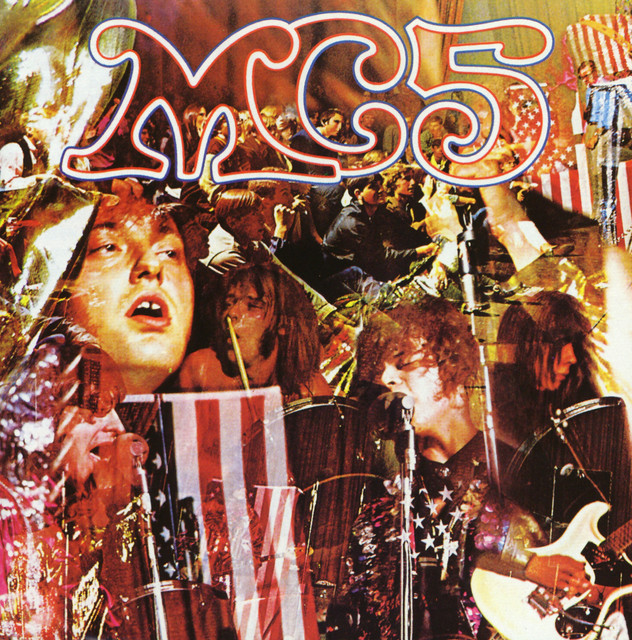
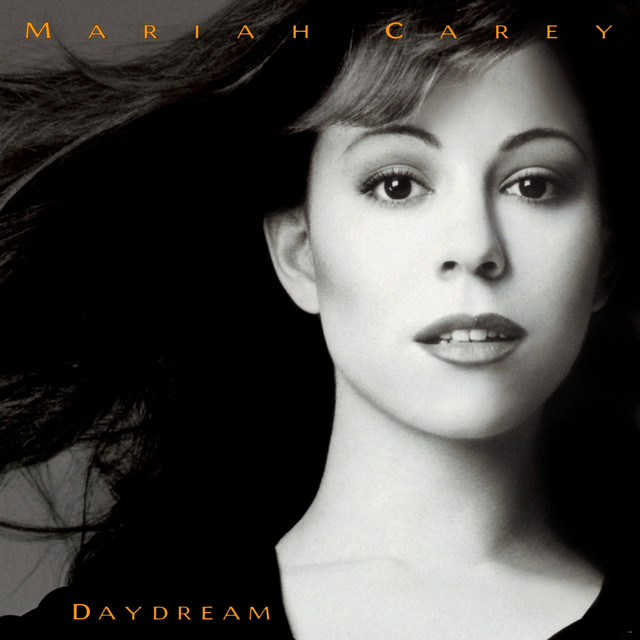
コメント