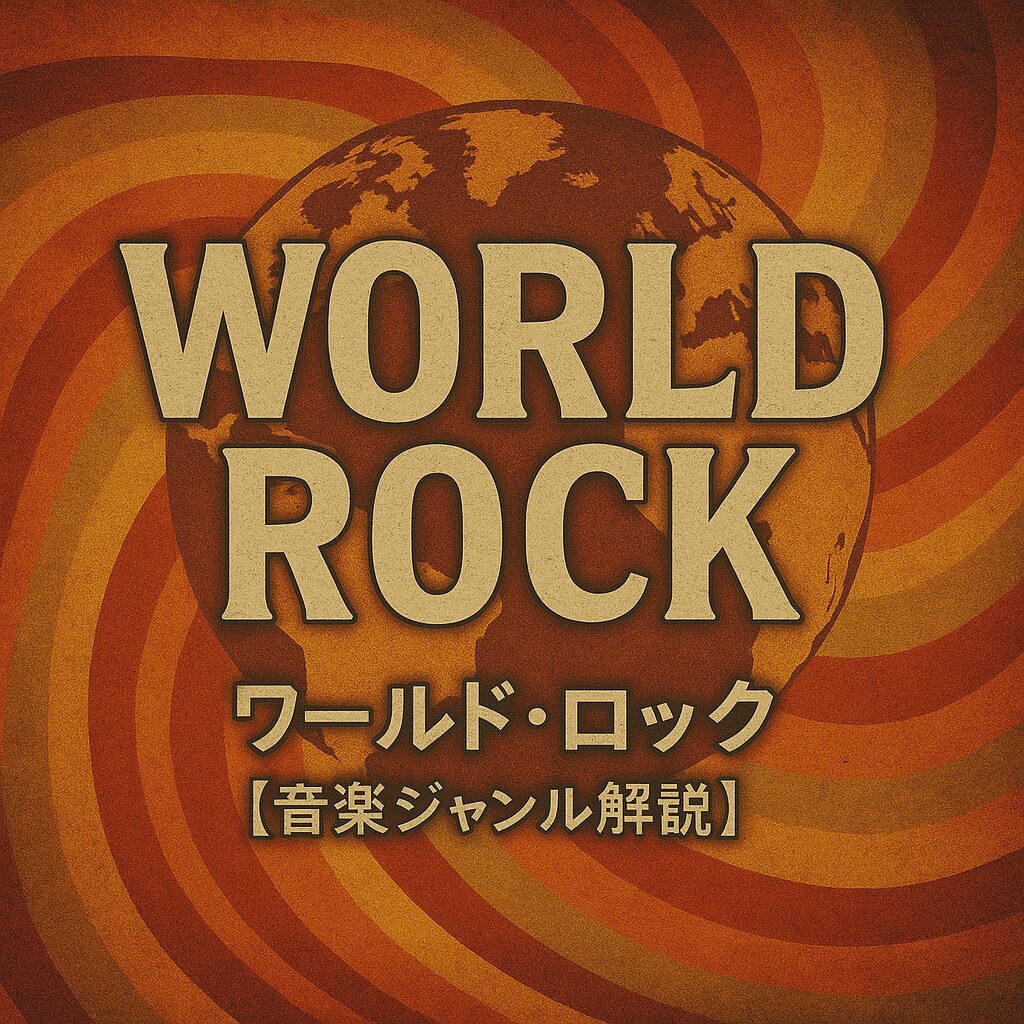
概要
ワールド・ロック(World Rock)は、世界各地の民族音楽・伝統音楽とロックのエッセンスを融合させたジャンル横断型ロック音楽の総称である。
「ワールド・ミュージック」という広範な枠組みに属しつつも、ギター、ベース、ドラムといったロックの基本構成を保ちながら、各地域のリズム、旋律、楽器、歌唱法を積極的に取り入れるのが特徴である。
つまりワールド・ロックとは、ロックという汎西洋的フォーマットに、アフリカ、アジア、中東、ラテンアメリカ、ヨーロッパの土着性を注ぎ込むことで、新たな表現領域を切り開く音楽と言える。
成り立ち・歴史背景
ワールド・ロックの源流は、1960年代末〜1970年代初頭のサイケデリック・ロックやプログレッシブ・ロックによる異文化志向にさかのぼる。
The Beatlesが『Revolver』『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』でインド音楽やサウンド・コラージュを導入したことを皮切りに、
Traffic、Peter Gabriel、Paul Simon、David Byrneらが次々と異文化とロックの融合を試みた。
1980年代には、イギリスで「ワールド・ミュージック」という用語が定着し、異国的音楽へのリスペクトと商業的展開のバランスが模索される時代に入る。
この文脈の中で、**“ロックのフォーマットで世界音楽を奏でる”**という形で発展したのがワールド・ロックである。
グローバリゼーションとともに世界各国のバンドが登場し、
1990年代以降はジャンルを横断する“フュージョン・ロック”の一形態として定着していく。
音楽的な特徴
ワールド・ロックの音楽的な特徴は非常に多様だが、以下のような要素がしばしば見られる。
- 地域伝統楽器の導入(シタール、ダラブッカ、ジャンベ、尺八、バラライカなど)
-
民族音階や変拍子の使用:西洋音楽にはない独特の旋律感・リズム感。
-
多言語・土着語による歌唱:英語以外の歌詞が多く、文化的多様性を感じさせる。
-
コーラスやコール&レスポンスなど集団性を重視:儀式性、祝祭性を伴うことが多い。
-
政治的・社会的な文脈を含むリリック:アイデンティティ、植民地主義、移民問題など。
-
ロックの骨格(ギター、ベース、ドラム)に伝統音楽を溶かし込むアレンジ。
代表的なアーティスト
-
Santana(米・メキシコ系):ラテン系だが、アフロ・キューバンやブルースを巻き込んだ世界ロック的存在。
-
Peter Gabriel(UK):ソロキャリアでアフリカや中東の音楽を積極的に導入。
-
Paul Simon(US):『Graceland』で南アフリカ音楽を紹介し、文化融合を成し遂げた。
-
Tinariwen(マリ):サハラのトゥアレグ族出身。砂漠のブルースとロックの融合。
-
Gogol Bordello(ウクライナ系):ジプシーパンク。東欧民謡とロックの激烈融合。
-
Dengue Dengue Dengue(ペルー):アンデス音楽+エレクトロ+ロック。
-
Rokia Traoré(マリ):アフリカの弦楽器×ロック的構成で世界的評価を受けた。
-
The Hu(モンゴル):ホーミーと馬頭琴+ハードロックで国際的にブレイク。
-
Jambinai(韓国):伝統楽器とポストロック/メタルの融合。圧巻のライブ力。
-
Systema Solar(コロンビア):クンビア、ヒップホップ、ロックを横断。
-
Seun Kuti & Egypt 80(ナイジェリア):フェラ・クティの息子。アフロビートとロック精神の結合。
名盤・必聴アルバム
-
『Graceland』 – Paul Simon (1986)
南アフリカ音楽を取り入れた傑作。世界とロックの交差点。 -
『So』 – Peter Gabriel (1986)
ヒット曲「Sledgehammer」「In Your Eyes」収録。アフリカン・ポップをロック化。 -
『Aman Iman』 – Tinariwen (2007)
砂漠のブルースと反骨のメッセージが交差する一枚。 -
『The Gereg』 – The Hu (2019)
モンゴリアン・メタルの衝撃作。馬とギターの激突。 -
『Différance』 – Jambinai (2012)
韓国伝統音楽+ポストロックの現代的解釈。
文化的影響とビジュアル要素
-
民族衣装、部族的シンボル、自然崇拝、宗教的モチーフなどがビジュアル面に強く出る。
-
“母国語でロックする”という文化的意志の表れ:ローカル性の誇りが感じられる。
-
グローバリゼーションと逆行する“土着の声”としてのカウンターカルチャー性も強い。
-
ワールド・ミュージック・フェスティバル(WOMAD、Rainforest World Music Festivalなど)で広く支持される。
-
MVは土地、部族、儀式、踊り、自然風景などを主題にした映像詩的作品が多い。
ファン・コミュニティとメディアの役割
-
WOMAD(World of Music, Arts and Dance)をはじめとするフェスが文化交流の中心地。
-
Bandcampなどのプラットフォームで世界各地のアーティストが直接発信。
-
BBC RadioやNPR、France Interなどの国際放送が積極的に紹介。
-
YouTubeではルーツを掘るディープなファンコミュニティも形成。
-
Spotifyでは「Global Rock」「World Fusion Rock」などのプレイリストが存在。
ジャンルが影響を与えたアーティストや後続ジャンル
-
ポストロック系バンド(Jambinai、Yosi Horikawaなど):伝統と実験の橋渡し。
-
エスノ・エレクトロ(Dengue Dengue Dengue、Chancha Via Circuito):ルーツ+デジタル。
-
ワールド・ジャズ(Shakti、Avishai Cohen):即興性と民族旋律の交錯。
-
ネオフォーク/トライバル・インダストリアル(Heilungなど):儀式音楽と重低音の交差。
-
グローバル・ヒップホップ(Baloji、Lowkey):ラップとワールド視点の融合。
関連ジャンル
-
ワールド・ミュージック:伝統音楽+モダン解釈の総称的カテゴリー。
-
エスニック・ロック/フォーク・ロック:土着性とロックの交差点。
-
アフロビート/アフロ・ロック:ナイジェリア発のポリリズム+反骨音楽。
-
サイケデリック・ロック:音響的トリップ性を共有。
-
ラテン・ロック/トロピカリア:地域型ワールド・ロックの一例。
まとめ
ワールド・ロックとは、ロックという共通語を通じて、それぞれの“故郷の声”を世界に響かせる音楽である。
それはコスプレではなく、アイデンティティの再生であり、過去と未来を結ぶ音の旅なのだ。
“その土地にしか鳴らない音”を、“世界の舞台で鳴らす”――それがワールド・ロックの本質である。



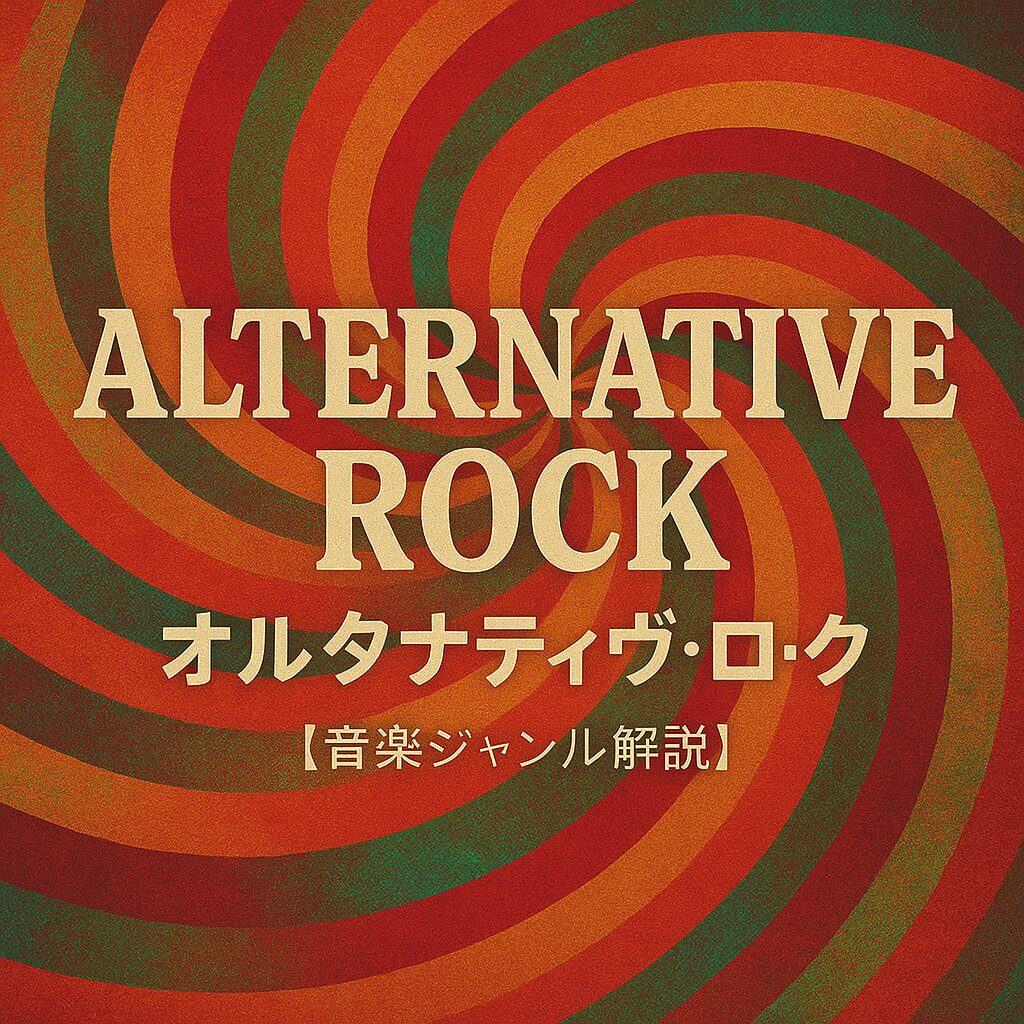
コメント