
発売日: 1982年10月8日
ジャンル: ポップロック、2トーン・スカ、ミュージックホール、バロック・ポップ、シアトリカル・ポップ
概要
『The Rise & Fall』は、Madnessが1982年に発表した4作目のスタジオ・アルバムであり、
「2トーン・スカ・バンド」から「ブリティッシュ・ポップの語り部」へと進化を遂げた、芸術性と大衆性が最も高次に交差した代表作である。
前作『7』で見せたスカ一辺倒からの脱却に続き、本作ではサウンドの幅が飛躍的に拡大。
バロック・ポップ、ケルト音楽、サイケ、ジャズ、音楽劇などが織り交ぜられ、**まるで一篇の映画か舞台作品のように展開する“都市と記憶の組曲”**となっている。
一見してコミカルで軽やか、だがその奥には、ロンドンの街角に埋もれた哀しみと懐かしさ、時代への郷愁と皮肉が混在している。
アルバムはリリース当時から高い評価を受け、「Our House」の世界的ヒットとともに、
Madnessの名前を“スカ・リヴァイバルの一発屋”から“英国ポップの本質を担う存在”へと押し上げた。
全曲レビュー
1. Rise and Fall
タイトル曲にしてアルバムの序章。
Suggsが語りかけるように歌うスタイルで、古い街並みの記憶と、それが変化していく様子への感傷を、
木管やピアノの柔らかい音色で包み込む。
のちの『Parklife』や『The Life Pursuit』にも通じるローカル回想ポップの先駆。
2. Tomorrow’s (Just Another Day)
哀愁あるメロディとダークなスカのビートが印象的な人気曲。
「明日は今日と変わらない」という諦念と、それでも前に進もうとする陰と陽の同居がMadnessらしい。
歌詞とアレンジが緊密に結びついた、成熟の証とも言える名作。
3. Blue Skinned Beast
サッチャー政権下のイギリスに対する、ブラックユーモアに満ちた政治風刺ソング。
“青い肌の獣”という寓話的表現により、戦争や体制の暴力性を鋭く刺す。
語り芝居風のヴォーカル、軍楽隊風のアレンジが効果的で、イギリス音楽における“風刺の伝統”を継承する一曲。
4. Primrose Hill
ロンドン北部の丘「プリムローズ・ヒル」への郷愁がにじむ、穏やかで詩的なナンバー。
Suggsの囁くようなヴォーカルと、木漏れ日のような音の柔らかさが調和し、
まるで記憶のアルバムをめくるような静けさが広がる。
サウンド面ではサイケポップの影響も感じられる。
5. Mr. Speaker (Gets the Word)
スウィング・ジャズ調のサウンドに乗せた、議会と演説をテーマにした風刺的ミュージカル・ナンバー。
テンポの良い語り口と寸劇風の展開は、まさに音楽ホール伝統のモダンアップデート。
ユーモアの奥にある“言葉の無力さ”というテーマが効いている。
6. Sunday Morning
日曜の静けさを写し取った、叙情的インストゥルメンタル。
ピアノとストリングスのアンサンブルが美しく、
“休息”というより“空虚”を描いたような、都市の寂しさが沁みる。
物語の間奏としても完璧な配置。
7. Our House
世界的ヒットとなった代表曲。
どこか懐かしく、誰にでもあった家族の風景をポップに描いた**“家庭讃歌”であり“労働者階級の讃美歌”**。
サビのキャッチーさ、ピアノのリフ、ホーンアレンジ、すべてが完璧に機能しており、
この1曲でMadnessが“英国ポップの語り部”であることを確定させた。
8. Tiptoes
静かなギターとサイケ調のエフェクトが印象的な異色作。
“つま先立ちで歩くように、誰にも気づかれずに進む”というイメージは、都市生活者の心象風景としても捉えられる。
音響的にも先鋭的で、当時のニューウェイブ〜ポストパンクとも接続する。
9. New Delhi
エキゾチックな旋律とスカビートが融合した“旅行者の目線”の一曲。
「異文化の風景を眺めるイギリス人の無意識」を軽やかに皮肉る視点があり、
旅する音楽としても、批評性を帯びたアートとしても機能する好例。
10. That Face
スウィング感のあるジャズ・ポップにのせた、顔の記憶と恋のすれ違いを描いたエレガントな小品。
音楽ホールの伝統を受け継ぎつつ、モダンな響きでまとめられており、
年齢や性別を超えて共感できる叙情が詰まっている。
11. Calling Cards
ミドルテンポで静かな感触の曲。
“誰かの痕跡”=calling cardがテーマで、去ってしまった人々への追憶と、残されたものの意味を考えるような深さを持つ。
Suggsの語るような歌い方が、物語性を強調している。
12. Are You Coming (With Me)
問いかけと勧誘の形で展開する、終盤にふさわしい静かな旅立ちの曲。
希望や未来というより、“過去から離れる”ことを選んだ人間の静かな決意を思わせる構成。
リリカルでありながら、決して甘くならないのがMadnessの真骨頂。
総評
『The Rise & Fall』は、Madnessが単なるスカ・バンドではなく、
イギリスという国とその人々の記憶、風景、日常を音楽で記録する“現代の民謡家”であることを証明した大傑作である。
都市と記憶、家族と国家、ユーモアと哀しみ、物語と構造。
そのすべてを詩と音楽で繋いだこの作品は、**ポップであることを決して軽視しない、“大衆音楽の理想形”**のひとつだと断言できる。
それはアルバムの随所に見られるイギリスらしい諧謔と詩情、ミュージックホール的構成、そして愛すべきローカリズムの力による。
“栄光と没落”というタイトルは、社会にも人にも当てはまる。
そのどちらもを笑いながら受け入れるMadnessの姿こそ、このアルバム最大のメッセージなのだ。
おすすめアルバム(5枚)
-
The Kinks – Village Green Preservation Society (1968)
ブリティッシュ・ポップによる郷愁の金字塔。『The Rise & Fall』の精神的先祖。 -
Blur – Parklife (1994)
Madnessの後継として、“日常と音楽の接点”を再定義した傑作。 -
The Divine Comedy – Promenade (1994)
文学的ポップと音楽劇的構成の融合。Madnessの芸術性と共鳴。 -
Ian Dury & the Blockheads – Laughter (1980)
ロンドン的ユーモアと風刺、ジャンル越境の在り方において共通点多数。 -
XTC – Skylarking (1986)
ポップと詩的視点、英国的アレンジ美学が炸裂した作品。Madnessの静的側面とシンクロ。



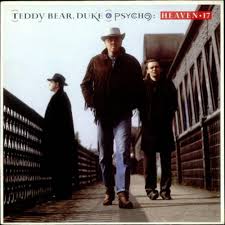
コメント