
発売日: 2022年1月21日
ジャンル: ポストパンク、アートロック
⸻
概要
『The Overload』は、イギリス・リーズ出身のバンド、Yard Actによるデビュー・アルバムであり、現代社会への鋭い風刺とストリート感覚に溢れた一作である。
このアルバムは、2020年代初頭のUKにおける“語り系ポストパンク”の潮流の中でも異彩を放ち、ユーモアと怒り、希望と諦念が交錯する「語りかけるような音楽」として注目された。
バンドは元Post War Glamour GirlsのJames Smithと、Menace BeachのRyan Needhamを中心に結成。
DIYスピリットとシニカルな視点を武器に、バンド結成からわずか2年でUKチャート2位という快挙を成し遂げた。
『The Overload』というタイトルは、“過負荷”の意味を持ち、情報社会、政治、経済、労働、階級、自己のアイデンティティが渦巻く現代に対する皮肉である。
それは“あまりに多すぎる現代”の中で、私たちは何を信じ、どう笑い、どう生き延びるのかという問いそのものである。
アルバムは、The FallやSleaford Mods、Talking Heads、さらにはArctic Monkeysの語り口にも通じる、話し言葉のようなボーカルスタイルを中心に展開され、英国労働者階級の現実や人間の矛盾を、乾いたユーモアとともに描いている。
⸻
全曲レビュー
1. The Overload
ノイジーなベースとファンク調のグルーヴが交錯するタイトルトラック。
主人公は“情報過多社会の中で自分を見失う市民”。
「It’s all just a bit of fun, until someone gets hurt」というラインが、軽薄さと暴力性の表裏を示している。
2. Dead Horse
ビートが軽快で、リズムの跳ね方はどこかTalking Heads的。
使い古された政治のメタファー「デッドホースを叩き続ける」というタイトルに、Yard Actらしい自虐的な知性が光る。
「どこまで怒ればいい?」という問いが、ポスト真実時代に刺さる。
3. Payday
労働者の夢と現実を描く皮肉なナンバー。
「ボーナスが出たら車を買う、それでどこかへ行く」といった夢想の語りが、徐々に資本主義の罠へと変化していく。
エレクトロ風味のベースラインが中毒的。
4. Rich
短いながらも毒気の強い楽曲。
“金持ち”と“庶民”の境界線を、あまりにあっけらかんと嘲笑する。
「They’re just like us, only richer」——この一言がすべて。
5. The Incident
中盤にして物語調の展開が加速する楽曲。
不条理な出来事が連鎖し、次第に現実感が揺らいでいく構成は、Kafka的ともいえる。
ギターが細かく鳴り続ける様は不安の再現である。
6. Witness (Can I Get A?)
宗教的フレーズ「Can I get a witness?」を借用し、社会への“証言”を求める。
群衆の声、沈黙の同調圧力が描かれ、パフォーマティブな怒りに対する皮肉もにじむ。
コーラスの盛り上がりが絶妙。
7. Land of the Blind
静かなイントロから徐々に高まる構成が美しい。
“盲目の国では片目の者が王”という格言を下敷きに、政治と支配、そして無関心について描かれる。
ダークでメランコリックな一曲。
8. Quarantine the Sticks
ロックダウン期の社会と人間を風刺的に描いたナンバー。
田舎に住む者たち、都会に出た者たち——分断された社会を、“棒で隔離する”という形で象徴化。
パンデミック後のUKを象徴する1曲。
9. Tall Poppies
7分を超える大作で、アルバムの核心とも言える物語的な曲。
“目立ちすぎた者は刈り取られる”という意味を持つタイトルに、UKの階級意識と小市民的精神が凝縮されている。
牧歌的なギターと語りが、静かな風刺を生む。
10. Pour Another
アルコールと自己欺瞞をテーマにしたビターな一曲。
「もう一杯注げば、すべて忘れられる」という現実逃避が、かえって痛々しい。
ジャズ的なコード感とリズムが心地よいが、背後には苦味が残る。
11. 100% Endurance
終曲にして、唯一「希望」があるように感じられるアンセム的楽曲。
「結局、誰もが100%で持ちこたえてるわけじゃない」という諦観と共感がにじむ。
歌詞もメロディも、包容力に満ちた美しい締めくくり。
⸻
総評
『The Overload』は、Yard Actが提示する“話すロック”の到達点であり、ポストパンクというジャンルに新たな息吹を与える作品である。
本作では、リフ主体のギターに跳ねるベース、乾いたドラムというシンプルな構成ながら、何より際立っているのはJames Smithの“語り”である。
彼の発話は、ニュースキャスターのようでもあり、近所の皮肉屋のようでもある。
語りとサウンドのテンポ感が絶妙に絡み合い、楽曲は「風刺小説」のような趣を持つ。
それはCharlie ChaplinやGeorge Orwellの系譜にも通じる、イギリス的アイロニーの継承であり、同時にアップデートでもある。
また、“政治的であること”が説教臭くならず、常に「笑い」と「観察眼」を伴っている点も重要だ。
特定のイデオロギーに固執せず、むしろ“どの視点も偏っている”というメタ批評性が、現代的である。
そして何より、ロックが“物語を語る”という原点に回帰している。
その語りは怒号ではなく、ウィットと脱力でできており、聴く者に問いかける余白を残す。
このアルバムは、今という時代に、音楽が“どう言葉を扱うか”を問い直した傑作であり、ポストパンクの先にある新たな「語りの美学」を提示している。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- Sleaford Mods『Spare Ribs』
Yard Actの先輩格にあたる語り系パンク。怒りとユーモアの融合。 - Dry Cleaning『New Long Leg』
話し言葉の語りと日常の観察が共通する2021年の傑作。 - The Fall『Hex Enduction Hour』
全ポストパンク語り系バンドの原点とも言える重要作。 - Fontaines D.C.『Dogrel』
アイルランド的語りと都市の詩が交錯するデビュー作。 - Arctic Monkeys『Tranquility Base Hotel & Casino』
物語性と語り口、そしてユーモアの構築美において接点がある。
⸻
7. 歌詞の深読みと文化的背景
Yard Actの歌詞には、明確な“階級意識”と“政治的懐疑”が横たわっている。
例えば「Payday」や「Dead Horse」では、労働者がシステムに組み込まれながらも、それに皮肉を投げかける視点が描かれている。
これは1970〜80年代のサッチャー政権時代に起きたUKパンクと、明確に地続きの感性である。
「Tall Poppies」は特に興味深く、地方都市における“夢を持つこと”と“それが許されない空気”を描いており、イギリス社会の“足を引っ張る文化”が背景にある。
これは日本社会における同調圧力とも通じるテーマかもしれない。
一方で「100% Endurance」は、それらすべての諦観と嘲笑を乗り越えた「連帯」の歌として響く。
つまり本作は、“怒りの果てに見える希望”を描く、静かなプロテスト・アルバムなのである。



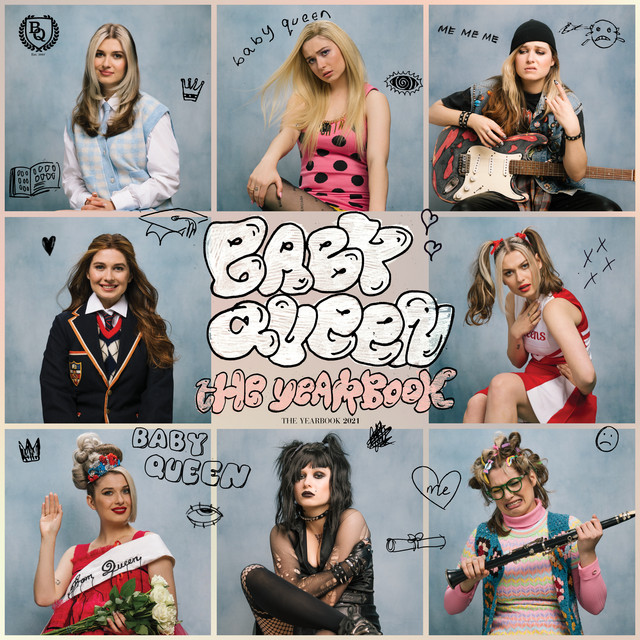
コメント