
発売日: 2024年10月25日(日本では若干前後の可能性あり) ウィキペディア+2Pitchfork+2
ジャンル: オルタナティブ・ロック、インディー・ロック、フォーク/サイケデリック要素も混在 Slant Magazine
概要
『The Night the Zombies Came』は、ピクシーズが2024年に発表したスタジオ・アルバムであり、バンドのキャリアにおいて 再構築期の新たな一章 を象徴する作品である。
本作は、旧来のベーシストであったパズ・レンチャンティン(Paz Lenchantin)を2024年3月に迎えて離脱、代わって英国出身のエマ・リチャードソン(Emma Richardson)が加入してからの初作品であるという点も大きな転換点である。 ウィキペディア+1
プロデューサーは、過去の再結成期アルバム(『Head Carrier』『Beneath the Eyrie』『Doggerel』)でもタッグを組んできたトム・ダルゲティ(Tom Dalgety)であり、本作でもその“第四期”とも呼べる体制を支えている。 Pitchfork+1
タイトル『The Night the Zombies Came(ゾンビが来た夜)』は、その字面だけをとってホラー趣味ともとれるが、実際にはホラーをそのまま主題化したものではなく、「ゾンビ」という言葉が象徴的・連想的に歌詞中に現れたため採用されたという。 ウィキペディア+1
音的には、アルバム全体が“映画的な連作短編集”のような構成を帯びていて、フォーク調の“ダストボウル”風バラードと、往年のピクシーズらしいパンク〜ロックの激走曲が交互に現れるという二極構成を、バンド自身が録音中に意識していたという。 Bass Magazine+1
それゆえ、再び“若き頃の混沌”をそのまま再現するのではなく、年輪を重ねたバンドが自らの歴史を反省・再解釈しながら、新たな音楽観を提示しようとしている作品と読むことができる。
全曲レビュー
(※13曲収録)
以下、収録順に沿って1曲ずつ解説する。音の特徴、歌詞のモチーフ、流れの中での役割に注目しながら読み進めてほしい。
1曲目:Primrose
冒頭にふさわしく、静かなアコースティック・フォーク風のイントロダクション。
“もし私を見かけたなら/我が娘と友に愛を”と歌う歌詞から始まり、穏やかな風景と儚さを描く。歌声も力が抜けており、バンドが“エモーショナルな段階”に入っていることがすぐに感じられる。
この曲がアルバムの「もう一方の顔」(ダストボウル系)を示す導入部として機能しており、後続の激しい曲とのコントラストを構築しているように思える。
2曲目:You’re So Impatient
いきなりテンポを上げ、ギターのカッティングとドラムの推進力が前面に出たロック・ナンバー。
“君はとてもせっかちだ”と直截的なタイトル/歌詞ながら、焦燥・欲望・待機というテーマを扱っており、バンドが再び“動く”ことを選んだことを示すような曲である。
初期ピクシーズが持っていた「静→爆発」の構造を、熟成された視点で再提示している。
3曲目:Jane (The Night the Zombies Came)
タイトル曲を含む一連の物語群の中心となる位置付け。
“ゾンビが来た夜”というイメージをそのまま借りながら、幼い記憶、逃走、夢と現のあわいなどが綯い交ぜにされている。
サウンド的には60年代フィル・スペクター的な壁のようなサウンド・レイヤーも感じられ、バンドの“ドラマ性”が強まっている。録音当初、メンバーは「蜂の群れに追われているようだ」と語ったという。 therockpit.net+1
4曲目:Chicken
ブルース・ロック的な匂いを漂わせる曲。
“チキン”というタイトルのユーモアと皮肉が歌詞に含まれ、喪失や願望、自己をからかうようなトーンもある。ギターリフとリズムの混ざり具合が印象的で、「バンドらしい遊び心」が出ている。
シングルカットもされたこの曲は、本作の“ロック寄り”フェーズを象徴する作品。
5曲目:Hypnotised
緩やかな始まりながら、中盤以降テンポと雰囲気が揺らぎを持って展開する。タイトルどおり“催眠”や“迷い”といったテーマが暗示され、歌詞における象徴性・寓話性が深い。
本作でギタリストのジョーイ・サンティアゴが歌詞を書いたという報もあり(厳密には前作からのステップだが)、バンドの内的変化が音に現れている。 Bass Magazine
6曲目:Johnny Good Man
ややブルージーで落ち着いたテンポのナンバー。
“ジョニー良い男”という名前が示唆する通り、自己反省/再出発/物語性を帯びた歌詞が展開する。ギター・ベース・ドラムのバランスが整っており、バンドの円熟期のサウンドが感じられる。
7曲目:Motoroller
タイトルどおり“モーター付きロール”=移動/疾走を主題にした曲である。
ギターのリフが回転するように刻まれ、歌詞にも“走る/止まらない”というモチーフが繰り返される。ロック寄りの位置付けだが、曲構成としては意外にも内省的なアウトロを伴っており、単純な疾走だけでは終わらない。
8曲目:I Hear You Mary
アルバム中盤・後半の静的な核。
“私は君を聞く/メアリー”というタイトルから、対話や懺悔、記憶というテーマが立ち上がる。サーフ・ロックのリフと低音のグルーヴが混ざる構成で、古くからのファンにとっても“らしさ”を感じさせる一曲である。レビューでも「遺骸の中を歩くような歌詞」と評された。 The Washington Post
9曲目:Oyster Beds
海辺/潮風/浅瀬といったイメージを伴ったバラード調。 “牡蠣の寝床”というタイトルが示すように、自然/生命/時間の流れを歌う。アルバムの“フォーク寄り”の顔がここでも明確だ。第3のシングルとして発表されており、その意味でも本作の多面性を示す。 LOS40
10曲目:Mercy Me
少しサイケデリックな響きを持つナンバーで、スローテンポ、長めの反響、余白を多く含んだ構成。タイトルの“ああ、哀れな私”という語感もあり、バンドの成熟したメランコリーが滲んでいる。
11曲目:Ernest Evans
タイトルが人名でもあり、過去のロックンロール/ポップ文化の参照を含んだメタ的な雰囲気がある。サウンド的にはミドルテンポ〜ややダークなロックで、アルバムの“語り物”セクションとして位置づけられる。
12曲目:Kings of the Prairie
“草原の王たち”というスケールの大きなタイトル。フォーク/カントリー的な香りを帯びつつも、ロックバンドとしての重量感を保っている。広がる音像がこのアルバム終盤の“旅”を感じさせる。
13曲目:The Vegas Suite
ラストを飾る“スイート(組曲)”という表現が示すように、変拍子・展開・アウトロ的要素を含む、幕の引きとしてふさわしい大作。録音時メンバーが「レコーディング終盤にこれを流したら完璧だった」という発言をしており、バンドがこのアルバムに一区切りを付ける意図を持っていたことがうかがえる。 therockpit.net+1
総評
『The Night the Zombies Came』は、ピクシーズがこれまでの「轟音と静寂」「ノイズとメロディ」の振り幅を、年齢と経験を経たうえで改めて設計し直した作品である。
初期のピクシーズをそのまま再現するのではなく、むしろ「初期を認識した上での成熟」という立ち位置が明確になっているように思える。
サウンド面では、プロデューサーのトム・ダルゲティが持つモダンなロック・プロダクションが本作でも機能しており、アナログ的な温度感とクリアな音像が両立している。レビューでは「過去と和解しつつ新たな方向へ踏み出している」などの言及もある。 Slant Magazine+1
ラインナップの変化も重要である。ベースがパズからエマ・リチャードソンに移行したことで、バンドの内部動力にも微細な変化が生まれており、それが本作の音調の多様性や構成感覚に反映されている。
テーマ面では、「ゾンビ」「死」「再生」「自然」「時間」「記憶」といったモチーフが散りばめられており、それらが単なるホラー的イメージではなく、人生の余白や静けさ、そして音楽的旅路として結実している。
ただし、批評・ファン双方から「初期の衝撃には届かない」「楽曲間の変化が大きくて統一感を欠く」との声もある。 dailycampus.com+1
それでもなお、本作は「再び生き続けるバンド」が選んだ道を誠実に描いた作品と見做せる。ピクシーズが過去のレガシーを背負いながらも、復刻ではなく再構築を選んだという点において、リスナーには大いに価値ある一枚であると言えるだろう。
結論として、『The Night the Zombies Came』は、ピクシーズが“生き残るための音楽”ではなく“生き続けるための音楽”を放った、静かな決意のアルバムなのだ。
おすすめアルバム
- Doggerel / Pixies — 本作のひとつ前、再構成期の直接的な前作。流れを掴むためにも。
- Beneath the Eyrie / Pixies — 再結成後の中期として、フォークや幻想的要素が強かった作品。
- Head Carrier / Pixies — 再結成期初期の“新しい出発”を示した作品。
- Surfer Rosa / Pixies — ピクシーズ原点。荒削りだが伝説的なサウンド。
- Doolittle / Pixies — 彼らの歴史における金字塔。今作の背景を知るうえでも重要な一枚。
制作の裏側
本作の録音は米・ヴァーモント州ギルフォードのスタジオ(Guilford Sound)で行われ、バンドは「曲が二つのキャンプに分かれてきた」と語っている。ひとつは“ダストボウル・ソング(Dust Bowl Songs)”と称された、カントリー/フォーク寄りのバラード系、もうひとつは“激走パンク系”である。 Bass Magazine+1
また、録音中にはアナログ機材の使用を積極的に取り入れ、ギター/ベース/ドラムのライヴ感を重視しつつ、現代ならではのプロダクション処理も併せ持つアプローチがとられた。
ベーシスト交代という内部変化もあって、エマ・リチャードソン加入後、バンドのダイナミックスが微妙に変わったという報告もある(バンドメンバー談では「彼女が入ってからグルーヴが変わった」とのこと)。
タイトルに関しても、フロントマンのブラック・フランシス(Black Francis)は「歌詞を全部チェックした結果、ゾンビという言葉だけが“なんとも言えない何か(je ne sais quoi)”を持っていた」と語っており、あえてホラー趣味に落とし込まない余白のある選択をしている。 ウィキペディア


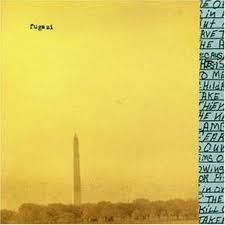

コメント