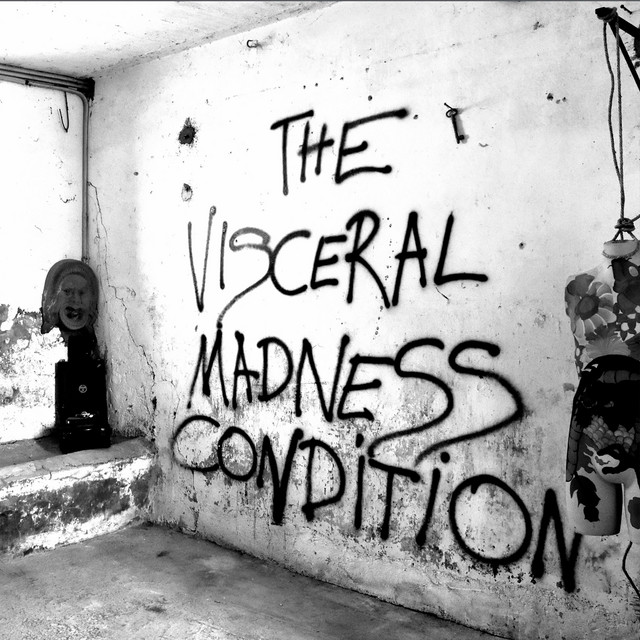
発売日: 1988年4月18日
ジャンル: ニューウェイブ、ポップロック、ブルー・アイド・ソウル、ソフィスティ・ポップ
概要
『The Madness』は、Madnessの解散後、中心メンバー4人(Suggs、Chas Smash、Chris Foreman、Lee Thompson)によって結成された同名バンド The Madness による唯一のアルバムであり、
1980年代の終わりに現れ、すぐに消えていった“影のマッドネス”の記録である。
1986年のMadness解散から2年、4人はバンド名に“The”を冠し、新たなプロジェクトを始動。
しかしMike Barson(鍵盤)、Daniel Woodgate(ドラム)ら主要メンバーの不在、さらにはプロデューサー不在のセルフプロデュース体制など、音楽的にも構造的にも未完成な不安定さが漂っていた。
サウンドはシンセやドラムマシンを多用したより打ち込み寄りのニューウェイブ・ポップ。
そこにかつてのユーモアやスカ的跳躍感はほとんどなく、都市の倦怠や失われた時間への皮肉が、洗練されたアレンジとともに静かに滲む。
商業的には失敗し、バンドも本作をもって解散するが、
その孤独と再構築への試行錯誤は、Madnessというバンドが“何によって支えられていたのか”を逆説的に浮かび上がらせる。
全曲レビュー
1. Nail Down the Days
アルバムはこの曲で始まる。
電子ドラムと淡々としたヴォーカルに支えられたこのトラックは、“何かを待ち続ける日々”の疲弊と諦観を、軽やかなグルーヴで描く。
バンド名を冠したアルバムの冒頭にして、すでに**“静かな終末”の気配**が漂っている。
2. What’s That
跳ねるようなギターとパーカッシヴなビートが印象的なナンバー。
歌詞は都市の雑踏と情報過多を風刺するような内容で、かつてのMadnessの諧謔精神を薄く残す。
とはいえ、音の抑制されたトーンがどこか孤立を感じさせる。
3. I Pronounce You
唯一のシングルカットにして本作最大のトピック。
中近東風の旋律と、儀式めいたリズムが交錯するこの曲は、政治と宗教、アイデンティティの不安定さを描いた異色の一作。
テーマ的にもサウンド的にも先鋭的であり、80年代末の混迷を内包する表現となっている。
4. Oh
メロウなコード進行とソウルフルなメロディが融合したブルー・アイド・ソウル風のナンバー。
恋愛の不安や無力感が漂い、愛の持つ曖昧さを冷静に見つめる視点が印象的。
Suggsの歌唱も控えめで、全体的に抑制された感情が響く。
5. In Wonder
ほのかな希望を感じさせるイントロから始まりながら、歌詞では**“期待しないこと”の哲学**が語られる。
“Wonder”=驚き、という言葉を諦めと並置する構造が印象的で、
知的で冷ややかなニューウェイブ・ポップの気配が強く感じられる。
6. Song in Red
アルバム中最も実験的なサウンドを持つトラック。
緊張感のあるギターリフ、ミニマルなドラムマシン、ポエトリー風のヴォーカルが交錯し、アート・ポップ的な意匠を見せる。
明快なメロディは少ないが、空気感の構築に特化したサウンドスケープは評価すべき点。
7. Nightmare Nightmare
ダークなタイトルどおり、不穏なシンセとタイトなリズムが支配する一曲。
内容も夢と現実の境界を揺らがせるような構成で、80年代末の精神的不安定さを音にしたような楽曲である。
この曲を中盤に配置するあたり、アルバムの“内向きな迷宮性”を象徴している。
8. Beat the Bride
愛と制度、儀式と個人というテーマをポップなラテン調に包んだ風刺的ナンバー。
結婚という構造の滑稽さを皮肉るリリックと、サウンドの軽快さの対比が効果的。
かつてのMadnessならもっと明るく突き抜けただろうが、ここではどこか抑制されているのが特徴。
9. Gabriel’s Horn
アルバムの中で最も“音楽ホール的叙情”を感じさせる佳曲。
天使のトランペット(Gabriel’s Horn)をモチーフに、救済を期待しながらもどこか醒めている語りが展開される。
音の抜けの良さと、哀愁を帯びたメロディが美しい。
10. 11th Hour
“土壇場”というタイトル通り、終わりの直前、ギリギリのところに立つ人間の心理を描いたクロージング・ナンバー。
歌詞も演奏も淡々としていながら、“すでにすべては過ぎ去った”という空気感が漂う。
アルバムの幕引きとしては完璧な“諦念と静かな希望”の音。
総評
『The Madness』は、Madnessというバンドの“欠落した状態”を音楽化したアルバムである。
そこにはかつてのスカや音楽ホールの跳ねるような明るさはほとんどなく、
代わりにあるのは洗練されたニューウェイブと、漂う空虚、そして都市生活者の孤独な視線。
完成度においては荒削りな面も多く、商業的には失敗に終わったが、
本作を通じて見えてくるのは、バンドのアイデンティティとは何かを逆説的に問う鋭い作品であるということだ。
“Mad Not Mad”の延長線上にありながら、より硬質でより諦念に満ちた音楽的遺言──
『The Madness』は、そんな音の影絵のような作品なのである。
おすすめアルバム(5枚)
-
David Sylvian – Brilliant Trees (1984)
内省的でソフィスティケイテッドなポップス。『The Madness』の精神性と共鳴。 -
The Style Council – Our Favourite Shop (1985)
政治意識とブルー・アイド・ソウルの融合。都市的抒情を共有。 -
China Crisis – Flaunt the Imperfection (1985)
洗練されたニューウェイブ・ポップ。感情を抑えた美学に接点あり。 -
Talk Talk – It’s My Life (1984)
電子と詩情の絶妙なバランス。ポップスの中の内省性。 -
XTC – Mummer (1983)
Madnessとは別の道を進んだ英国ポップのもうひとつの成熟例。


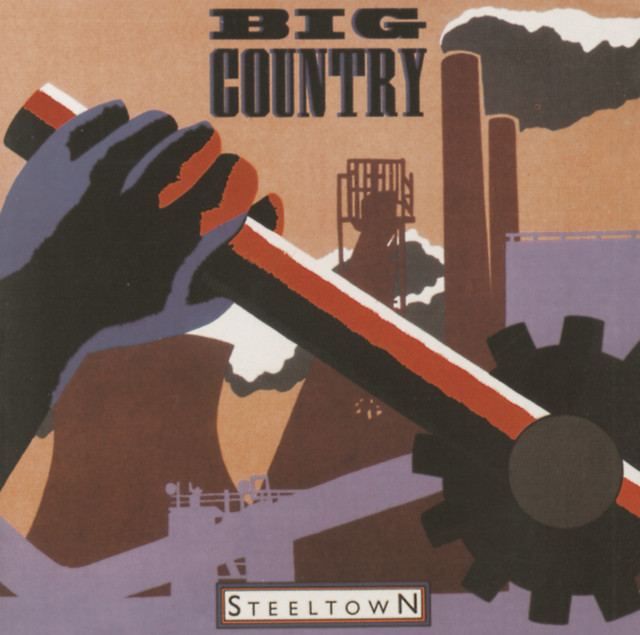
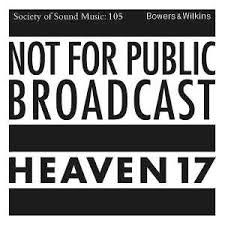
コメント