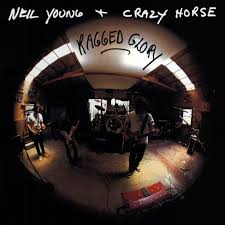
発売日: 1990年9月9日
ジャンル: ガレージ・ロック、グランジ、ハード・ロック
音の“ほつれ”に宿る真実——Neil Young、轟音の中に描いた祝祭と傷跡
『Ragged Glory』は、Neil YoungがCrazy Horseとの最強コンビで1990年に発表した17作目のスタジオ・アルバムであり、グランジ黎明期に突入したロックシーンの先頭で、轟音と即興性を武器に再び最前線へ躍り出た“老練なる若者”の記録である。
タイトルの“Ragged Glory(ほつれた栄光)”が象徴するように、音は粗く、構成はラフで、ギターはノイジーかつ奔放。だがそのすべてが、過剰な編集や洗練とは無縁の“生の美しさ”を掴みにいくヤングの信念を体現している。
ニールが90年代オルタナティヴ世代から“ゴッドファーザー・オブ・グランジ”と称されるきっかけともなった作品であり、Pearl JamやSonic Youth、Nirvanaらが崇めた“原型”の一枚でもある。
全曲レビュー
1. Country Home
10分近いジャムから始まる大作。ツアーと田舎、自由と疲労の交錯を描いたロードソング的ナンバーで、演奏の自然発火がまさに“生きているロック”。
2. White Line
アコースティック調ながら、ギターの掛け合いが光るミドル・チューン。“白い線”=ハイウェイやドラッグの暗喩とも解釈される、危うさと美しさが同居する一曲。
3. Fuckin’ Up
本作屈指の名曲。「またやっちまった…」と繰り返す歌詞が、自己破壊と赦し、そして愛情の矛盾をリアルに描く。 コール&レスポンス型の構造もライヴ映え抜群。
4. Over and Over
同じフレーズを反復する長尺ジャム。反復そのものが“感情のうねり”を形づくる、ポスト・ミニマル的な魅力。
5. Love to Burn
愛と時間をテーマにしたヘヴィな一曲。ゆったりとしたテンポながら、歪んだギターの波が感情の深部をさらけ出す。
6. Farmer John
60年代ガレージ・バンドThe Premiersのカバー。荒くれたパンク魂とカントリー的なノスタルジーが絶妙に融合。 ニールの趣味性が光る。
7. Mansion on the Hill
理想と現実、アメリカン・ドリームの崩壊を歌ったような寓話的楽曲。ミディアム・テンポながら重心の低い演奏がズシリと響く。
8. Days That Used to Be
ボブ・ディラン「My Back Pages」へのオマージュ。“過去は正しかったのか?”という内省が、優しくも鋭いメロディに乗せられる。
9. Love and Only Love
轟音のなかに“愛こそがすべて”という逆説的な希望が差し込む。ギター・ジャムの応酬と精神性が共鳴する、祈りのような一曲。
10. Mother Earth (Natural Anthem)
唯一のアコースティック曲にして環境讃歌。オルガンとスライドギターが導く“自然への賛美と人類への警鐘”で締めくくられる。
総評
『Ragged Glory』は、Neil Youngが40代にして“最もラウドで若々しい音”を鳴らした奇跡的アルバムであり、過去のどのロックとも違う、未来を切り開く原始的なエネルギーに満ちている。
ここには、ポリッシュされた音楽はない。あるのは感情のままに掻き鳴らされたギター、予測不能なグルーヴ、時に愚直なまでの繰り返し——つまり“リアルな音楽の運動体”。
1990年の音楽シーンの中で、ヤングは決して流行の中心にはいなかった。だがこの作品をきっかけに、彼は“グランジの父”として次世代の耳を惹きつけ、ニール・ヤングが過去の人ではなく“現在進行形のロックそのもの”であることを証明した。
おすすめアルバム
-
Sleeps with Angels / Neil Young & Crazy Horse
『Ragged Glory』の熱量と対照的な、死と夢を巡る内省的グランジ詩篇。 -
Mirror Ball / Neil Young & Pearl Jam
グランジ世代とヤングが邂逅した歴史的コラボ作。轟音の血脈が繋がる。 -
Daydream Nation / Sonic Youth
ノイズと構成、時間の歪みを操るアート・ロックの金字塔。『Ragged Glory』との精神的共振あり。 -
Tonight’s the Night / Neil Young
粗く、崩れた演奏の中に真実が宿るという哲学が最もむき出しになった1970年代の先駆。 -
Freedom / Neil Young
『Ragged Glory』直前の力作。静と動、政治と個人、すべてのヤングが詰まった傑作。


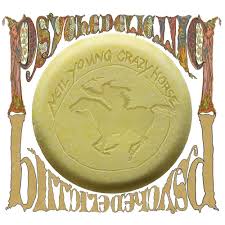
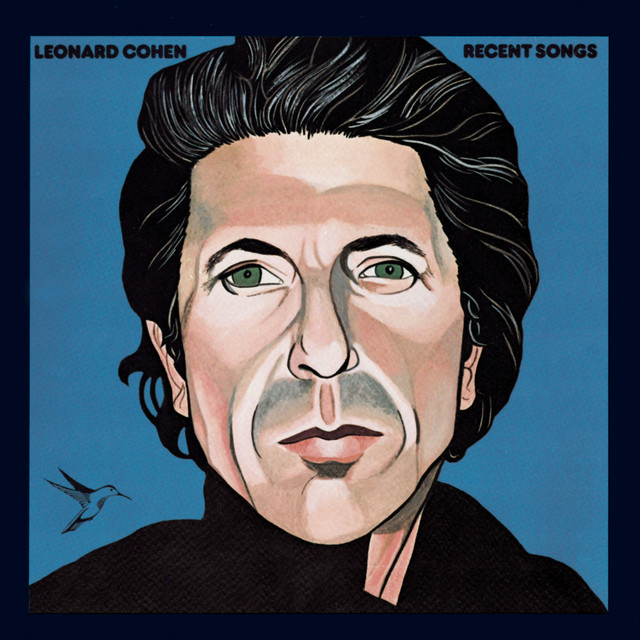
コメント