
発売日: 1998年(録音は1989年)
ジャンル: ディープ・ハウス、アシッド・ジャズ、ソウル、クラブ・ミュージック、エレクトロニカ
概要
『Modernism: A New Decade』は、The Style Councilが1989年に録音したものの、当時のレコード会社(Polydor)によりリリースを拒否された幻のアルバムであり、“ポール・ウェラーが解体直前に放った最後の挑発”であると同時に、“1980年代UKポップの終焉を告げる静かな爆弾”でもある。
1998年にようやく公式音源として陽の目を見るまで、本作は“ウェラー最大の問題作”として長く語り草になっていた。
その理由は明快で、本作が全面的にハウスミュージック――特にディープ・ハウスやアシッド・ジャズ――へと舵を切った、“ダンスフロア直結の完全クラブ・アルバム”だったからである。
これは、The Jamや初期The Style Councilでの政治的ポップ、ソウルフルな社会批評路線とは一線を画すものであり、当時のウェラー・ファンやレーベルにとってはあまりにも“逸脱”していた。
しかしポール・ウェラーにとっては、ハウスやクラブカルチャーは単なるトレンドではなく、“新しい世代の音楽的解放区”として映っていた。
本作はその世界へ自ら飛び込み、“古いポップの様式からの脱却と再出発”を模索する試みだったのだ。
結果的にこのアルバムがThe Style Councilの最終作となり、同年にバンドは解散。
それから約10年後にリリースされた『Modernism』は、時代を先取りしすぎた“未来から届いた遺書”のような響きを持つ作品として再評価されるに至る。
全曲レビュー
1. A New Decade
アルバムの幕開けは、ジャジーなコードとクラブ的な4つ打ちリズムが交錯するディープ・ハウス。
“新しい10年(90年代)”に向けた宣言的楽曲で、過去との決別と未来への静かな希望をにじませる。
ボーカルは最小限、リズムと空気感が主体。
2. Love of the World
ミニマルな構成の中に、“世界への愛”という普遍的かつ抽象的なテーマを込めたダンスチューン。
シンセパッド、ベースライン、反復フレーズが絡み合い、ウェラーなりの“ユートピアのビート”を目指した試み。
3. The World Must Come Together
社会的メッセージを残しつつ、アシッド・ジャズのテイストを感じさせる柔らかなサウンドが印象的。
“世界はひとつになるべきだ”というタイトルは、80年代ポリティカル・ポップの総括のようにも響く。
メッセージとグルーヴの融合を試みた佳曲。
4. Hope (Feelings Gonna Getcha)
このアルバムでもっともフロア直結型のハウス・トラック。
コーラスと鍵盤の絡みが美しく、“感情こそが真実を暴く”というテーマが、身体性と直結している。
もはやThe Style Councilの面影はほとんどないが、その“変貌ぶり”が鮮烈。
5. Sure Is Sure
チルアウト的な空間をまとった、メロウなエレクトロ・ソウル。
“確かなものは何もないけど、それでいい”というメッセージが、90年代的な相対主義への接近を感じさせる。
クラブカルチャーと個人主義の交差点。
6. That Spiritual Feeling
唯一、本作以前にEPで発表されていた楽曲で、ソウルとハウスの中間をゆったり漂うスピリチュアル・ダンスナンバー。
ディー・C・リーの美しいコーラスが彩りを添え、アルバム中もっともThe Style Council的な温もりを残す曲でもある。
7. Everybody’s on the Run
反復的なベースラインとパーカッシブなリズムが駆け抜けるアーバン・ファンク。
“誰もが逃げている”というフレーズが、政治・恋愛・日常のすべてを貫くメタファーとして響く。
デジタルビートに託された逃避と模索。
8. Can You Still Love Me?
アルバムの最後を飾るのは、極めて内省的なスロウ・ソウル・ナンバー。
アコースティック感のない機械的なトラックに、感情のこもったウェラーのヴォーカルが浮かび上がる。
“僕をまだ愛せるか?”という問いは、ファンにも、自分自身にも向けられた最終告白のように響く。
総評
『Modernism: A New Decade』は、The Style Councilというバンドが最後に選んだ“未来への跳躍”であり、“1980年代的ポップ”から脱却しようとしたポール・ウェラーの孤独な宣言である。
しかしそのジャンプは、まだ地面が固まっていない“次の時代”へと向かっていたため、当時は受け入れられず、失敗作と断じられた。
だが今振り返れば、本作はUKハウス、アシッド・ジャズ、エレクトロソウルの文脈で極めて先鋭的かつ誠実な挑戦であり、ポップ・アーティストの“変化を恐れない姿勢”そのものの記録と言える。
“モダニズム”という名にふさわしく、時代に先んじて過去を葬り、新しい言語を探し続けた人間の軌跡がここにある。
おすすめアルバム(5枚)
-
Young Disciples / Road to Freedom
90年代UKアシッド・ジャズの代表作。『Modernism』の精神的後継者。 -
Everything But The Girl / Walking Wounded
ポップアーティストがクラブミュージックへ接近した好例。遅れて来た“モダニズム”。 -
Paul Weller / 22 Dreams
ウェラーが自己再構築を成し遂げた野心作。『Modernism』以降の開花。 -
The Beloved / Happiness
90年代UKクラブカルチャーに寄り添ったメロディアスな電子ポップ。 -
Massive Attack / Blue Lines
政治性とクラブビートの融合という意味で、最も成功した“ニュー・デケイド”の象徴。


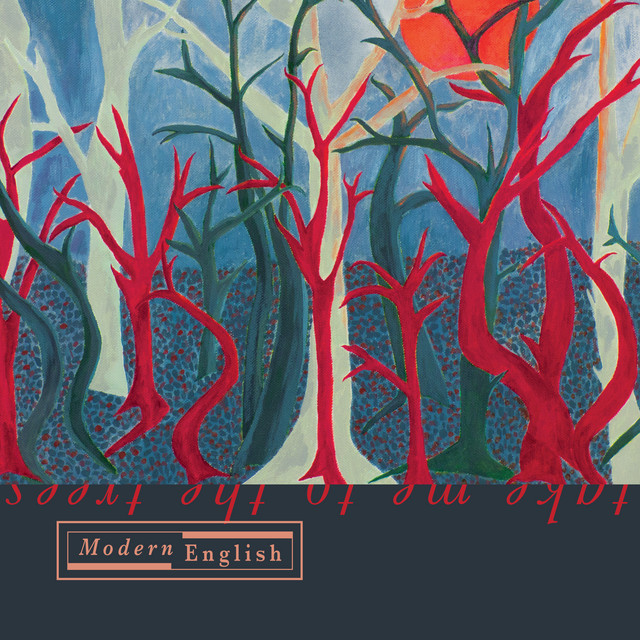
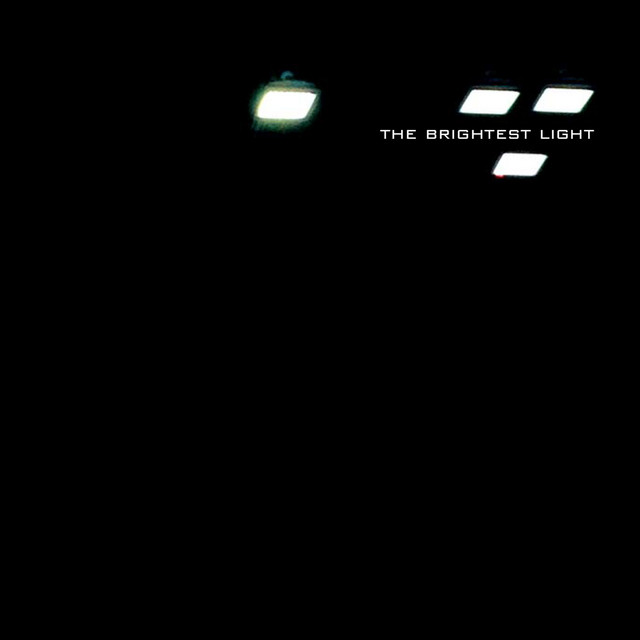
コメント