
発売日: 2004年11月1日
ジャンル: シンセポップ、ソフトロック、オルタナティヴ・ロック、アートロック
血ではなく記憶で語る——Manic Street Preachers、痛みのない喪失と美の境地
『Lifeblood』は、Manic Street Preachersが2004年に発表した7作目のスタジオ・アルバムであり、政治的怒りやギターの咆哮を抑え、より内省的で叙情的な世界観に傾倒した“静かなる異端作”である。
前作『Know Your Enemy』での混乱と爆発から一転、本作ではギターを控えめにし、シンセやストリングスを用いた透明感のあるサウンドスケープを構築。
「血液(Lifeblood)」というタイトルとは裏腹に、このアルバムに流れるのは熱い血ではなく、“記憶”や“感傷”といった冷たい美しさなのである。
歌詞はより個人的で、文学的・歴史的なイメージも織り交ぜながら、失われたものへの敬意や、過去との対話を丁寧に綴っていく。
怒りや混沌よりも、喪失と静かな諦念、そして淡い希望のような感情が支配する、異質にして繊細な傑作である。
全曲レビュー
1. 1985
アルバムの幕開けにして、美しくも切ないノスタルジア。1985年という象徴的な年を回想しながら、“今”との断絶を映し出す。
2. The Love of Richard Nixon
シンセ主導の政治バラード。「ニクソンへの愛」と題されてはいるが、実際は失敗者への共感と皮肉が交錯する一曲。
3. Empty Souls
メロディアスでありながらも、どこか空虚な響きを持つ。「空っぽの魂」とは、現代社会における実存の不在を映す鏡なのだろう。
4. A Song for Departure
別れをテーマにした叙情的なナンバー。心の温度がゆっくりと下がっていくような感覚が、旋律にそのまま宿っている。
5. I Live to Fall Asleep
“眠ること”がテーマの夢のような一曲。現実逃避ではなく、静かな受容の美しさが漂う。
6. To Repel Ghosts
ジャン=ミシェル・バスキアへのオマージュ。芸術と死の関係を通して、“過去に囚われること”への複雑な視点が提示される。
7. Emily
フェミニスト詩人エミリー・ディキンソンを讃える軽快なロックナンバー。詩的でありながらポップ、アルバムの中でも異彩を放つ。
8. Glasnost
ソ連時代の“グラスノスチ(情報公開)”をテーマにした楽曲。開かれたはずの未来がなぜか不安に満ちていたという逆説が響く。
9. Always/Never
二項対立をテーマに、「常に/決して」という言葉の反復が、愛と不信、記憶と忘却のあいだを揺れ動く。
10. Solitude Sometimes Is
孤独を“必要悪”として描いた静かなバラード。ピアノとストリングスの美しさが、心の深い場所をそっと撫でていく。
11. Fragments
締めくくりにふさわしい、断片的な記憶のモザイク。本作の主題=過去、記憶、再構築を象徴するかのような余韻の深い一曲。
総評
『Lifeblood』は、怒りではなく回想、破壊ではなく観察、そして激しさではなく沈黙によって語られるManic Street Preachersの異端作である。
ギターの代わりにピアノやシンセ、ストリングスが織り成す音空間のなかで、彼らは自身の歴史、時代、そして“いなくなった誰か”に語りかけるように歌っている。
この作品がリリース当時に賛否を分けたのは当然だろう。
だが、時を経て聴くとき、その繊細さと静かな誠実さが、Nicky WireとJames Dean Bradfieldの美意識の高さを証明していることに気づく。
まるで冷たい白い部屋で、過去のアルバムのジャケットを一枚ずつ眺めていくような時間。
それが『Lifeblood』というアルバムが与える体験なのだ。
おすすめアルバム
-
This Is My Truth Tell Me Yours / Manic Street Preachers
本作の前段にあたる、内省的なテーマと広がりのある音像を持った名盤。 -
The Kick Inside / Kate Bush
文学性と繊細な感情表現において通じる、美しくもミステリアスなデビュー作。 -
The Back Room / Editors
ポストパンク由来の冷たい音像と感情の引き算が印象的な作品。 -
Hopes and Fears / Keane
ギターレスでメロディを中心に据えた00年代らしい叙情派ロックの代表作。 -
The Future / Leonard Cohen
政治と内面、時代の不安と静けさを詩的に描いた重厚な作品。


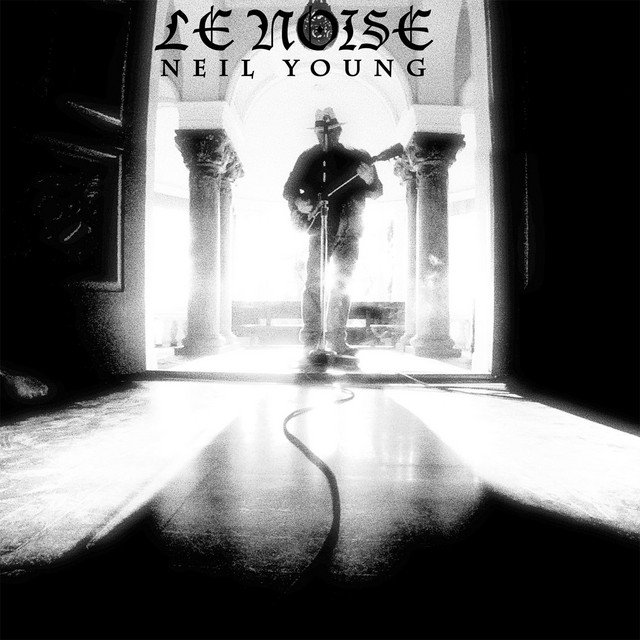
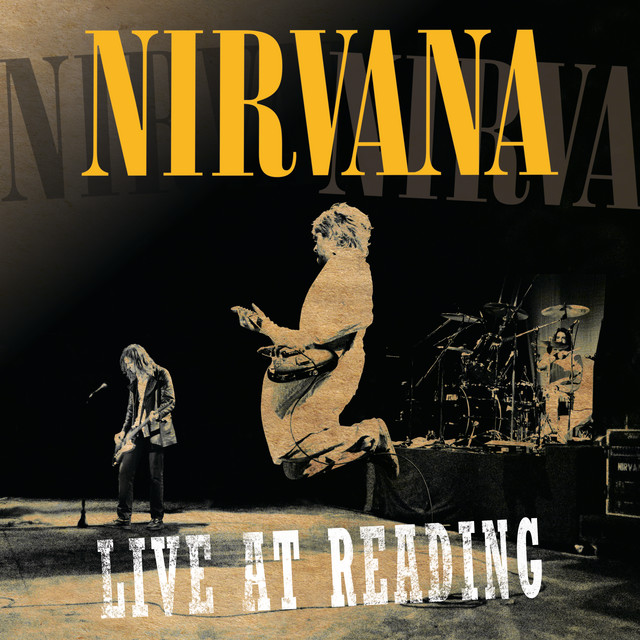
コメント