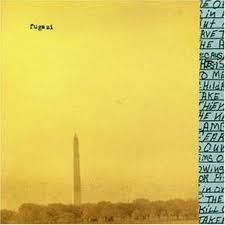
発売日: 1993年6月30日
ジャンル: ポスト・ハードコア、オルタナティブ・ロック
概要
『In on the Kill Taker』は、フガジが1993年に発表したサード・アルバムであり、
バンドのキャリアの中でも最も攻撃的で、最も緊張感に満ちた作品として知られている。
本作は、1990年の『Repeater』で築いたポスト・ハードコアの構築美と、
1991年のEP『Steady Diet of Nothing』でのミニマルなアプローチの延長線上に位置するが、
サウンドはより荒々しく、演奏は生々しく剥き出しだ。
つまり、理性と衝動が最も激しくせめぎ合った瞬間の記録である。
当初はスティーヴ・アルビニ(Nirvana『In Utero』、Pixies『Surfer Rosa』で知られる)をプロデューサーに迎えて録音されたが、
バンドはそのテイクに満足せず、最終的にTed Niceleyと**Don Zientara(Inner Ear Studios)**のコンビで再録音。
結果として、フガジ史上もっとも「火花の散る」サウンドが誕生した。
タイトルの “In on the Kill Taker” は直訳すれば「殺しの分け前に与る者」。
つまり、“暴力の構造に自覚的であれ”という警句でもある。
このアルバムは、社会的・政治的暴力を批判する知性と、
個人の内側に潜む暴力性への自問が交錯する、哲学的なハードコアなのだ。
全曲レビュー
1. Facet Squared
切り裂くようなギターリフで幕を開ける、最初の一撃。
ガイ・ピチオットの叫びとイアン・マッケイのコール&レスポンスが強烈で、
サウンドは混沌そのものだが、リズムは精密に制御されている。
「顔の断面(Facet)」というタイトルは、社会の多面性と個人の分裂を暗示している。
2. Public Witness Program
社会批評性の高いナンバー。
メディアと群衆の関係を冷ややかに描く。
「公的証人プログラム」という皮肉なタイトルが、情報社会の匿名性と責任の欠如を突く。
演奏は切迫感に満ち、フガジの最も“政治的な瞬間”のひとつ。
3. Returning the Screw
不安定なテンポとギターのノイズが織りなす緊張の連続。
タイトルは「ネジを巻き戻す」=制度や暴力の再生産を意味する。
ベースのジョー・ラリーが作るミニマルなリフが、まるで機械のように無感情で美しい。
4. Smallpox Champion
フガジの社会意識が最も明確に出た曲。
“天然痘のチャンピオン”というタイトルからも分かるように、
アメリカの軍事的・文化的侵略を比喩的に批判している。
ガイのボーカルが狂気じみており、リズムの反復が暴力のループ構造を象徴している。
5. Rend It
「裂け目」を意味するタイトルどおり、音が縦に裂けていくような感覚を持つ。
途中でのブレイクと再爆発のコントラストが見事。
イアンとガイのツインボーカルが“対話する怒り”を作り出す。
6. 23 Beats Off
変拍子を多用した実験的なトラック。
“23拍ずれた”というタイトルが示すように、拍のズレが社会の不協和を象徴している。
静と動の切り替えがスリリングで、まるで爆発寸前の空気を音にしたようだ。
7. Sweet and Low
インストゥルメンタル曲。
ギターの反復とディレイが美しく、フガジの瞑想的側面が表れる。
アルバムの緊張を一時的に解きほぐす「間(ま)」として機能している。
8. Cassavetes
映画監督ジョン・カサヴェテスへのオマージュ。
インディペンデント映画の巨匠に捧げられたこの曲は、
芸術における誠実さと独立性をテーマにしている。
“この世界に妥協するな”というメッセージが痛烈。
9. Great Cop
軍隊や権威を風刺した、短くも強烈なナンバー。
“いい警官”という言葉の裏に潜む暴力の正当化を暴く。
ハードコアのスピード感と知的皮肉が完璧に噛み合っている。
10. Walken’s Syndrome
タイトルは俳優クリストファー・ウォーケンの特徴的な話し方に由来するとされる。
リズムの切り方が不安定で、まるで会話が乱れるような感覚を持つ。
音楽的にはポストパンク的構築の極致。
11. Instrument
ダークで内省的なギターリフから始まる、アルバム終盤のハイライト。
“楽器”というタイトルだが、歌詞ではむしろ人間が制度の道具になる恐怖を描いている。
フガジが常に警鐘を鳴らしてきた「個人の主体性」のテーマがここでも貫かれている。
12. Last Chance for a Slow Dance
アルバムを締めくくる、哀切と力強さを併せ持つ名曲。
タイトルどおり“最後のスローダンス”という穏やかな比喩の中に、
終末と再生のテーマが潜んでいる。
ギターの反復とボーカルの抑制が美しく、
このアルバムのカタルシスを静かに描き出すラストトラックである。
総評
『In on the Kill Taker』は、フガジのキャリアの中で最も“緊張した音”が鳴っているアルバムである。
それは演奏の激しさではなく、理性と感情の均衡がギリギリのところで保たれているという意味でだ。
この時期、アメリカではオルタナティブ・ロックが商業的成功を収め、
同じワシントンD.C.の地下から出てきたフガジにも、メジャーからの巨額オファーが殺到していた。
しかし彼らはすべてを拒否し、Dischord Recordsでの完全独立を貫いた。
その倫理的緊張感が、そのままこの作品の音になっている。
サウンド面では、イアンとガイのツインギターが互いに反発しながら絡み合う構造が極限まで進化し、
ジョー・ラリーの変則的ベースラインとブレンダン・キャンティーのドラムが支える。
結果として、ポリリズム的ハードコアの究極形がここに完成している。
『13 Songs』が怒りの純度を示した作品だとすれば、
『In on the Kill Taker』は怒りを芸術の構造へと昇華したアルバムである。
また、この作品を通してフガジは単なるパンクバンドではなく、
“思想を鳴らす集団”としての存在を世界に確立した。
社会的テーマ、抽象的詩作、構築的演奏――そのすべてが一つの極点に達している。
それは、後のAt the Drive-InやRefused、Mars Voltaにも多大な影響を与え、
ポスト・ハードコアの美学を決定づけた。
おすすめアルバム
- Repeater / Fugazi (1990)
初期の理想と構築性が融合した代表作。フガジの原点を知るならこれ。 - Red Medicine / Fugazi (1995)
音響的実験と自由度が増した中期の傑作。 - The Argument / Fugazi (2001)
最終作にして成熟の極み。静寂と緊張が共存する。 - Liar / Jesus Lizard (1992)
同時期のシカゴ・サウンド。スティーヴ・アルビニ制作の荒々しい質感が共鳴する。 - Dirty / Sonic Youth (1992)
ノイズと政治性を兼ね備えた90年代オルタナのもう一つの頂点。
制作の裏側
初期録音はシカゴのスティーヴ・アルビニのスタジオで行われたが、
そのサウンドはあまりにも粗く、バンドの意図するバランスとは異なっていた。
イアン・マッケイは「アルビニの録音は素晴らしかったが、あまりに“外側の暴力”に寄っていた」と語り、
最終的にワシントンD.C.へ戻り、Don ZientaraとTed Niceleyのチームで再録音した。
その再録音が功を奏し、アルバムはローファイの生々しさとスタジオ的精度の中間点を得た。
また、制作時にはバンド内部にも緊張が走っており、
その“張り詰めた空気”が、アルバム全体の緊迫したサウンドを生んでいる。
イアンは当時こう語っている。
“僕らの音楽は怒りではなく、抵抗のための設計図なんだ。”
『In on the Kill Taker』は、まさにその言葉どおり、
暴力を超えて“思考としてのハードコア”を実現した作品である。
知性と衝動のせめぎ合い――その緊張の記録が、今もなおこのアルバムの中で燃え続けている。


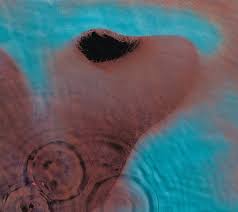

コメント