
発売日: 2009年3月24日
ジャンル: ファンク、エレクトロ・ポップ、ニュー・ウェイヴ
概要
『MPLSound』は、2009年に発表されたプリンスのアルバムであり、彼が長年追求してきたファンクと電子音楽の融合を再び先鋭化させた作品である。
同時期にリリースされた『Lotusflow3r』『Elixer』(ブランディ・エレヴァンと名義)との3枚組構成の一部として登場し、彼の多面的な音楽性を象徴する位置づけとなっている。
タイトルの“MPL”は、彼の拠点であるミネアポリス(Minneapolis)を指し、80年代初期の「ミネアポリス・サウンド」を現代的に再構築するという意図が込められている。
つまり本作は、シンセサイザー主体のリズムマシン・グルーヴ、乾いたスネア、そして艶やかなファルセット・ヴォーカルといった、かつてのプリンスらしさを意図的に蘇らせた原点回帰的電子ファンク作品なのである。
制作はすべて彼自身による宅録スタイルで、ほとんどの楽器・プログラミングを自ら担当。
『1999』や『Controversy』の頃を思わせるビート感の中に、2000年代的なデジタル音響処理とポップな感性が共存している。
プリンスが再び自らの都市「ミネアポリス」へと音楽的帰還を果たしたという点で、キャリアのひとつの円環を描くアルバムでもあるのだ。
全曲レビュー
1. (There’ll Never B) Another Like Me
アルバムの幕開けを飾るのは、プリンスらしい自信とエゴの宣言ともいえるファンク・トラック。
軽快なリズムマシンと鋭いベースラインの上で、彼は「俺のような奴は二度と現れない」と高らかに歌う。
1980年代的な電子ファンクを再現しながらも、ヴォーカルの多層処理が現代的で、過去と現在を結ぶ橋のような一曲である。
2. Chocolate Box (feat. Q-Tip)
ヒップホップ・アーティストのQ-Tipを迎えたコラボレーション曲。
スラップ気味のシンセベースと遊び心あるトークボックスが絡み合い、ファンクの遺伝子を未来型に変換したような実験性を持つ。
プリンスのヴォーカルとQ-Tipのラップの対比が、ジャンルを超えたリズム対話を生んでいるのが印象的だ。
3. Dance 4 Me
ダンス・フロア志向のエレクトロ・ファンク。
メロディはシンプルながらも、リズム構成の緻密さが際立ち、クラブ文化へのラブレターのようにも聴こえる。
後年、リミックス盤やDJセットでも人気を博し、プリンスがEDM以降の流れを先取りしていたことを示す一曲である。
4. U’re Gonna C Me
この曲では一転して、内省的でアンビエントな電子ソウルが展開される。
1980年代後半のバラード曲を想起させるメロウなトーンに、現代的なシンセパッドが重ねられており、孤独とロマンスの狭間を漂うような余韻を残す。
5. Here
ドライなドラムマシンが刻むビートの上に、シンプルなコード進行とリバーブのかかったヴォーカルが響く。
「君がここにいれば」という繰り返しのフレーズが印象的で、ミニマルな構成による精神的親密さを描き出す。
6. Valentina
当時のスーパーモデル「ヴァレンティナ」を題材にしたとされる軽快なポップ・ナンバー。
恋愛ソングとしては異例の明るさを持ち、ギターと電子リズムのバランスが『Around the World in a Day』時代のサイケ・ポップ的要素を思わせる。
7. Better with Time
スロー・テンポのバラードで、成熟した愛と時間の流れをテーマにしている。
アコースティック・ギターの響きが電子的トラックの中で柔らかく光り、過去作『The Gold Experience』の叙情性を思い起こさせる。
8. Ol’ Skool Company
アルバムのハイライトともいえるファンク・ジャム。
ブラスの代わりにシンセを使ったアンサンブルが炸裂し、まるで1982年の「Controversy」が21世紀にアップデートされたかのよう。
プリンス自身の社会風刺的な語りもあり、政治と音楽を結びつける彼のスタンスが健在であることを示す。
9. No More Candy 4 U
終曲は、短く鋭いエレクトロ・ファンクの小品。
リズムマシンの乾いた質感とコミカルなヴォーカル処理が、アルバム全体を軽やかに締めくくる。
「もう甘いお菓子はおしまいだ」というタイトルには、享楽的ポップカルチャーへの皮肉も滲む。
総評
『MPLSound』は、プリンスの音楽的アイデンティティを再定義した作品である。
彼は80年代に築いたミネアポリス・サウンドを再び自らの手で解体・再構築し、電子音楽の時代にふさわしい形で提示した。
その方向性は決して懐古ではなく、むしろ自らが築いた遺産を現代的ツールで再発明するという自己再生のプロジェクトであった。
デジタル録音環境の冷たさを、プリンス特有の官能的なグルーヴで温める技術は健在で、彼が時代の変化に決して取り残されなかったことを証明している。
『Lotusflow3r』がギター主導のロック寄りサウンドだったのに対し、『MPLSound』は完全にクラブ/シンセ中心。
この二面性が、彼の音楽家としての柔軟性を如実に示している。
また、本作のエレクトロニックな質感は、その後のインディ・ポップやR&Bシーン(例えばThe WeekndやJanelle Monáeなど)にも間接的な影響を与えたといえる。
商業的には大ヒットとまではいかないが、プリンスの本質をもっともよく伝える晩年の作品の一つとして高く評価されている。
それは、彼が単に流行を追うのではなく、自身のサウンド哲学を時代ごとに更新していった稀有な存在だったことの証左なのだ。
おすすめアルバム
- 1999 / Prince (1982)
本作の原点となるエレクトロ・ファンクの金字塔。 - Controversy / Prince (1981)
政治的テーマと電子ファンクが融合した初期の代表作。 - Lotusflow3r / Prince (2009)
同時期リリースで、ギター主体のロックサイドを示す姉妹作。 - Sign o’ the Times / Prince (1987)
社会派かつ実験的なプリンスの最高傑作のひとつ。 - Parade / Prince (1986)
アートポップ的な美学とファンクの融合が際立つ名盤。
制作の裏側
『MPLSound』は、プリンスの自宅スタジオ「Paisley Park」ではなく、ミネアポリス郊外の宅録環境でほぼ独力で制作された。
彼はこの時期、レコード会社との契約から完全に独立し、独自のオンライン販売サイト「Lotusflow3r.com」を立ち上げていた。
この自由な体制こそが、彼の創作に再び火をつけたのだ。
使用機材としては、Linn LM-1ドラムマシンやヴィンテージ・シンセサイザー(Oberheim、Prophet-5など)を多用。
80年代の音を再現しつつ、Pro Toolsによる現代的な編集でシャープな質感に仕上げている。
結果として、『MPLSound』は、デジタルとアナログの理想的な融合点に立つ作品となった。


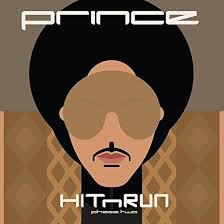

コメント