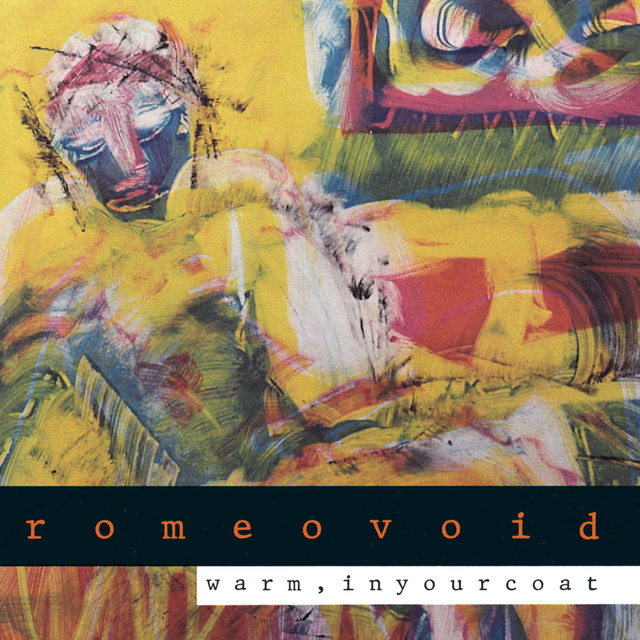
1. 歌詞の概要
「A Girl in Trouble (Is a Temporary Thing)」は、Romeo Void(ロメオ・ヴォイド)が1984年にリリースしたメジャー・レーベル移籍後のシングルであり、同年のアルバム『Instincts』に収録された代表曲である。
タイトルの「A Girl in Trouble(困難にある少女)」という言葉に続く「Is a Temporary Thing(一時的なことよ)」というフレーズは、社会が女性に対して持つ偏見や軽視、そして一時的な存在として“消費”する構造を強烈に風刺している。リスナーは最初、慰めのように響くこの言葉が、実は非常に皮肉的で、冷酷な現実を暴いていることに気づくだろう。
曲全体は、社会的ステレオタイプ、ジェンダーの権力構造、そして女性の主体性に対する鋭い問いかけで構成されており、同時にそれを、ファンク・ポップ風の洗練されたサウンドとダンサブルなビートで包み込んでいる。この対比──辛辣な歌詞と軽快なリズム──こそが、この楽曲の核心的な魅力である。
2. 歌詞のバックグラウンド
Romeo Voidはサンフランシスコ出身のポストパンク/ニューウェーブ・バンドであり、1979年から1985年にかけて活動していた。「Never Say Never」のような荒々しく挑発的な初期の楽曲とは異なり、「A Girl in Trouble」ではより洗練された音像とポップ・ミュージックとしての表現力を前面に押し出している。
この曲はバンドにとって最大のヒットとなり、全米チャートで最高35位を記録するなど、一般的な注目を集めた作品でもある。しかしそのメロディの明るさとは裏腹に、歌詞のテーマは極めてシリアスだ。特に女性ヴォーカリストであるデボラ・アイヤルの低く語りかけるような歌唱には、怒りでも悲しみでもなく、「観察者」としての冷静な視線が宿っており、聴く者に深い不穏さを与える。
デボラ・アイヤルはネイティブ・アメリカンの出自を持ち、詩人でもあり、自身の身体性やルックスを武器にしたフェミニズム的な表現を重視していた。彼女が描く“トラブルの中の少女”とは、メディアや社会が消費する“被害者としての女性像”であり、そのステレオタイプを静かに、しかし明確に崩そうとしている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
この曲のサビは、あまりにもアイロニカルな美しさで印象に残る:
A girl in trouble is a temporary thing
困ってる少女なんて一時的なものよ
この一節は、女性の痛みや経験が“一時的”と見なされ、物語として消費されていく様子を示唆している。“trouble(困難)”とは、単なる恋愛問題か?虐待か?孤独か?どのような意味をとっても、それが“temporary(刹那的)”であるとされることの暴力性がここにはある。
She’s the kind who gets lost easy
彼女はすぐに道を見失うタイプHe’s the kind who’ll take advantage
彼はそれを利用するタイプ
ここでは、典型的な加害/被害の構図が描かれている。しかし語り口は冷静で、ジャーナリスティックですらある。それが、この曲のメッセージをより鋭くしているのだ。
(出典:Genius Lyrics)
4. 歌詞の考察
「A Girl in Trouble」は、その題名からも明らかなように、社会が女性をどのようにラベル化し、記号化し、消費していくのかを描いた楽曲である。その語りは憐憫や激情ではなく、どこまでも冷静で、まるで実験観察のような距離感を持っている。
この“距離”こそが、楽曲の強さである。女性の痛みや弱さを、ポップ・ソングの文法で語るとき、しばしばそれは“ロマンチックなもの”に変換されてしまう。しかしアイヤルはそれを拒否する。むしろ、リスナーの側がその変換を無意識にしてしまうこと自体が、“トラブルの中の少女”という構造を強化しているのだと示唆している。
また、「一時的なもの」と言い切ることで、彼女は皮肉にも“少女”を“一過性の存在”としてしか捉えない社会の冷たさを再現している。その言葉の裏には、“誰も本気で向き合っていない”という痛烈な批判が込められている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Girls Just Want to Have Fun by Cyndi Lauper
楽しさと自由の裏に、女性の社会的制限への反抗が込められたポップ・アンセム。 - I Am Woman by Helen Reddy
70年代フェミニズムを象徴する、自立した女性の誇りを歌った力強いバラード。 - Brass in Pocket by The Pretenders
魅力と力を同時に武器にする女性の視点を描いた、クールでセクシーなロック・ナンバー。 - Human Behaviour by Björk
人間関係の奇妙さとジェンダーの境界を超えた視点で描く、抽象と本能が融合した楽曲。
6. “少女”をめぐる文化構造:声なき存在から主体へ
「A Girl in Trouble」は、ポップの形式に潜む“構造的な暴力”を暴いた、非常にラディカルな作品である。Romeo Voidは、見た目には踊れるポップ・ソングを作りながらも、その内部に鋭利な批評性を仕込むことで、80年代の主流音楽シーンに異物のように切り込んだ。
この曲における“少女”は、保護されるべき存在でもなければ、単なる被害者でもない。むしろ彼女は“語られる存在”から、“語る存在”への変容の過程にある。デボラ・アイヤルの声は、決して同情を求めない。かわりにリスナーを見据え、無言で問いを投げかける。
Romeo Voidの「A Girl in Trouble」は、ポップの皮をかぶった社会批評であり、音楽におけるジェンダー表象の限界を揺さぶった希少な楽曲である。言葉少なに、それでも確実に、“その痛みを消費しようとするあなた自身”に向けて鋭い刃を向けている。その静かな攻撃性が、この曲をいまなお特別なものにしている。


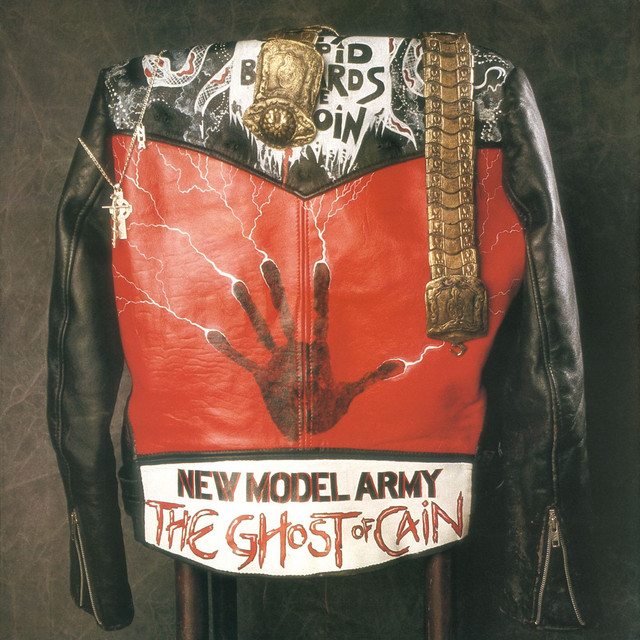
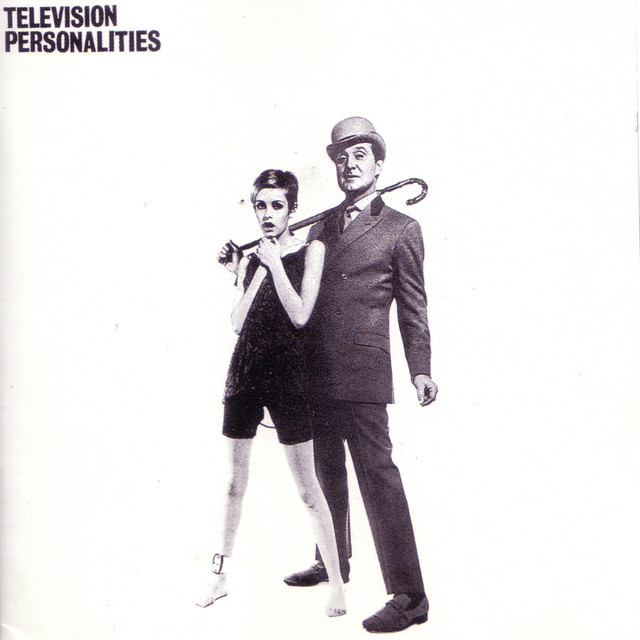
コメント