
発売日: 1973年9月
ジャンル: ハード・ロック、ブギー・ロック
概要
『Hello!』は、イギリスのブギー・ロックバンド Status Quo が1973年に発表した6作目のスタジオ・アルバムであり、彼らの音楽的アイデンティティが完全に確立された転機の作品である。
本作は、初めてイギリスのアルバムチャートで1位を獲得したことで商業的にも大きな成功を収め、以降の“Quoサウンド”を方向づける礎となった。
前作『Piledriver』(1972年)で始まったヘヴィでリフ主導のブギー・ロック路線が、本作においてさらに深化し、硬質なギターリフと一体感あるリズムセクションが全面に押し出されている。
メンバー全員が黒の衣装に身を包んだジャケットも話題を呼び、ロックバンドとしてのヴィジュアル面においても象徴的な時期となった。
全曲レビュー
1. Roll Over Lay Down
アルバム冒頭を飾る、典型的なブギー・ロックの快作。
反復的なギターリフとタイトなリズムが一体となり、まるでライブ音源のような臨場感を放つ。
フランシス・ロッシとリック・パーフィットのギターの絡みがシンプルながら圧倒的な迫力を生む。
2. Claudie
アコースティック・ギターと穏やかなメロディを主体にしたバラード調の楽曲。
シンプルなラブソングながら、どこかメランコリックな雰囲気が漂い、アルバムの中でよいアクセントとなっている。
3. A Reason for Living
ゆったりとしたテンポで展開されるミッドバラード。
“生きる理由”というタイトルにふさわしく、やや内省的なトーンを持ちつつ、バンドとしてのサウンドの厚みを損なっていない。
4. Blue Eyed Lady
ファンキーなリズムとブギーの融合が面白いナンバー。
パーフィットによるリードボーカルが、女性への欲望と憧れを軽妙に描き出す。
ギターリフとベースのうねりがクセになる一曲。
5. Caroline
シングルとしてもヒットした、Status Quo屈指の代表曲。
イントロのアップテンポなカッティング・ギターから一気にテンションが高まり、ライブではオープナーとして頻繁に演奏される定番。
シンプルかつ直感的な構成がバンドの美学を体現している。
6. Softer Ride
力強いギターにドライブ感あるドラムが加わり、典型的なQuoスタイルのロックンロールが展開される。
“やわらかな旅”というタイトルとは裏腹に、スピード感あふれるアンサンブルが爽快。
7. And It’s Better Now
控えめなピアノと落ち着いた歌唱による異色の楽曲。
バンドのブギー・ロック路線とは一線を画し、感傷的な歌詞が染み入る。
アルバム内での緩急のバランスを担う一曲として重要。
8. Forty Five Hundred Times
10分を超える大作であり、アルバムのハイライト。
複数のパートからなる展開がありながら、どこまでも“グルーヴ”と“リフ”に忠実。
即興性と構築美が融合したライブ向きの名演で、クライマックスにふさわしいスケール感を持つ。
総評
『Hello!』は、Status Quoが長年にわたり貫く“ブギー・ロック”のフォーミュラを確立した決定的アルバムである。
リフ主体の構造、タイトでドライブ感あるアンサンブル、無駄のない構成――それらすべてが本作で明確な形となり、“Quoらしさ”が確立した。
また、シンプルであることを恐れず、むしろ反復の中に快感と高揚を生み出す構造は、ロックの原初的な力を思い出させてくれる。
キャッチーでありながらハード、ルーズでありながら一糸乱れぬグルーヴ――この相反する要素の共存こそが、Status Quoの真骨頂であり、本作が今なお多くのロック・ファンに愛される理由なのだ。
おすすめアルバム(5枚)
-
Status Quo – Piledriver (1972)
『Hello!』の前作にして、ブギー・ロック路線の始まり。荒削りな魅力が光る。 -
AC/DC – High Voltage (1975)
リフ主体のハード・ブギーが共通。Status Quoの音楽性をさらに剛直化したようなサウンド。 -
ZZ Top – Tres Hombres (1973)
南部風のブギー・ロック。リズム重視のロック感覚が近い。 -
Humble Pie – Smokin’ (1972)
ブルースとロックの混交によるグルーヴ重視型サウンド。 -
Slade – Slayed? (1972)
UKハードロック/グラム的側面を持ちつつ、シンプルなリフとノリ重視のアプローチが共鳴。


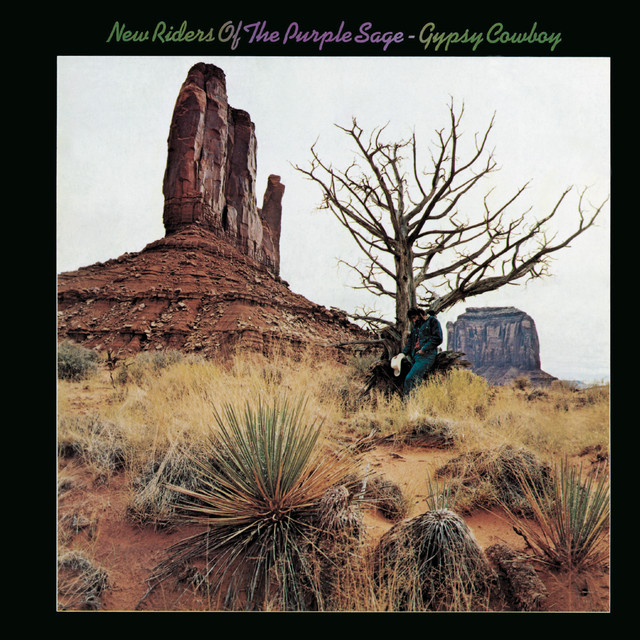
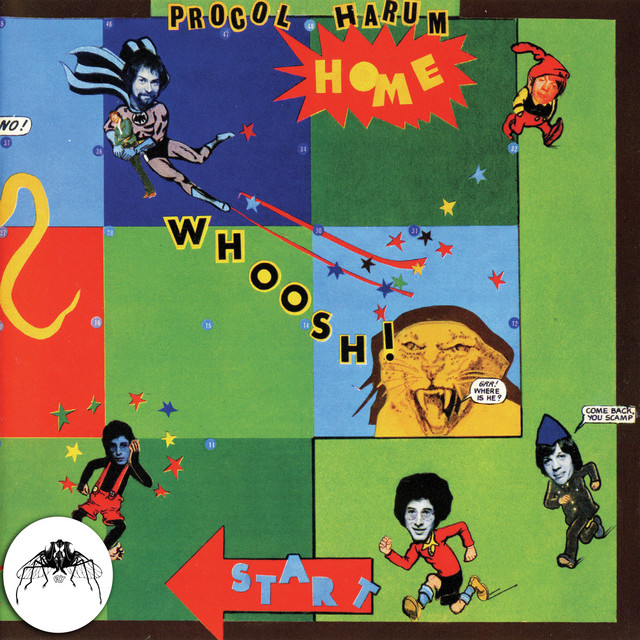
コメント